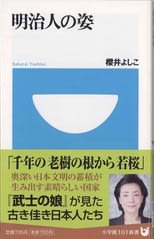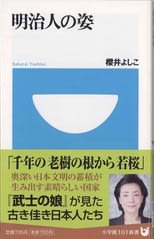
明治人の姿 (小学館101新書)
新渡戸稲造著「武士道」、岡倉天心著「茶の本」、杉本鉞子著「武士の娘」、これらは外国で高い評価を得て日本に逆輸入の形で和訳された本である。
「武士道」「茶の本」については、相当数の和訳本が出ている。
「武士道」については、国立国会図書館の「近代デジタルライブラリー」で、明治41年3月刊行の、桜井彦一郎訳のものを公開している。
http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40004040&VOL_NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0
藤原正彦氏の『国家の品格』でとりあげられて、再度の日の目を見た感じだが、若い人たちに是非読んでもらいたいと思う。私は手ごろに三笠書房の文庫本で、奈良本辰也訳本を読んでいる。
「茶の本」については、幾つかの和訳本を読み比べられた秀逸のサイト
茶の本-和訳と評論について があり、大変興味深い。
http://tubakiwabisuke.cool.ne.jp/tensin.tyanohon.html
又、青空文庫では村岡博訳によるものを見ることができる。
www.aozora.gr.jp/cards/000238/card1276.html
私も二冊異なった和訳本を持っている(S41版・浅野晃訳、S47版・ソートン・F・直子訳)が、最近原文「Book of Tea」が収録された、桶谷秀昭の「茶の本―英文収録」が 講談社学術文庫から出ているようだ。英語はからきし駄目な私だが、恐いもの見たさで購入しようかと思っている。
「武士の娘」は、大岩美代の訳本を二・三年前読んだ。越後長岡藩の家老であった家に、明治六年に生まれた女性の自分史だが、「厳しい躾と教養」に裏打ちされた武士の娘の生き様が外国で評価されて、これも逆輸入されて紹介された。
最近この本を取り上げて、櫻井よし子氏が「明治人の姿」という著作を出している。「真の自由は、行動や言語や思想の自由を遥かにこえて発展しようとする精神的な力」であり、われわれ現代人が忘れてしまった明治人の気概を「武士の娘」から見出そうとしている。自由を履き違えた現代人には、耳の痛い内容だが、一方では100%納得させられる。共に一読をお薦めする。
永六輔の「明治からの伝言」という本を捨てられずにいる。
私の心の中に大きな位置を占める、母方の祖母の思い出と共にある。