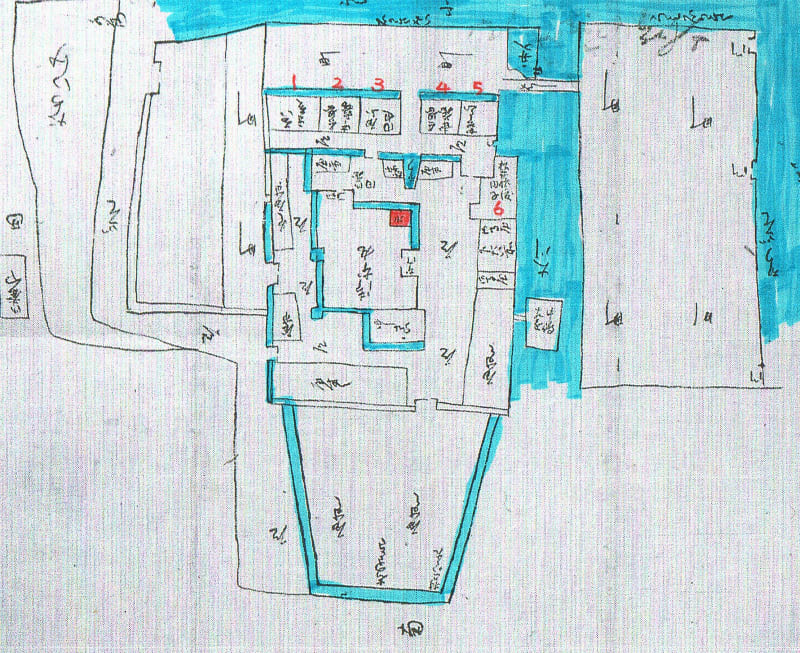吉田神道家の援助者としての細川家のことが、綿考輯録・巻31(忠利公・上巻p173)に見える。
これは光尚と烏丸家の御弥々の祝言に関わる記述に紹介されている。
つまり「御弥々殿は萩原殿へ御養子之御約有之候得共、いまた烏丸殿へ御座候・・云々」という記事に続いている。
此萩原殿と有之ハ右兵衛督兼従朝臣の事也、吉田兼治朝臣之御二男、御母は忠興君の御妹後浄勝院、豊国大明神の神主にて領壱万石なりしに、豊国社荒廃後領地も上り散々の体ニ而候を、忠興君段々仰立候趣を以、豊後国ニ而千石之知を領し堂上ニ被列候、寛永十年九月朔日萩原殿より三斎君江御書之内ニ、今度ハ拙者儀ニ付、種々被入御情、忝奉存候とあるも此の事なるへきか、又寛永十一年閏七月、忠利君より酒井讃岐守殿江之御書
一書申入候、萩原殿之儀豊国へ被遣候時も万事 権現様御直判を以被仰出、知行之儀も勿
論右之分ニ御座候、此御書物三ツ内慶鶴と御座候ハ、萩原殿雅名ニ而御座候、又豊後にて
千石被下候時も、三斎へ御奉行衆より慥被仰聞候由候、秀頼より御申渡候儀ハ一ツも無御
座候、御書出三ツ則懸御目候、恐惶謹言
閏七月二日
酒井讃岐守様
人々御中
右此御書ハ、萩原殿豊国神主之時、領地之証書被進候哉との問に、御答被成候かと見え申候、按るニ、太閤秀吉を豊国大明神と勘免之比ハ、秀頼公御幼稚にて、家康公諸事御はからひなるゆへ、家康公の御判なるへき事勿論なり、所詮萩原家之事三斎君大方ならさる御周旋の次第、彼御家ニは今ニ厚く慕はるゝ由
右ニ付而高本慶蔵覚書左之通
六所大明神神主行藤上総介藤原保定云、昔年為学問在京し、吉田の松岡仲良か許にありける比、
仲良命にて萩原佐兵衛督兼嶺卿の御三男に、句読なとさつけ申とてたえす参りけるに、ある時
兼嶺卿仲良か許に参り給ひて、保定にむかひて明日は三斎祭をするなり、そなたハ肥後の人こ
とに細川の家臣なるよし、折から幸なれハ、朝飯後より來りてゆるりとかたらるへし、其案内
に來りたるとのたまふ、難有御事なりと領掌して、仲良にそのよし申けれハ、実々かの御家に
ハ年ことに祭り給ふ、奇特に思ひよられたり、かならす参らるへしといふ、明の日仰のことく
参りけれハ、いつものかわりて奥のかたにめしてかたのことく饗応し給ふ、上総介不審におも
ひ、いかなれハ御家にて三斎をまつらせ給ふにやと申けれハ、不審もつともなり、さらハ事長
けれともそのよしを語るへし、余か先祖ハ吉田家の息なりしを、豊国の祠たてられける時、一
万石を寄せられてその神主になされたり、しかるに此祠破却の時、からくのかれ出て吉田にか
へりひそまり居けるを、そなたもしりつらん、三斎所縁あるにつけて、関東にさま/\申こと
わり、一万石の家廃亡すれハ千石を給ふ例なりとて、あなかちに愁訴せらる、三斎申さるゝ事
なれハさすかに黙止しかたく有けん、豊前中津の辺にて千石の地あて行ハれて、堂上に列し
たり、されとも所領海をへたてゝ物事便ならさりけれハ、その後やう/\に申ことはりて、今
は畿内に点しかへられたり、されハ余か家領ハまたく三斎の庇護なれは、家のあらんかきり疎
略すへからすとて、年々に祭りををするなり、此よしミにてさき/\ハ細川家ニも絶す書通を
もしたりしに、いつの比にやかの家よりことはり申さるゝむねありて、今は音問をたにせす、
心の外の事なり、余か家にとりてハかく疎略にてハ過しかたき事なるそ、折もあらハかの家の
有司にそのよしをもかたりてよ、かゝる事なれハけふそなたをまねきたり、心よく一献をもす
くしてよとて、ねんころにもてなし給ふ、その日は三斎君御忌日なりしや、又ハ二三月比なり
しや、年久しく事にてたしかにハ覚へすとそ、
右ハ寛政二年戌十二月八日上総介物語之趣也、此方様より御取遣御断之事不分明、天明七年未十一月よりハ又々御取遣等有之候由、萩原殿より上総介江右物語之年月も覚不申由、且又慶長より寛永迄は豊前ハ一円ニ 忠興公御領地ニ而候処、壱万石萩原殿御知行とあるも、始は 忠興君御領之内を分被進たるにても可有之哉、又豊後御代官地之内なるを萩原殿にてハ後年豊前と被心得候哉、尚可考
豊国社に対する家康の処置は言語に絶するものがあった。のちには入口を塞ぐように建てられた妙法院の仕打ちにより、豊国廟は墓参さえ難しくなり、まったく顧みられることさへない有様となった。神主・吉田家の興亡もまた豊国社とともにあった。忠興存命の時代は妹・伊也の聟・吉田兼治の家の事でもあり、彼の政治力が如何なく発揮されたことが良くわかる。
その後幾たびか将軍家においても豊国社再建の機運が上がったというが、妙法院が家康の言を楯にとり拒んだため、実行されることはなかった。明治廿年に至り再建の機運が満ちみち、三十一年に竣工を見たのである。秀吉没後三百年の年であった。
津田三郎の著作「秀吉・英雄伝説の奇跡」は豊国社と萩原氏の不遇な歴史と、明治に至ってからの豊国神社の再建のことなど大変委しく書かれている。
然し上記の六所大明神神主行藤上総介の言については、触れられていない。
萩原兼従はその後神道家として大成し、没後は吉田山の神海霊社に祀られた。その社前に立つ石の鳥居は万治三年十一月、宇土支藩細川行孝が寄進したものである。その所以は、家記には登場しないが行孝は幼少期萩原兼従の許で育てられたとある。
兼従の母・浄勝院(伊也)は忠興の妹であり、兼従と行孝は叔父・甥の間柄である。なぜ行孝寄進の鳥居がここに存在するのか、津田三郎氏は御承知であっただろうか。














![熊本藩の社会と文化[蓑田勝彦]](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7230/9784906897230.jpg?_ex=200x200&s=2&r=1)