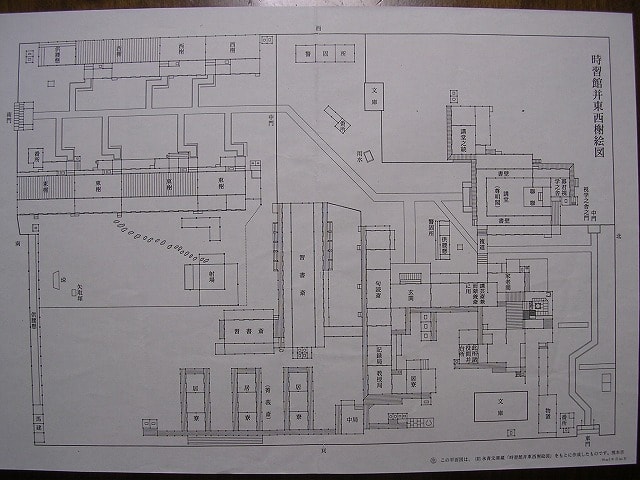三三七
覺
一諸手永御年貢納方皆濟目録之儀、當秋各別被仰付候、然
處被及御沙汰候受米無御座候分ハ、年内皆濟難成手永可
有御座哉、其分ハ先つ假目録差出、年内相濟申筈ニ候、
右假目録之儀は、本目録之通帳面仕立、諸御蔵御銀所よ
り受取手形相添、年内現米銀納申筈候、稜々高何程之内
何程は何月幾日迄何を以相納、殘何程不納と書記、假目
六差出候様
一例年正月十一日諸御代官より皆濟目録以後、米銀を以相
納候趣、又は春夏其外諸受米帳面ニ仕立、十一日目録差
出來候、當秋ハ右之通被仰付たる儀候得は、十一日目録
仕立方之儀左之通
一莨受米 一薪受米 一種子受米
一水夫受米 一麥受米
右受米有之候手永は、皆濟目録差出候以後、何程は何方
へ相納候との趣、毎之通帳面仕出候様、右受米無之手永
は、御知行取御扶持米方手取米、又は御切手取御扶持方
其外春以後手永ニ受居候分を書裁、十一日目録差出候
様、尤右帳面仕立様之儀は、御吟味方へ承合候様
但、年内納方皆濟不仕手永も、假目録差出申儀ニ付、
是又十一日假目録を差出候様
右之通可致沙汰候間、御仲間中えも御通達夫々不洩様可
有御達候、以上
寶暦六年子閏十一月九日 御郡間
三三八
覺
一御鷹之野御供中、寒朝又は寒風之節、末々共寒気難儀仕
候者も可有之候、其外湯茶等も給候事ニ付、彼是為見繕
御案内役ニ歩御小姓相添被差出、寒強節は於村方焼火ニ
ても仕候様ニ相應之薪を調相渡申筈ニ候、其外湯茶をも
快給候ため、右湯茶を出し候百姓ニは相應之茶代をも相
渡候筈ニ候、右之通ニ付村々ニて相對ニ薪等を出せ焼火
等は堅不仕、右支配人之差圖相守候様可被申付候、若心
得違之物有之、支配人之差圖相背候ハヽ、委ク承届急度
相達候様及沙汰候、畢竟御供之末々迄へ被為附御心、且
又在方少しも迷惑不仕様ニとの御事ニ候、右之通被仰付
候間、此旨被相心得、彌以末々迄相慎候様、家来/\へ
も重疊可被申付候、以上
寶暦六年十一月
三三九
一御侍中所持之開立山之儀、先祖以来之持傳、或ハ追々相
求、近来之内開を立山ニ被仕立、又は年久敷所より、畝
數之相違も有之、地床紛敷相聞候ニ付、段々吟味しら
へ相濟候付て、今度御郡間根帳相改候、依之開立山所持
之面々ヘハ、畝數之書付を根帳ニ割印を用、後年とも為
證跡、銘々ニ被渡置筈ニ候、勿論右割印之書附無之開立
山は、證跡正敷申傳有之候とも、御赦免之内ニは加へ不
申候、尤以来右所持之開立山を譲渡候節ハ、今迄之通、
双方より之願書ニ右割印之書附相添、其所え御郡代へ可
被相達候、遂讃談及沙汰候節、右割印之書附も調替、御
郡代へ差越、譲受之面々へ御郡代より被相達筈候事
同年十月日
三四〇
覺
一去年度々之天災ニ付て、諸御郡共下方至極及難儀候様子
相聞候、依之為御救、格別之譯を以、當秋之儀御蔵納・
御給知共、御土免貮歩下ヶ被下候間、此段可有沙汰候事
但、損引ニ出候方ハ、土免崩候事ニ候得は、沙汰之外
ニ候、以上
寶暦六年正月
三四一
一新地方・御郡方新地共、通方相成候得は、二ノ口・増水
夫米ハ被成御免筈之由、大塚甚蔵へ高橋氏被申聞候事
一御山奉行御用ニ付廻在仕、各會所え休泊等之節、賄入目
之事
一黑米 三合宛 一賄分之飯米朝夕共同断
一雑事代三十文 右鹽噌・野菜・茶・薪代共
一黑米 貮合 晝飯
一菜代 十文 右同断
一一領一疋・地侍御用ニ付指出候節、右同断
右御山奉行は、廻在之節加扶持不被下、一領一疋・地侍
ハ元より無給・無扶持之事ニ候、前々より在賄を受來候
由、依之以後迚も同前ニ候、乍去飲食之儀、限りなきも
のにて、其入目分量不極置候ては、各會所幷村方ニても
との位ニ仕候哉とあやふみ、間ニハ超過之儀も加有之哉
と存候付、右之通極候事
但、此賄、會所より仕出候てハ、不圖調味之失墜も可有
之候間、各手前之給物ニ添調可被申候、只朝夕各被申
給候通之事ニて濟し可被申候、左候て賄料は各へ、其
時々會所より仕向可申候、此賄ひたとハ有之間敷候ニ
付、時々之仕向難成程之事は有之間敷候、尤通帳仕立
置、何月幾日何之何某、何御御用ニて罷出候入目と委
敷記し置、各判を用置、暮出銀割之節、右之通帳前ハ
我等共加印を取、會所年中出来銀帳ニ一稜ニ書のせ、
右之賄ハ賄通ニて見しらへ申事ニ候
右御山奉行・一領一疋、手永・村々ニても賄入目之事
一黑米 三合宛 一賄朝夕共同断
一雑事代三十文 右鹽噌・野菜・茶・薪・油代とも
一黑米 貮合 晝飯
一菜代 十文
右之通ニて賄可申候、左候て當春及沙汰置候出来銀、村
々根帳と書印、其砌當番之組頭見届、判前無之加印は仕
間敷候
但、右之面々罷出候御様筋、一村ニかヽり、又ハ五ヶ
村組ニかヽり、或惣村ニ渡り、扨又まひとびの村へ聞
申様成違有之候間、庄屋共手前ニて此差別いたし、難
分節は各へ伺取計可申候、若村々まひとび、又ハ惣村
ニわたり申節ハ、庄屋共之取計にて之出来銀之割合も
成兼可申候間、此儀は各より可有指圖候
手代・小頭共、村々へ罷出候節之賄之事
一粟 六合宛 一賄朝夕共同断
但、代米割賦致し候ハヽ、替口〆米三合
一雑事代拾文
一粟三合 晝飯分
一雑事代四文
右之通ニて庄屋より賄、村出来銀帳ニ其手代・小頭より
自筆ニて、或ハ朝、或ハ晝・晩と日記を致せ置、時々當番
之組頭も見届せ、左候て其役人印形を仕置可申候、惣て
手代・小頭共、村々ニ入込候儀各日々ニ不存候て不叶事
ニ付、上ニ右之村々根帳、會所へ出候上、虚實を糺可被
申事
但、手代・小頭共成たけハ村賄受不申様、勘辨可仕候、
自他ハ不及申、他村たり共方角能所ハ宿へ歸り認可仕
候、併一概ニは論かたく、御用之緩急ニより可申候、
たとひ居村・隣村たり共、はつし候て宿迄歸り候儀難
成節は、其所ニて認可仕候、此分かちハ右根帳を各見
届被申候へハ、忽邪正知レ申儀ニ候事
右之通相改候間、左様相心得、以来役人共ハ勿論、小百
姓迄如是改之儀承届居候様、若吟味之節不承と申者有之
候ハヽ、各可為越度候、以上
寶暦五年亥十二月