細川内膳家に於かれては、忠隆公の三人の姫の生母は正室であった前田利家の女・千世姫であろうとされている。
忠隆公は父・忠興によって離婚を言い渡されたが、これに復せず廃嫡されたが、暫くの間同居していたのだろうと推測されている。
長女の徳姫(西園寺左大臣實晴簾中)の生年は、永源師壇紀年録に記録があるが慶長十年生まれだとある。(p123)
前田家の記録によると、慶長五年六月、利家の正室・芳春院(まつ)は、家康に対する謀反の疑いで前田家が危機に瀕し、自ら江戸へ證人となり下った。
気に成る事は娘「千世姫」のことであり、千世が前田家に帰り村井長次に嫁いだが、その長次に対し「お千世に会いたい、お父上(前田八家・村井又兵衛)とともに、お千世を江戸へ下してほしい」と懇願している。
又兵衛は芳春院のために江戸と加賀を往復しているが、この事が実現したかどうかは前田家の記録でも判らないらしい。
判っているのは、慶長十年より前の話だという事がわかる。それはこの又兵衛が慶長十年に江戸で死去していることである。
そしてその時期、母・芳春院をあんじながら、千世は加賀で村井長次と共に暮らしていたのである。

10月10日(火)〜 12月2日(土)
上天草市・天草市・苓北町 連携企画
島原大変肥後迷惑―「自然災害伝承碑」までの道のり―
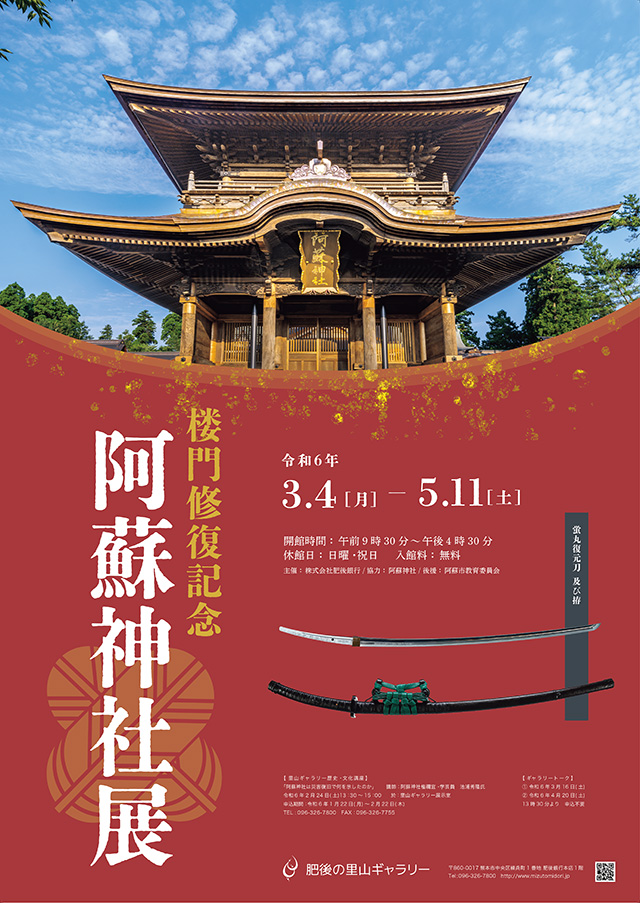
史料や災害伝承碑を通して、先人が残した伝言を未来へ伝える展覧会です。
| 会期: | 2023年10月10日(火)〜 12月2日(土) |
|---|---|
| 時間: | 9時30分〜16時30分 |
| 休館: | 日曜・祝日 |
| 催し: | ■ギャラリートーク 11⽉11⽇(⼟) 島原⼤変の⾃然災害伝承碑 ※いずれも13:30 ~ 14:00 場所:ギャラリー展示室 申込不要 |
熊本大学永青文庫研究センターのサイトを開きましたところ、を始められたことが判りました。
先ずは「クラウドファンディング」の案内のようですが、稲葉先生も大変ですね。
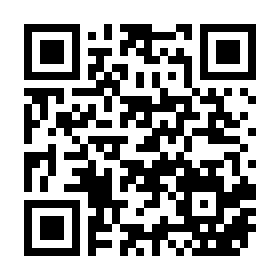 URL https://twitter.com/eisekiken_kuma
URL https://twitter.com/eisekiken_kuma
加賀前田家に関することで、私の認識不足とまた新しい発見があった。
細川忠利の江戸證人としての江戸在住は慶長5年の正月25日だとされる。一方加賀前田家に於いても、利家室まつが江戸證人となったが、私は慶長4年の事と承知していたが、これが間違っていた。
慶長4年閏3月3日、前田利家が亡くなった後、9月に至ると「家康暗殺計画」「首謀者は前田利家」という報告が家康のもとにもたらされた。
利長は領国経営の為に帰国しており当地にはいない。居城伏見城から大坂城に入った家康はその危機を回避したが、この計画に関わったとされる「浅野長政、土方雄久、大野治長」は流罪に処せられた。
そして、加賀征伐が企てられるが、利長は弁明にこれ勤め11月に入ると、横山長知を江戸に遣わしてさらに家康に弁明に勤めた。その結果慶長5年和睦に至り、前田利常(利長嫡男)に珠姫との婚約が成立、徳川家との関係悪化を案じた利家室の「まつ」(芳春院)が自ら江戸證人になるとして当時住まいしていた伏見を5月下旬に立ち、6月6日に江戸に入ったという。
何故細川家はそれを遡る事5ヶ月、早々に忠利を江戸に送ったのだろうか。
『看羊録』という姜![]() (カン・ハン、日本読みはきょうこう)という人物が書いた著があるが、ここには「秀頼を奉じる利長は、家康に劣らぬ勢威があった。利長は諸大名とともに、『家康を殺して、その土地を分けよう』と謀り、血盟した。この謀略を佐和山城の石田三成が知り、家康に書状で伝えた」としてその諸大名を「上杉景勝、伊達政宗、佐竹義宣、宇喜田秀家、加藤清正、細川忠興」と記している。
(カン・ハン、日本読みはきょうこう)という人物が書いた著があるが、ここには「秀頼を奉じる利長は、家康に劣らぬ勢威があった。利長は諸大名とともに、『家康を殺して、その土地を分けよう』と謀り、血盟した。この謀略を佐和山城の石田三成が知り、家康に書状で伝えた」としてその諸大名を「上杉景勝、伊達政宗、佐竹義宣、宇喜田秀家、加藤清正、細川忠興」と記している。
姜![]() は、豊臣秀吉の第2次朝鮮出兵で捕虜となり、日本で3年間幽閉された人物で、日本の国情を本国に手紙で送ったのだが、それが『看羊録』なのだが、当時これが知られることは無かったろうが、当時の状況を知る上では興味深い。
は、豊臣秀吉の第2次朝鮮出兵で捕虜となり、日本で3年間幽閉された人物で、日本の国情を本国に手紙で送ったのだが、それが『看羊録』なのだが、当時これが知られることは無かったろうが、当時の状況を知る上では興味深い。
母・芳春院の江戸證人としての江戸下向に対しては、加賀家中では反対が多かったらしいが、芳春院の決意は「いはんや君(秀頼か)の御ため、世のため、又は子を思ふ心の闇には、何をか思ひきわめて侍らんとて、やすやすと思ひたちぬ」との強い決意による行動である。
さて、細川家に於ける忠興の想いは如何であったろうかと想像するのである。

本能寺からお玉が池へ ~その⑰~ 医局・西岡 暁
露の世は 露の世ながら さりながら(小林一茶)
さはさりながら、夏逝きてまた「露」の季節がやって来ました。
秋景色と言えば、露以上に(?)紅葉ですね。「お玉ヶ池」が元「桜が池」だったように、江戸にはよりも桜の名所が多いようです。それに対して、「本能寺」のある京都には日本を代表する紅葉の名所が幾つもあります。そう云えば、佐倉は他の木々よりいち早く紅葉すると云います。「蕉門十哲」の一人・内藤丈草がその桜紅葉を詠んでいます。
早咲の 得手を桜の 紅葉かな (内藤丈草)
[20]吉田山
そんな訳で、この「本能寺からお玉が池へ」の道行も里帰り(?)の日を迎えたようです。
数多の京都の紅葉の名所が集まっているのが「東山」一帯です。東山は、皆様ご存知のように京の街の東に連なる山々のことで「東山36峰」と呼ばれます。「36峰」と云うのは、比叡山から南に如意ヶ嶽(=大文字山)を経て稲荷山に至る35の峰々と如意ヶ嶽の西に(鹿ヶ谷を挟んで)孤立する吉田山から成っていて、合わせて36峰になります。
吉田山に鎮座する古社「吉田神社」(859年(貞観元年)創建)の信長・秀吉時代の宮司は、吉田兼見(1535~1610)でした。兼見の父・吉田兼右は、ガラシャの夫・細川忠興の祖母・智慶院の兄で、兼見の子・兼治の妻は忠興の妹・伊也です。
吉田兼見は、元々明智光秀とは親しい間柄でした。「本能寺の変」の5日後に勅使として光秀を安土城に訪ねた兼見は、その日の日記に光秀が「今度謀反の存分」を語ったと書いています。ただ残念ながら「謀反の存分」の内容は記されていません。その翌々日、光秀は上洛して兼見の屋敷を訪れ、朝廷の五山(山ではなく、天龍寺等5つの寺のことです。5寺の中東福寺等三寺が東山にあります。)と大徳寺への献金を兼見に託しています。このように吉田山は、(吉田神社の兼見を通して)「本能寺の変」とは深い関りがあった(と言っても、兼見やまして朝廷が「本能寺の変」の黒幕だった訳では勿論ありません。)ようです。

都名所之内 吉田山神楽岡(長谷川貞信)
出典:立命館大学アーク・コレクションarcUP2558
吉田山の南東近くに天台宗の古刹・真如堂(真正極楽寺@京都市左京区浄土寺真如町)があります。真如堂は「本能寺の変」の斎藤利三の墓所があるのです。[11]で述べたように、斎藤利三は山崎の戦で敗れ、六条河原で処刑されましたが、その首は利三の友人が夜陰に乗じて奪い去ったのです。首を奪ったのは、絵師の海北友松(1533~1615)と真如堂住職・東洋坊長盛(1515~1598)です。彼らが奪い取った利三(の首)を真如堂に葬りました。そして後年、彼等二人の墓所も(友松のは利三と並んで、東陽坊のは利三の裏に)真如堂に建てられました。現在真如堂は、その案内表示を建てていて、そこには「戦国武将 斎藤利三、東陽坊長盛、海北友松 の墓」と書いてあります。東陽坊長盛は、黒茶碗「東陽坊」、海北友松は、建仁寺「大方丈障壁画」や妙心寺「花卉図屏風」が有名で、何れも重要文化財です。
また、真如堂の本堂の南、墓地との間に、春日局が父の菩提を弔って植えたといわれる「たてかわ桜」(縦皮桜。縦に筋が走るエドヒガン系の品種)があります。1959年(昭和34年)の「伊勢湾台風」でたおれたたてかわ桜は、数年後自力で復活しましたが、金ねんその樹勢はどんどん弱って来たので、日本製紙(特殊な)挿し木技術で後継木が育成されています。三井家家祖・三井高利が遺言で墓所を造らせて以来真如堂は三井家の菩提寺になり、その御縁で三井グループの一員である日本製紙がたてかわ桜の護持役を買って出たのです。

©真如堂 鈴聲山真正極楽寺
話は飛びますが、高利の7代前の三井乗定の嫡男(ですが、三井家を継いだのは前に養子に入っていた高久でした。)・定条(さだえ)の孫に近江鯰江城主・三井乗綱がいます。乗綱の次男・虎高は藤堂家の婿養子になり、虎高の次男・高虎を藩祖とする藤堂藩の11代藩主・藤堂高猷の江戸屋敷こそあの「お玉ヶ池種痘所」が二度目の移転後、大学東校→東京医学校になり、「東京医学校」が加賀藩上屋敷(跡)に移転するまでの16年間在った場所でした。そして今、その場所には三井記念病院が建っています。
長崎と京の名医 向井元升の次男・兼時は「蕉門十哲」の一人・向井去来です。去来が1694年(元禄7年)夏に向井家の菩提寺・真如堂で行われた神州・善光寺の阿弥陀如来の出開帳を詠んだ句があります。
涼しさの 野山にみつる 念仏かな (向井去来)
吉田山は、京都大学の「東(隣の)山」でもあります。1200年もの歴史ある古社(で、「八つ橋発祥の地」)・京都熊野神社から東大路通(「東山通」とも云う)を北に200mほどの処に學京都大学病院があります。更にその北・東山近衛交差点を左に折れると、すぐ右にあるのが京都大学医学部(@京都市左京区吉田近衛町)です。
1947年(昭和22年)に誕生した「京都大学医学部」は、1919年(大正8年)発足の「京都帝国大学医学部」をその前身としています。京都帝国大学医学部は、吉田山の西の麓、吉田神社参道の南に建てられ、今では京都大学医学部と附属病院のキャンパスになっていて、(「本部構内」等周辺6か所の「構内」と併せて、京都大学全学のメインキャンパスでもある)「吉田キャンパス」と呼ばれています。吉田キャンパス・病院西構内の再生医科学研究所(現・医生物学研究所)教授だった永田和宏が吉田山を詠った歌があります。
呼び捨てに 呼びいし頃ぞ 友は友
春は吉田の 山ほととぎす (永田和宏)
医科大学開学に当たって「京都帝国大学医科大学建築設計委員」4名が任命されました。その中には、明智光秀末裔の三宅秀と織田信長末裔の坪井次郎(初代坪井信道の孫:1863~1903)の二人共が加わっています。東京大学医学部だけでなく、京都大学医学部も光秀末裔と信長末裔の協働によって始まったことになるのです。坪井次郎は、信道の次女・幾の次男(長男は夭折)で、帝国大学医科大学(源・東大医学部)を卒業後永正学教室で研究した人で、同教室の助教授(現在の准教授)だった時に京都帝国大学医科大学建築設計委員に就任しました。そしてその開学にあたって学長に任命され、1903年に逝去するまで4年の間、学長の任にあたりました。
当時の「京都帝国大学創立計画」には「医科大学は京都または大阪に新設する」とあり、その他に岡山案もあったそうです。実際には「医科大学は大阪、他の分科大学は京都」に内定していたようなのですが、最終的には誘致運動が圧倒的に協力だった京都に決定したのでした。
大坂(源・大阪)は皆様御存知のように緒方洪庵が適塾を開いて福沢諭吉・大村益次郎etc.等の人材を輩出し、江戸に先行すること9年の1849年(嘉永2年)に洪庵が大坂除痘館(=種痘所)を開いた蘭学の先進地です。にも拘わらず、京都帝国大学医科大学の誘致に失敗した大阪に医科大学が誕生したのは、京都に遅れこと16年、1915年(大正4年)の大阪府立医科大学(現・大阪大学医学部)の開学まで待たなければなりませんでした。帝国大学に至っては、更にもう16年後の1931年(昭和6年)の開学です。その大阪帝国大学開学時には、三宅秀の孫・仁田勇(1889~1984)が理学部創立委員(の一人。後に大坂大学理学部長)になっています。
京の「本能寺」から江戸の「お玉ヶ池」(更に、和泉橋、本郷)への旅路は、こうして再び京(の京都帝国大学医科大学)へと帰り着いたことになります(か?)。
そればかりではありません。その流れは、はるか九州・筑前の箱崎まで伸びていました。
京都帝国大学開学の後、東京、京都に続いて「東北と九州にも帝国大学を」との機運が高まり、先ずは「九州帝国大学」の布石(?)として、福岡に京都帝国大学の第二医科大学が開かれることになりました。博多(今では「福岡」の一部?)の箱崎という処は(京都熊野神社と同じ平安時代の創建の筥崎宮の門前町で、福岡よりずっと)古い古い町で、野点の始まりだとされる箱崎茶会(1587年)で使われた「利休釜掛けの松」が今でも九州大学医学部構内に残されています。

京都大学医学部資料館(旧京都帝国大学解剖学講堂)
©京都大学大学院医学研究科
そこに1903年(明治36年)「京都帝国大学福岡医科大学」が誕生しました。京都帝国大学の第二医科大学というばかりではなく、全国的に見ても「第三医科大学」でした。これが現在の九州大学医学部の源流になるのですが、開学時には京都帝国大学の一部だったので、(「東大病院だより」に倣えば)京都帝国大学の「ファウンダー」が即ち九州帝国大学医学部の「ファウンダー」でもあることになります。京都帝国大学福岡医科大学初代学長・大森治豊(1852~1912)は、1879年(明治12年)東大医学部卒業の外科医で、大学同期に佐々木政吉(帝国大学医科大学第一内科初代教授:1855~1939)がいます。佐々木政吉は、[13]の佐々木東洋の養子ですから、三宅秀の義甥にあたります。
その12年後に開学した第4の医科大学「東北帝国大学医科大学」の場合は、「仙台医学専門学校」をその前身としていますので、残念ながら「本能寺から御玉ヶ池へ」の流れが先代まで流れていくことはありませんでした。ただ、仙台医学専門学校の校長と東北帝国大学医科大学初代学長を務めた山形仲芸(なかき:1857~1922)が東京大学医学部の4期生(同期に森鴎外。学部長は三宅秀)だったという御縁はあります。仙台医学専門学校は、皆様ご存知のように、魯迅(1881~1936)が留学生として学んだ学校です。
遙けき昔、「本能寺の変」で兵刃を交えた明智家と織田家でしたが、その270余年の後に(その末裔たちが)江戸・お玉ヶ池で「東京大学医学部開祖の大功労者」(by金子準ニ)として手を握ることになり、更にその40年後には、「京都大学医学部開基の大功労者」として再び手を握る事になりました。京都帝国大学建築設計委員の中に、明智光秀の末裔・三宅秀と、織田信長の末裔・坪井次郎とが共に加わっていたからです。日本の医科大学の嚆矢・帝国大学医科大学(現・東京大学医学部)とそれに次ぐ第二の医科大学・京都帝国大学医科大学(現・京都大学医学部)の開学に、光秀の末裔と信長の末裔が共に深く関わったのでした。「第二」とは言え、皆様ご存知のように京都大学医学部は本庶佑先生と山中伸弥先生という二人のノーベル賞受賞者(但し、山中先生は神戸大学卒業)を輩出しています。
【最上義俊の一門家老楯岡甲斐守光直、忠利君御預之事ニ付而御国江之御書】(綿考輯録・巻二十九)
■元和八年十一月二日
民部者急差下候、最上浪人楯岡甲斐と申仁我等ニ被成御預候間、跡より可 民部=小笠原民部
差下候、甲斐守下着次第、百人扶持相渡可申候、宿ハ何レニても寺を可申
付候、下国之上家ハ可申付候、当分之兵粮塩噌以下見計可申付候、謹言。
直々、甲斐守大阪よりも船中廿日分為賄百人扶持相渡候へと申付候、又甲
斐守人数上下百弐三十人も有之由ニ候、可有其心得候、以上。
十一月二日 内 忠利
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いわゆる最上騒動に対する処置である。13代家親の死後、若い嫡子義俊の相続に反対する老臣があり、騒動となって将軍家の周旋により義俊の相続について条件を付けて申し渡されたが、それでも老臣が叔父の山野辺義忠の擁立を申し立て将軍家の周旋に反対の意を表した結果、御取つぶしとなったものである。
8月に至り最上家は改易、義俊の大叔父に当たる楯岡甲斐守光直は豊前配流と決定したものである。
光直の死後は、息二人は細川家家臣となった。
11代 12代・父義光により殺害
最上義守---+--義光---+--義康
| | 13代 14代
| +--家親---義俊(12歳)
| |
| +--義親
| |
| +--(山野辺)義忠
| 甲斐守
+--光直---+--孫一郎・定直---→(楯岡小文吾家)
|
+--蔵之助--------→(楯岡三郎兵衛家)
しかし、配流の身分ながら120~30人程も引き連れてという話が本当ならば、翌年15年ぶりに42人の一族郎党と共に帰国する米田監物(是季)のことも頷けるというものである。
一 三番組本陳附并先手物見二て合戦中敵合且諸勢手分向等東西二発走致馬之見合不申候二付出立二も相
成終日別手辛労有之面々左之通
三池丹左衛門 藤崎彌右衛門 吉津次一郎 東 太郎平
富藤権之助 井上儀左衛門 志水一学 片山傳四郎
中嶋次兵衛 山代丈之助 中村九右衛門
右之外鳥越阪戦場江者貮番手大筒塩山牛右衛門弟并二五番組八番組七番組茂手分二て追々数人出張炮
発働申候
一 今日拂暁ゟ炮戦相始五ッ比ゟ圖明寺越坂四ッ半比大谷間道三所之戦争二相成大小之炮聲山海二想音誠
以夥敷九ッ比ゟ者賊兵寺より鳥越阪二寄来味方苦戦二相成候處追々應援馳付競懸申し候間賊も四五度
者返合頻二発炮二候得共七ッ比二至賊兵遂二大崩二相成坂之下ゟ新町表江相至引取申候 敵■■致たる
勢二乗し濱手往還追分迄五六町程押詰往還筋二て賊兵相見不申尚押詰候処を見込ミ遂有之長迄見合人
数引揚之節手負死傷之賊を見出し各首揆取小銃玉薬等分取其外兵粮玉薬箱等道路二打捨有之候 為躰
実二敗北之次第相顕申候 左候て峠二相扣居申候内諸手ゟ少々相進往還之左右山中等手負死骸之首を
揆取申候 右之内二者御物頭大里隼之助嫡子同角太郎三番組鬼塚源八手負見出外様足軽など四五挺一
同二炮発致中村左助組子ゟ右手負之首を揆取セ申候 彼是時刻為後貮番手御物頭七番但等馳付たる一
番手之玉薬も乏敷空腹ニも有之旁引替り大谷口江引揚兵粮を遣玉薬入替尚又暮前ゟ鳥越坂山手ニ相詰
入夜ハ番組ニ引替引取申候
(つづく)
















