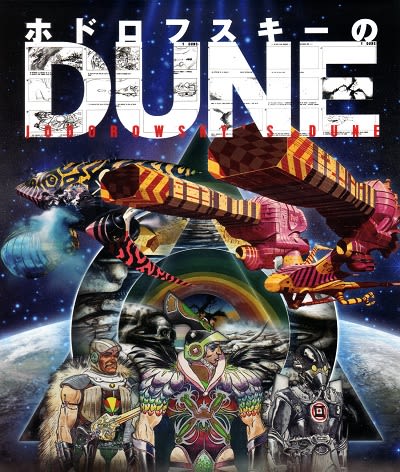MOPDtK『The Coimbra Concert』(clean feed、2010年)。ピーター・エヴァンス聴きたさに入手したが、グループ名は「Mostly Other People Do the Killing (MOPDtK)」。また思い切った名前を付けたものだ。しかも、ロゴマークは、エディ・アダムズの有名な写真「サイゴンでの処刑」を模している。

Peter Evans (tp)
Jon Irabagon (ts, ss)
Moppa Elliot (b)
Kevin Shea (ds)
ジャケットもふざけている。誰が見ても吹き出すと思うが、キース・ジャレット『The Koln Concert』のパロディである。調べてみると、これだけでなく、オーネット・コールマン『This is Our Music』とか、ロイ・ヘインズ『Out of the Afternoon』とか、アート・ブレイキー『A Night in Tunisia』とか、名盤のパクリのオンパレード。
パクリということで言えば、全曲がモッパ・エリオットによることとなっているが、「A Night in Tunisia」、「Let's Cool One」、「A Love Supreme」、「Our Love is Here to Stay」といったジャズスタンダードの断片が埋め込まれている。しかし、これはコミックバンドなどではなく、凝り固まった認知を笑い飛ばすような活動とみるべきだ。かつてジョン・ゾーンが、「Jazz snob, eat shit」と言ったように。
この音楽をどのように言い表すべきか。ピーター・エヴァンスの諸作に通底していて、たとえばイングリッド・ラブロック『Strong Place』でも強く感じられる「Re-focusing」か。楽器編成や文法はジャズのものを踏襲しながら、フリージャズ創世記にあったに違いないような、さらなる自由を見出すための活動が形になっているような感覚か。それぞれのプレイヤーの演奏が全体としての和集合を作っているのではなく、各々の演奏の積集合(共通部分)をキープしながら、あとは四方八方に飛びださせる感覚か。
ピーター・エヴァンスの音楽を聴いていると、スタニスワフ・レム『ソラリス』において、ソラリスの海の上に形成された雲のことを思い出す。人間が飛行機から観察していることに呼応し、雲は赤ん坊の目や鼻や口の形を作りだす。しかし全体としてみれば統合世界としての顔を形成しているわけではなく、観察者は吐き気をもよおすといった描写だった。
もちろん、ここでの演奏は、グロテスクでも、吐き気をもよおすわけでもない。ひたすら愉快である。
●参照
ピーター・エヴァンス『Ghosts』
ピーター・エヴァンス『Live in Lisbon』
『Rocket Science』
ウィーゼル・ウォルター+メアリー・ハルヴァーソン+ピーター・エヴァンス『Mechanical Malfunction』
ウィーゼル・ウォルター+メアリー・ハルヴァーソン+ピーター・エヴァンス『Electric Fruit』