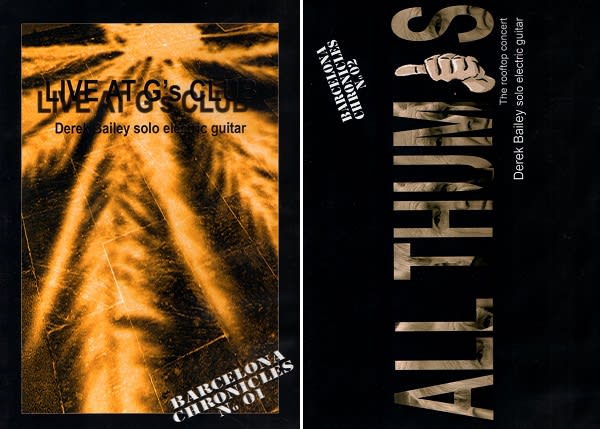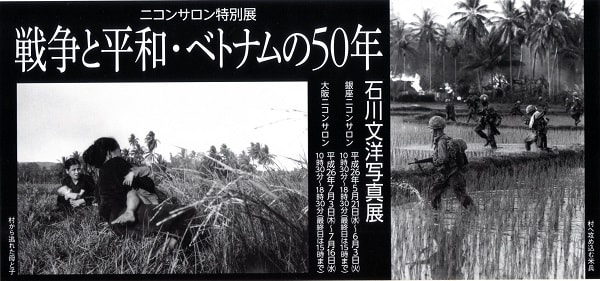ポール・オースター『闇の中の男』(新潮社、原著2008年)を読む。
以前に原著にあまり良い印象を持たなかったのではあるが、名翻訳家・柴田元幸氏の手にかかってどう化けたのか気になり、避けるわけにはいかない。

これは、あり得た<アメリカ>を平行宇宙として描く物語である。
それぞれの伴侶を失った老人、その娘と孫娘。老人は、別世界の<アメリカ>で殺人行為を強いられようとする男の物語を夢想する。その世界では、<9・11>が起きなかったアメリカであり、いくつもの州が独立を宣言、ブッシュの率いる連邦政府に抗っている。男は、この世界を想像する者、すなわち物語を夢想する老人を殺しにいくようにと脅迫される。ひとりを殺さなければ、なお多くの死者が出るというのである。
老人の娘は結婚に失敗して絶望。孫娘は、理知的なはずの夫が、絶望状態を脱するため、周囲の反対にも関わらずイラク戦争に赴き、あろうことか、テロ組織に惨殺され、その映像がテレビとネットで流される。孫娘は引きこもりとなり、映画を観続ける。
オースターは、これが、<アメリカ>が不当に奪われたこと(すなわち、愚かなブッシュ政権)への怒りの表明であることを隠そうとしていない。そして、柴田氏が「あとがき」で書いているように、この小説を日本で読む者は、不当に奪われた現在の日本を重ね合わせることだろう。オースターと同様に、あるいは、違う形で、四分五裂し内戦に陥った<日本>の平行世界を書く者が出てきても、おかしくはない。
はじめに読んだとき、向こう側の<アメリカ>において、読者が感情移入する男があまりにもあっけなく最期を迎えることに、呆然とさせられた。しかし、これも、何だって起こりえて、それでも世界は動き続けることの象徴かもしれない。まさに、小説のなかで引用される言葉「As the weird world rolls on(このけったいな世界が転がっていくなか)」の通りである。
わたしはこの言葉の意味がよくわからず、「ひどい世界は過ぎ去っていく」とでも訳すのだろうと無理に解していた。しかしそれは、勝手な教訓的解釈であり、字義通り素直に訳すべきものであった。悪かろうと良かろうと、世界はすべて混淆して「weird(けったい)」なのであり、別に良い方向に向かうとは限らず、「転がっていく」のである。おそらく、オースターはそこに希望を見いだしている。
心に引っかかった言葉の、拙訳と、柴田氏の名訳との比較。比べるのはもとより愚かなことではあるが、やはり柴田氏の訳は素晴らしい。表現がやわらかく、短文に切り、気持ちが乗っているようである。
"Betty died of a broken heart. Some people laugh when they hear that phrase, but that's because they don't know anything about the world. People die of broken hearts."
●拙訳 「ベティは絶望によって死んだ。こう言うと笑う人もいるが、それは世界のことを何にも知らないからだ。人は絶望で死ぬんだ。」
●柴田訳 「ベティは心が破れて死んだのだ。この言い方を聞くと笑う人もいる。でもそれは、世界について何も知らないからだ。人は本当に、心が破れて死ぬのだ。」
(小津安二郎『東京物語』における原節子の台詞をもとに)
"Yes, Miriam, life is disappointing. But I also want you to be happy."
●拙訳 「そうだよ、ミリアム、人生はつまらないものだよ。だけど、君には幸せになってほしい」
●柴田訳 「そうともミリアム、世の中は嫌なものだ。でも私はお前に、幸せになってほしいとも思うのだ。」
(パラレルワールドからブリックを追ってきた同級生は、昔、憧れの的だった。妻を逃がしたブリックは、彼女との逢瀬を愉しむ)
"Let the man and the woman who met as children take mutual pleasure in their adult bodies. Let them climb into bed together and do what they will. Let them eat. Let them drink. Let them return to the bed and do what they will to every inch and orifice of their grown-up bodies. Life goes on, after all, even under the most painful circumstances, goes on until the end, and then it stops."
●拙訳 「子どもとして出会った男女に、大人の身体をもってお互いに悦ばせよ。ふたりにはベッドに入らせ、やりたいことをさせよ。食べさせよ。飲ませよ。そしてまたベッドに戻り、発育した身体のどんなところに対しても、やりたいようにさせよ。人生は続く。どんなに痛ましい状況でも、最後まで人生は続き、そして終わる。」
●柴田訳 「子供のころ出会った男女よ、大人になったたがいの体から快楽を貪るがいい。二人一緒にベッドに入って好きにするがいい。食べるがいい。飲むがいい。ふたたびベッドに入って、たがいの大人の体の隅々とすべての開口部とにしたい放題をするがいい。何といっても、どんなに辛い状況であっても人生は続いていくのだ。終わりまで続いていき、やがて停止する。」
(ブリルが孫娘に対して述べる回想。若いころ、モラルをどのように扱っていたか)
"That was the fifties. Sex everywhere, but people closed their eyes and made believe it wasn't happening. In America anyway."
●拙訳 「それが50年代。セックスはいたるところにあって、しかし、人々は目を閉じてまるでそれがないかのように信じていた。アメリカのどこでもだ。」
●柴田訳 「それが50年代だよ。いたるところセックスはあるのに、人々は目を閉じて、何も起きてないふりをしたんだ。少なくともアメリカではね。」
(カティアの若い恋人がイラクに行くと聞いて、ブリルは思いとどまるよう説得する)
"... but the last time you were here, I remember you said that Bush should be thrown in jail --- along with Cheney, Rumsfeld, and the whole gang of fascist crooks who were running the country."
●拙訳 「・・・でも君はこのまえ、ブッシュを監獄に入れるべきだと言っていたじゃないか。チェイニーも、ラムズフェルドも、この国を動かしているファシストの犯罪者たち皆も。」
●柴田訳 「・・・、このあいだここに来たときは、ブッシュは刑務所に入れられるべきだと言ってたよね―――チェイニー、ラムズフェルド、国を動かしているファシストの悪党どもみんなと一緒に。」
(ブリルやカティアは、カティアの恋人がテロリストに殺される映像を視てしまう。)
"Sleep is such a rare commodity in this house, ..."
●拙訳 「睡眠はこの家では稀少な商品となり、・・・」
●柴田訳 「眠りはこの家ではきわめて稀少な品なのだ。」
"But there's one line ... one great line. I think it's as good as anything I've ever read.
Which one? She asks, turning to look at me.
As the weird world rolls on.
Miriam breaks into another big smile. I knew it, she says."
●拙訳 「でもあの一言が・・・偉大な一言がある。いままで読んだもののなかで一番良いものだと思う。
どの一言? 彼女は訊いて、わたしを見た。
”ひどい世界は過ぎ去っていく”
ミリアムはにっこり笑って言った。知ってるよ。」
●柴田訳 「でも一行は・・・・・・一行は素晴らしい。いままで読んだ中で最高の部類に属す一行だと思う。
どの行?と、私の方に向き直りながらミリアムは訊く。
このけったいな世界が転がっていくなか。
ミリアムはまたニッと満面の笑みを浮かべる。わかってたわ、と彼女は言う。」
●ポール・オースター
ポール・オースター+J・M・クッツェー『Here and Now: Letters (2008-2011)』(2013年)
ポール・オースター『Sunset Park』(2010年)
ポール・オースター『Invisible』(2009年)
ポール・オースター『闇の中の男』(2008年)
ポール・オースター『写字室の旅』(2007年)
ポール・オースター『ブルックリン・フォリーズ』(2005年)
ポール・オースター『オラクル・ナイト』(2003年)
ポール・オースター『幻影の書』(2002年)
ポール・オースター『ティンブクトゥ』(1999年)
ポール・オースター『リヴァイアサン』(1992年)
ポール・オースター『最後の物たちの国で』(1987年)
ポール・オースター『ガラスの街』新訳(1985年)
『増補改訂版・現代作家ガイド ポール・オースター』
ジェフ・ガードナー『the music of chance / Jeff Gardner plays Paul Auster』