■『マンダラの謎を解く 三次元からのアプローチ』武澤秀一/講談社現代新書読了。マンダラは単に図絵にとどまらず立体的な石窟や飛鳥寺の伽藍配置などにも表現されているとする著者の指摘はなかなか興味深かった。
飛鳥寺は塔を中心としてそのまわりを三つの金堂が取り囲んでいたという。その復元図が載っているが、その伽藍配置をみると確かに立体マンダラだとする著者の見解にも素直に頷くことができる。
その伽藍配置が日本では次第に変容していく。
確かに例えば法隆寺では塔と金堂が横に並び、伽藍の中心性が失われている。薬師寺では東塔と再建された西塔が伽藍の前に配置され、金堂が回廊のほぼ中心に配置されている。塔が本来のストゥーパつまり卒塔婆という意味から変わっている。
塔が伽藍の中心から次第に外れるとともに塔に代わって伽藍の中心に配置された金堂も、横長になっていく・・・。その最たるものが三十三間堂だ(金堂は次第に本堂と呼ばれるようになる)。
著者はこの変化を**立体的幾何学的な、いわば硬直した中心性ではなく、周囲に溶けこむやわらかな叙景性を求めての動きとみることができる。**と指摘している。
そのように変容していったのは一体何故なのか。そのことについて著者は「島国ゆえに」という小見出しからも分かるように、日本の地形の特性、大陸とは異なり細かな地形の変化で、つねに目印となる山並みが目に入ってくる島国であることを挙げている。
塔を中央に据えた中心性の強い伽藍配置不要の地理的特性。これは、和辻哲郎の『風土』にも通ずる指摘だ。
なかなか興味深い論考だった。さて、次はこの本。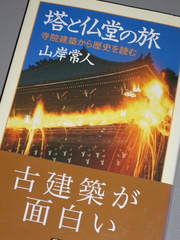
『塔と仏堂の旅 寺院建築から歴史を読む』山岸常人/朝日選書









