■ 昨年の秋に亡くなられたコラムニストの天野祐吉さんの『成長から成熟へ ―さよなら経済大国』集英社新書を読んで、そう言えば同じようなことを以前このブログに書いたな、と思って探してみた。2011年4月24日に書いていた。友だちのKさんと同じようなテーマで語り合っていた。少し稿を改めて再掲する。
「女優の田中好子さんが亡くなりましたね」
「そうだね。スーちゃん、20年ちかく闘病しながら女優してたんだね。知らなかったな。キャンディーズの活動期間ってちょうどボクの学生時代と重なるんだけど、あの頃はメンバー3人の誰が好みか、よく友だちと飲みながら話したな」
「私はキャンディーズの頃はまだ生まれてないので、よく知りませんが、すごく人気があったんですね」
「なぜかテレビの向こうのアイドルという感じではなくて、身近な存在という感じだったな」
「U1さんは誰が好きだったんですか?」
「ボクはミキちゃん、少数派だったけど」
「なんとなくわかります、私。ふふふ」
***
「福島の原発の事故ってどうなるんでしょうね、とても心配です。これから、何年?何十年?も住めなくなってしまうのかな・・・」
「チェルノブイリはいまだにダメでしょ」
「今の暮らしを続けていいのかなって思いますね」
「そうだね、人が完全には制御することができない発電システムを前提とした暮らしを続けていいものかどうか・・・」
「今現在の電力の消費水準、これを原子力発電に替わる発電、風力とか太陽光発電でまかなうという考え方も、どうなのかな。原発の発電量って消費量の3割くらいでしたっけ。そのくらい抑えることができるような、そういう暮らしをしなくちゃいけないんじゃないかなって思いますけど、無理かな・・・」
「ボクは電力消費ゼロの江戸時代に学ばなくてはならないのではないかってこの頃思うね」
「江戸時代の暮らしに今に活かせるヒントがある・・・」
「そう。江戸時代は日本の伝統的な文化が成熟した時代だよね。それが、明治になって西欧の文化を取り込む際、千年以上も連綿と継承されてきた伝統文化をほとんど断ち切ってしまったことがまずかったのではないかと思う。建築なんてまさにそう」
「そうなんですね・・・。江戸までは夜になれば随分暗いところで過ごしたわけですね。でもその暗さが例えば蒔絵などの工芸を育んだともいえるんですよね」
「そうだね、蒔絵って暗い空間で観るからいいんだね。というか、暗い空間で鑑賞する芸術だよね。他にもあるね、きっと。例えば月を愛でるとかさ」
「そういえば谷崎が「陰翳礼讃」で日本の空間の暗さを評価しましたね」
「そうだね。日本には空間の暗さが育んだ文化があったんだよね。でもそういう暗さを日本人はいつのまにかなくしてしまった」
「そうか・・・」
「まあ、田舎では昭和30年代半ばころまでかな、広い部屋でも裸電球ひとつだったけどね。家電製品もあまりなくて、風呂も薪で沸かして、ご飯も薪で炊いて、エコな暮らしをしてたんだよね」
「でもそんな時代にはもう戻れません」
「でも、今の電気じゃぶじゃぶな暮らしでいいとは思わなくなったな。「清貧の思想」に学べってことなのかな」
「そういえば、ありましたね。貧しくても豊かな心」
「どうもね、明治になって唱えられた「和魂洋才」っていうのがダメというか、無理だった、そんな気がするな。「和魂和才」だよね、やはり。この国の感性というか、精神的な風土に相応しい技術、文化があったと思うけど、それを明治以降、西洋の技術に置き換えてきたことに無理があった・・・」
「次第に技術や文化までもが均一化されてきたわけですね、グローバリズムとかいって」
「この20年間で、一般家庭の消費電力は2割くらいアップしたらしいけど、ずっと和魂和才でやってきていたら、原発まで必要になるような社会にはならなかったかもね。日本は工業立国で進むというコンセプトもどうだったのかな。日本人本来の心性にあった質素というか慎ましやかな生活から変わったわけだよね」
「利便性を追い求め過ぎたのかもしれませんね、アメリカ型の暮らし。それで、なんだろう、細やかな感性までなくしてしまったような・・・」
「そうだね」
「フランスは確か7割以上を原発に頼っていますよね。でも同じヨーロッパでもドイツやスウェーデンではまた事情が違いますね」
「共に確か一度決めた脱原発を見直す方向を打ち出したと思うけど、福島の事故でこれからどうなるかね」
「日本もこれからどうするのか、よく分からない・・・」
「ここは今回の津波の被害や原発事故で国民の意識がどう変わるか、だね。原発なんてもうこりごりなのか、やはり必要だって考えるか」
「人口もピークを過ぎてどんどん減っていきますしね」
「そう、今後50年で6千万人まで減少するって言われてる。そろそろこの国に相応しい成熟型の社会を、イメージしないと」
「そうですね。もう一度伝統文化を取り戻すような、社会でしょうか。で、個人のレベルでは豊かな自然にそっと・・・、同調するような暮らしかな。豊かな人生ってどういうものなのか、ですね・・・」
***
「これから桜を観に行こう。桜を観て、ああ、きれいだなって思う感性が大事なんだよ、きっと。東北のお酒でも飲みながら、続きをどう?」
「ええ いいですよ」
太字にした私のコメント部分、天野さんの主張にぴたり重なる。社会の状況からしてもう右肩上がりの経済成長なんてありえない。そんなことは誰でも気が付いているはずなのに・・・。

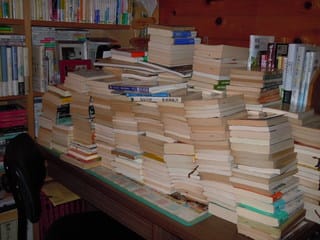

















 まあ、あくまでも個人的な感想ですが・・・。
まあ、あくまでも個人的な感想ですが・・・。












