

桜の下に祀られている石神・石仏 長野県朝日村 2023.04.05
■ 手前の道祖神、奥の左から庚申塔、青面金剛像 蠶神の順に載せます。
祝言跪座像 明治22年4月13日建之

大正9年12月吉日建之 この年(1920年)の干支は庚申。

線刻された青面金剛像 邪鬼の上に乗っています。脚元に二猿二鶏。手に持っているのは向かって左側に上から三叉戟(さんさげき)、剣、矢。右側上から輪?、羂索、弓。蛇を首にかけています。
昭和55年12月吉日建之 この年(1980年)の干支は庚申。朝日村にはこの年に祀られた庚申塔が何基かあります。

蠶神 養蚕が盛んだった地域に祀られていることが多いでしょう。明治12年2月8日建之














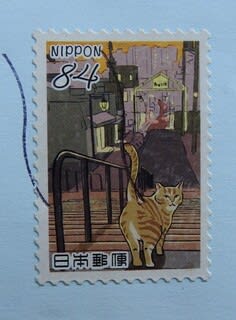








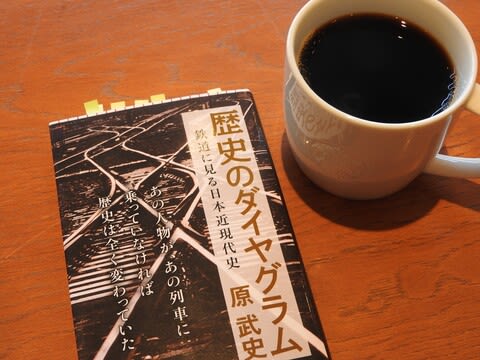 360
360