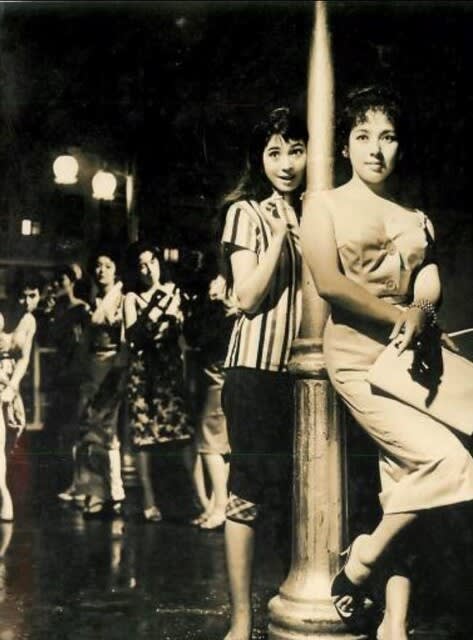映画「さかなのこ」を映画館で観てきました。

映画「さかなのこ」はのん主演で人気者魚博士のさかなクンの人生を振り返っていく作品である。予告編から気になっていたが、ついつい後回しになってしまった。子ども連れが多く、公開1ヶ月経ったにもかかわらず思いのほか満席に近いので驚く。
のんの天真爛漫なキャラクターが何よりすばらしい。
娯楽として十分楽しめる作品となっている。前半戦で、魚好きの8歳のミー坊が自由奔放に動きまわった後、高校生になったミー坊が不良グループと混じり合いながら成長していく。でも、魚と関係ある就職先に勤めたあとは転々と職になじめない話が続く。

前半戦の軽快さに比べると、後半戦の逸話は多いけどチグハグでそれぞれのシーンが尻切れトンボな印象を受ける。幼なじみとの同居生活や不自然な会食シーンなどの一部には不要なシーンもあるのでは?と感じる。もう少し縮めることはできるかもしれない。
⒈のん
高校に学ランを着て通う。いかにも田舎のツッパリって感じの不良グループが出てきて、天真爛漫で空気がまったく読めないミー坊は何が起ころうと気にしない。釣った魚をしめるシーンは練習したのであろう。ほかの不良グループとのケンカ話はまさにギャグ。コメディ要素が強くて楽しい。学ランが似合うのんがすばらしい。

のんは「あまちゃん」で全国区の人気者になった後、芸能プロダクションから個人事務所を作って独立しようとして相当な反発を受けたようだ。自分で動いた訳ではないだろう。この辺りの事情はむずかしいねえ。

⒉さかなくんの登場と幼少時のミー坊
8歳のミー坊を演じた子役の西村瑞季がいい。最近観た「こちらあみ子」のあみ子にかなり共通する周囲が見えないで自分勝手な女の子だけど、無邪気でかわいいのは2作とも共通する。学校からも呆れられるが、ミー坊をかばうのが井川遙演じるお母さんである。かなりいい感じだ。ただ、海辺の田舎町が舞台だけど、井川遙が帽子をかぶって出てくるとセレブの香りがする。

帰り道でハコフグの帽子をかぶった変なおじさんに遭遇する。いつも逃げていたが、好奇心でついて行く。これがさかなクン自ら演じるギョギョおじさんだ。家に行ったら、たくさんのお魚が泳いでいる水槽やさかなグッズがある。お母さんから日が暮れるまでに帰ってきてねと言われたのに気がつくと夜の9時でお父さんが警察を連れてくるなんてオチだ。原作にないらしいが、さかなクンは出演してよかった。
子どものころのミー坊が学校の上下校にいつも「魚介の図鑑」を持参している。これを観て、思わずジーンときた。自分も小学校低学年の頃、小学館の「魚介の図鑑」を読み込んだ時期があった。いちばん好きなのはサメのページだ。映画のさかなクンの水槽にもネコサメがいた。当時江の島に別宅があり、江の島水族館によく行った。そこでサメを見たあと図鑑と睨めっこしたものだ。当然学校の勉強は何もしていないので成績は良くない。それでも時刻表や歴史の図鑑ともども毎日見るのが楽しかったいい時代だ。

⒊子ども向き?
沖田修一監督作品では「モヒカン故郷に帰る」が好きだ。この映画も海辺の町を舞台にしているので共通する。子どもや高校生の使い方が上手く、目線を落としてギャグの要素も加えるところがいい。

最初家族4人で住んでいた家から、高校生の時には母娘一緒に住む賃貸住宅と思しき場所に移る。その時点で、アレ?別居したのかな?と思うけど、特に言及しない。最後に向けて、家族に関するセリフが出てくるが、井川遙がはぐらかす。これって子供を意識して離婚などの類のセリフをあえて言わせないのかな?
後半戦に向けては、説明が足りない印象を持つ。もっと子どもの視線も気にするべきでは?意識的に大人の理解度に合わせているとしたら、カッコつけすぎかもしれない。

映画「さかなのこ」はのん主演で人気者魚博士のさかなクンの人生を振り返っていく作品である。予告編から気になっていたが、ついつい後回しになってしまった。子ども連れが多く、公開1ヶ月経ったにもかかわらず思いのほか満席に近いので驚く。
のんの天真爛漫なキャラクターが何よりすばらしい。
娯楽として十分楽しめる作品となっている。前半戦で、魚好きの8歳のミー坊が自由奔放に動きまわった後、高校生になったミー坊が不良グループと混じり合いながら成長していく。でも、魚と関係ある就職先に勤めたあとは転々と職になじめない話が続く。

前半戦の軽快さに比べると、後半戦の逸話は多いけどチグハグでそれぞれのシーンが尻切れトンボな印象を受ける。幼なじみとの同居生活や不自然な会食シーンなどの一部には不要なシーンもあるのでは?と感じる。もう少し縮めることはできるかもしれない。
⒈のん
高校に学ランを着て通う。いかにも田舎のツッパリって感じの不良グループが出てきて、天真爛漫で空気がまったく読めないミー坊は何が起ころうと気にしない。釣った魚をしめるシーンは練習したのであろう。ほかの不良グループとのケンカ話はまさにギャグ。コメディ要素が強くて楽しい。学ランが似合うのんがすばらしい。

のんは「あまちゃん」で全国区の人気者になった後、芸能プロダクションから個人事務所を作って独立しようとして相当な反発を受けたようだ。自分で動いた訳ではないだろう。この辺りの事情はむずかしいねえ。

⒉さかなくんの登場と幼少時のミー坊
8歳のミー坊を演じた子役の西村瑞季がいい。最近観た「こちらあみ子」のあみ子にかなり共通する周囲が見えないで自分勝手な女の子だけど、無邪気でかわいいのは2作とも共通する。学校からも呆れられるが、ミー坊をかばうのが井川遙演じるお母さんである。かなりいい感じだ。ただ、海辺の田舎町が舞台だけど、井川遙が帽子をかぶって出てくるとセレブの香りがする。

帰り道でハコフグの帽子をかぶった変なおじさんに遭遇する。いつも逃げていたが、好奇心でついて行く。これがさかなクン自ら演じるギョギョおじさんだ。家に行ったら、たくさんのお魚が泳いでいる水槽やさかなグッズがある。お母さんから日が暮れるまでに帰ってきてねと言われたのに気がつくと夜の9時でお父さんが警察を連れてくるなんてオチだ。原作にないらしいが、さかなクンは出演してよかった。
子どものころのミー坊が学校の上下校にいつも「魚介の図鑑」を持参している。これを観て、思わずジーンときた。自分も小学校低学年の頃、小学館の「魚介の図鑑」を読み込んだ時期があった。いちばん好きなのはサメのページだ。映画のさかなクンの水槽にもネコサメがいた。当時江の島に別宅があり、江の島水族館によく行った。そこでサメを見たあと図鑑と睨めっこしたものだ。当然学校の勉強は何もしていないので成績は良くない。それでも時刻表や歴史の図鑑ともども毎日見るのが楽しかったいい時代だ。

⒊子ども向き?
沖田修一監督作品では「モヒカン故郷に帰る」が好きだ。この映画も海辺の町を舞台にしているので共通する。子どもや高校生の使い方が上手く、目線を落としてギャグの要素も加えるところがいい。

最初家族4人で住んでいた家から、高校生の時には母娘一緒に住む賃貸住宅と思しき場所に移る。その時点で、アレ?別居したのかな?と思うけど、特に言及しない。最後に向けて、家族に関するセリフが出てくるが、井川遙がはぐらかす。これって子供を意識して離婚などの類のセリフをあえて言わせないのかな?
後半戦に向けては、説明が足りない印象を持つ。もっと子どもの視線も気にするべきでは?意識的に大人の理解度に合わせているとしたら、カッコつけすぎかもしれない。