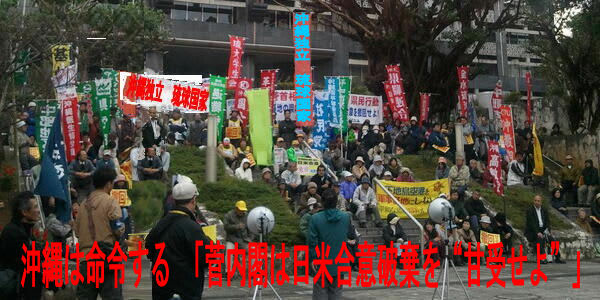
昨7月8日(2011年)の衆院本会議で佐藤茂樹公明党議員が菅内閣の原発事故に関わる責任問題を追及、それに対して菅仮免は「今回の原発事故に関ついては、現在政権を担っている私自身、あるいは我が党に大きな責任があることは言うまでもありませけれども、(声を一段大きくして)長年与党であった公明党のみなさんにも、そうした責任は少なくともその一端はあるわけでありまして」と答弁しているが、原子力発電所を監視・監督・指導する立場の原子力安全・保安院を原子力政策を推進する経産省に所属させた体制であることを改革せずに放置させていた、あるいは東電に省庁との癒着を生じかねない経産省からの天下りを許していたといった責任はあるかもしれないが、3月11日原発事故発生以降の危機管理対応の指揮・命令の当事者はすべて菅仮免と菅政権であって、如何に東電を管理下に置いて事故収束に向かわせるか、放射能が洩れ、住民避難を必要とした際の的確な避難指示と避難後の全体的な秩序の構築、そしてその時々の適正な情報公開、あるいは情報開示はすべて今の政権の責任事項であろう。
それまでも含めて公明党にも責任があるとしているなら、お門違いの責任転嫁としか言えない。
どんな遣り取りがあったか、責任発言に関する箇所のみを「衆議院インターネット審議中継」から取り出してみた。 佐藤茂樹公明党議員「最後に国家・国民のために総理に申し上げたいと思います。私は総理の居座りとも取れる一連の言動に対しても、遣り切れない思いを持っていますが、それ以上に一国の総理が、被災者の方々や、原発被害者に目を向けない、寄り添う心を持ち合わせていないことに対し、憤りすら覚えます。
その証拠が復興担当大臣でありながら、被災者の方々の感情を逆撫でするような言動を弄し、僅か9日で辞任するような人物を任命したことに端的に現れております。
1946年にルース・ベネディクトは名著『菊と刀』でアメリカ人類学史上最初の日本文化論を著し、日本文化を恥の文化と位置づけました。それから65年経って、失政に次ぐ失政を重ねながら、地位に異常な執着を見せ、自らの延命のためだけに首相の座に居座り続ける恥知らずな日本の首相を見たときに、ベネディクトはどのように感じるでしょうか。
歴史の審判で恥知らずな首相の烙印を押される前に、1分でも1秒でも早く潔く身を処すべきであると、最後に申し上げ、私の代表質問といたします」
菅仮免「終わりのところで色々とご指摘を頂きました。何か私が被災者の方々や原発被害者に目を向けていないとか、寄り添う心を持ち合わせていないというふうに一方的に決めつけられておりますけれども、私は、あ、そうしたみなさんの、おー、ことを、あわされたことは(忘れたことは)一度もありません。
また、あ、失政に次ぐ失政というようなご指摘を頂きましたけれども、例えば今回の原発事故については、現在政権を担っている私自身、あるいは我が党に大きな責任があることは言うまでもありませけれども、(声を一段大きくして)長年与党であった公明党のみなさんにも、そうした責任は少なくともその一端はあるわけでありまして、仮にすべての失政を押し付けて、えー、その責任を免れようとすることこそ、私は恥の文化として、反するような行動だと、いうことを申し上げ、私の答弁とさせていただきます」―― |
菅仮免が言っていることはお互いに責任はあるのだから、その責任を一方的に押しつけることこそ恥知らずだということだが、既に触れたように原発事故発生以来の危機管理対応の当事者は菅内閣であり、その責任範囲事項なのだから、失政の責任を野党に押し付けるようなもので、菅仮免こそ恥知らずに当る。
3月12日午前1時30分前後に1号機のベントを指示しながら、東電がベント準備に着手したのは3月12日午前9時04分。ベント開始は3月12日午前10時17分。
ベント指示からベント準備着手とベント開始までのスケジュールの間に菅仮免の福島第一原発視察がすっぽりと入っている。一刻一秒を争って急ぐべきベント開始の緊急事態に反して、そこに視察という別件が入り込んだのである。
3月12日午前6時14分に官邸からヘリで出発。福島第一原発到着は3月12日午前7時11分。3月12日午前8時04分に第一原発を離れる。
その1時間後にベント準備に着手している。
7月4日月曜日の朝日テレビ「TVタックル」では、3月12日、ベント指示の午前1時30分から1時間半後に当る午前3時にベントを行えば、風は陸から海側に吹いていたから、住民は放射能に被爆せずに済んだと批判している。
ベント開始前後は海側から内陸に向かって風が吹いていたという。
ベントの遅れがその後の水素爆発等を含めて事故を拡大させたことは疑いもない事実で、このようにベントを3月12日午前6時50分という早い時間に行うように指示していながら、指示通りに東電を動かすことができなかった責任、あるいは疑惑が持ち上がっているように菅仮免の視察時間を避けたために結果として風向きを無視することになったということが事実としたら、その責任、風向きを考えずに同心円で避難させた責任、真水注水から海水注水切り替え時の混乱の責任(班目原子力安全委員会委員長は国会で「海水だろうと何だろうと、水を入れなければ炉心の溶融はどんどん進んでしまうという認識です。従って、それがすぐできるんだったら、もう何も考えずにしてください、というふうにずっと助言を続けてございます」と証言している。)、さらに各種情報開示の遅れ、情報の混乱の責任等々、すべて野党に関係しない菅仮免を筆頭とした菅内閣に直接関係した責任事項である。
また、海江田経産省が原発再開の「安全宣言」を出し、佐賀県の玄海原発再稼動を立地自治体に求めているさ中に菅仮免が「ストレステスト」を原発稼動の安全確認の新基準として唐突に持ち出して立地自治体と原発会社に混乱を与えた責任も加わる。
《首相 原発再稼働の混乱を陳謝》(NHK NEWS WEB/2011年7月8日 12時5分)
菅仮免「私の指示の遅れと不十分さがあったことに責任を感じている。おわびしたい」
「指示の遅れと不十分さ」は何も今回に限ったことではない。昨2010年7月参院選前の消費税増税話も内閣と民主党に前以て議論を指示もせず、十分な準備の上に持ち出した消費税増税でもなく、10%の税率というわけではなかった。
首相として果たすべきだったにも関わらず果たさなかったこの責任不履行が招いた参院選大敗とねじれ国会でありながら、何ら学習せずに同じ轍を踏んで混乱を招いた性懲りもないストレステストの「指示の遅れと不十分さ」であって、「おわびしたい」の言葉だけは済まない、野党には関係ない、自信の資質としてある統治能力の欠如と言わざるを得ない。
与えられた地位に応じて果たすべき義務を果たすことができなかった責任不履行とはあくまでも役目上の失態そのものに当り、責任を取るとは失態に対して取るべき償いである。
松本前復興担当相が自らの不穏当な発言が祟ってたった9日間の在任で辞任した人事の失態については新しく就任した復興担当相が優れた仕事をすれば一時的停滞や混乱を超えて修復可能となり、「当然任命責任は私にあり、責任を感じている」と言葉で済ませて出処進退にまで発展させずに任命責任を逃れることはできるが、ベント指示を短時間に機能させることができずに原発事故を拡大させた失態は避難住民だけではなく、多くの国民のみならず農業従事者や漁業従事者、その他に重大な放射能被害を与えている以上、言葉のみで済ますことができる失態ではなく、自身の出処進退で償うべき責任であろう。
さらに遡って言うなら、菅仮免が2010年6月8日に首相に就任して1ヵ月後の7月参院選の自らが招いた大敗北の失態、そしてその後の小沢氏と小沢グループ排除の加速による党内統一破壊の失態、そして何よりもリーダーシップ欠如という自身が備えていた失態は党内混乱のみならず参院選敗北以降の国政補選や地方選挙の敗北の失態のそもそもの原因となった、それゆえに修復不可能であることを証明し、ねじれ国会という形で今なお修復不可能のまま推移している大失態なのだから、出処進退でその責任を果たすべきを、「参院選敗北は私に責任がある。皆さんに迷惑をかけたことをお詫びする」程度の言葉で済ませて首相の座に居座っている。
自らがつくり出した失態に対して言葉済ますことができる責任なのか、言葉では済ますことはできず、出処進退で示すべき失態に対する責任なのか、その区別もつかない責任意識の持主となっている。
出処進退で償うべき責任をも言葉で済ませている以上、野党議員に「失政に次ぐ失政を重ねながら、地位に異常な執着を見せ、自らの延命のためだけに首相の座に居座り続ける恥知らずな日本の首相」だと言われても仕方のない失態無視、責任無視の状況中に菅仮免は自を置いて平然としている。「恥知らず」と非難を受けるのは当然の措置と言える。
|