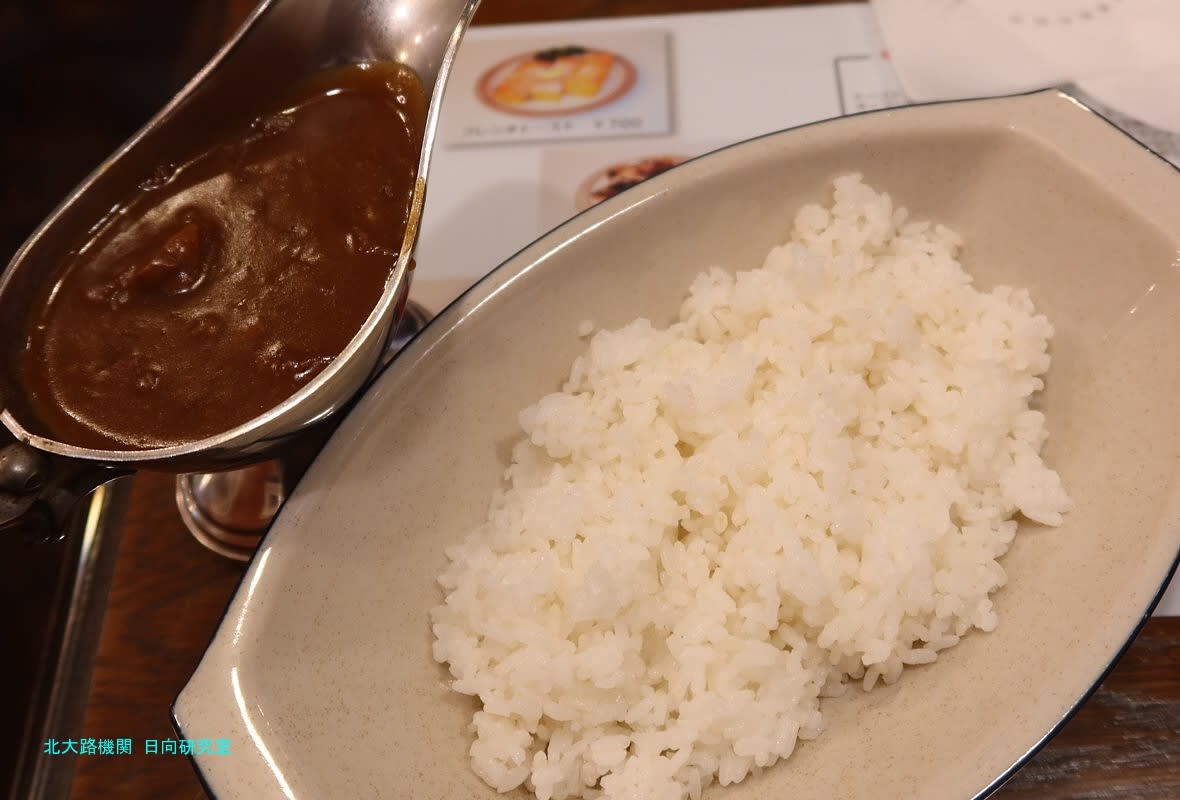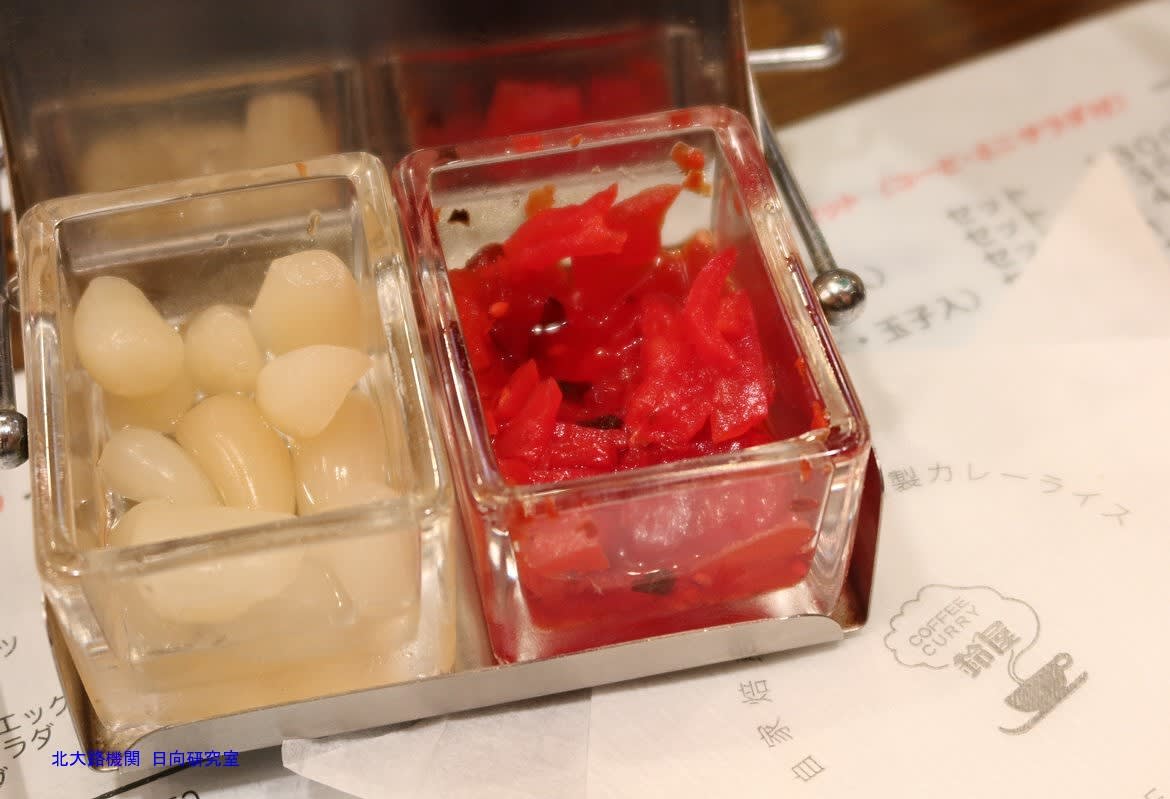■本日は憲法記念日
旗日であり祝日の一つではあるのですけれども本日は。

5月3日、本日は憲法記念日の祝日です、日本国憲法施行の日、大日本帝国憲法が改正された記念日です。日本国憲法制定は太平洋戦争敗戦後、そして新生日本の建国を祈念して制定された、非常に先進的な憲法であり、たとえば男女同権が明示されている憲法は世界には未だ日本国憲法のみですし、平和的生存権の明記という点でも世界に先駆けたものが。

憲法とはその国の制度を示した、構造、という単語と共通するものでありいわば日本のあり方そのものと倫理観や国家体制のあり方というものをしめした法体系です。ただ、実定法というような機能を有するものではなく、また併せて、刑法や民法などは明治憲法施政下に制定されたものであり、憲法の精神との、その齟齬なども幾度も問題視される。

明治憲法と現行憲法の民法や刑法をめぐる齟齬というものは、昨今であれば同性婚の問題、少し前であれば象徴的なものとして義務教育でも教えられるのは尊属殺重罰規定、厳正に解釈すると憲法には冗長性のはばがあります、そして冗長性の幅を実定法のけんけつに当てはめたものが憲法解釈であり、その冗長性の幅も時折議論となる事は確かでしょう。

58年、憲法記念日その都度にやはりNHKなどの政治討論番組などで論点となりますのは憲法改正という視点です。そして2024年は1947年から77年を経た年となるのですが、1947年というのが、明治憲法制定の1889年から58年を経ての憲法改正が日本国憲法なのですから、58年と77年、明治憲法よりも日本国憲法は長生きしているのですね、ゆえに。

解釈という憲法の冗長性を考えるならば、それは司法と立法府の工夫とともになにより良心が試されるとも思うのですがしかし、その冗長性を無視絵現に認めてしまいますと文字通り憲法の立ち位置というものが曖昧になり、ともすれば空文化という問題が生じてしまうのではないか、憲法の意義の喪失、という懸念が生じることはご承知の通りです。

九条、そして憲法問題を考える場合において避けて通れないのは、憲法九条の問題です。同性婚の問題や尊属殺人の問題に環境権やプライバシー権利、もちろん重大な問題ではあるのですが、個人の世界に関わる問題ではある一方で、安全保障に直結する九条の問題は世界そのものに関わる問題ではあるのですから、これは本題となりますが、重要な視点で。

構造、国の方向性を示すものではあるのですが九条の問題は、しかし安全保障環境と軍事技術の基盤が根本から変容している中にあって77年の時間というものを考えるにはあまりに長すぎるのではないかという視点です。なにしろ憲法制定の1947年はアメリカが唯一の核保有国、ソ連さえも核実験の前であり、核兵器を保有していなかった時代なのですから。

日本国憲法と日米安全保障条約は一体のものである、こう理解されるのはもともと日本が安全保障を依存する構想であったのは進駐軍による安全の確保であり、これは後に1956年に日本が国連加盟を果たしたのちにも国連警察軍のような超国家的な集団安全保障の枠組みも実現することはなく、日本の安保依存の基盤が形成されていました。

憲法の問題、毎年のように考えなければならないことは、現実の議論と思いこみの議論、後者についてはフェイクニュースなのか無知なのかの分水嶺で議論が進むためにかみ合わない状況画議論を進められず、しかし危機というものは制御しなければ進んでゆくために制御せず放置することはかえって事態を危機的な方面へ導いているという認識も必要だ。

九条を念頭に議論しますと、即座に徴兵制の話題をもちだして子供が戦場で死ぬという、論理の飛躍がありすぎるような展開が、これはWeb上などで散見されます、そして何度も同じ方が同じ投稿をしている場合もみられ、これはいわゆる認知戦なのか無知なのかというところが傍目にはみえなくなってしまうのですけれども。

認知戦や接近拒否領域阻止という概念、憲法の安全保障を巡る問題で難しいのは日本国憲法施行当時には核兵器さえアメリカ一国が独占している状態であり、確実なパックスアメリカーナ、自由と公正という意味で、成り立っていた瞬間があるのですが、日本国憲法施行から僅か2年後にソ連が核実験に成功し、ここで平和憲法の土台は崩れていたのですね。

1950年の警察予備隊創設、1951年の日米安全保障条約締結、1956年の集団安全保障機構である国際連合加盟、本来ならばここで解決しておくべきであった安全保障との向き合い方ではあるのかもしれませんが2020年代、ロシアウクライナ戦争と台湾海峡、そして朝鮮戦争という日本に影響が及ぶ緊張を背景に、今一度向き合い方を考えるべきなのでしょう。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
旗日であり祝日の一つではあるのですけれども本日は。

5月3日、本日は憲法記念日の祝日です、日本国憲法施行の日、大日本帝国憲法が改正された記念日です。日本国憲法制定は太平洋戦争敗戦後、そして新生日本の建国を祈念して制定された、非常に先進的な憲法であり、たとえば男女同権が明示されている憲法は世界には未だ日本国憲法のみですし、平和的生存権の明記という点でも世界に先駆けたものが。

憲法とはその国の制度を示した、構造、という単語と共通するものでありいわば日本のあり方そのものと倫理観や国家体制のあり方というものをしめした法体系です。ただ、実定法というような機能を有するものではなく、また併せて、刑法や民法などは明治憲法施政下に制定されたものであり、憲法の精神との、その齟齬なども幾度も問題視される。

明治憲法と現行憲法の民法や刑法をめぐる齟齬というものは、昨今であれば同性婚の問題、少し前であれば象徴的なものとして義務教育でも教えられるのは尊属殺重罰規定、厳正に解釈すると憲法には冗長性のはばがあります、そして冗長性の幅を実定法のけんけつに当てはめたものが憲法解釈であり、その冗長性の幅も時折議論となる事は確かでしょう。

58年、憲法記念日その都度にやはりNHKなどの政治討論番組などで論点となりますのは憲法改正という視点です。そして2024年は1947年から77年を経た年となるのですが、1947年というのが、明治憲法制定の1889年から58年を経ての憲法改正が日本国憲法なのですから、58年と77年、明治憲法よりも日本国憲法は長生きしているのですね、ゆえに。

解釈という憲法の冗長性を考えるならば、それは司法と立法府の工夫とともになにより良心が試されるとも思うのですがしかし、その冗長性を無視絵現に認めてしまいますと文字通り憲法の立ち位置というものが曖昧になり、ともすれば空文化という問題が生じてしまうのではないか、憲法の意義の喪失、という懸念が生じることはご承知の通りです。

九条、そして憲法問題を考える場合において避けて通れないのは、憲法九条の問題です。同性婚の問題や尊属殺人の問題に環境権やプライバシー権利、もちろん重大な問題ではあるのですが、個人の世界に関わる問題ではある一方で、安全保障に直結する九条の問題は世界そのものに関わる問題ではあるのですから、これは本題となりますが、重要な視点で。

構造、国の方向性を示すものではあるのですが九条の問題は、しかし安全保障環境と軍事技術の基盤が根本から変容している中にあって77年の時間というものを考えるにはあまりに長すぎるのではないかという視点です。なにしろ憲法制定の1947年はアメリカが唯一の核保有国、ソ連さえも核実験の前であり、核兵器を保有していなかった時代なのですから。

日本国憲法と日米安全保障条約は一体のものである、こう理解されるのはもともと日本が安全保障を依存する構想であったのは進駐軍による安全の確保であり、これは後に1956年に日本が国連加盟を果たしたのちにも国連警察軍のような超国家的な集団安全保障の枠組みも実現することはなく、日本の安保依存の基盤が形成されていました。

憲法の問題、毎年のように考えなければならないことは、現実の議論と思いこみの議論、後者についてはフェイクニュースなのか無知なのかの分水嶺で議論が進むためにかみ合わない状況画議論を進められず、しかし危機というものは制御しなければ進んでゆくために制御せず放置することはかえって事態を危機的な方面へ導いているという認識も必要だ。

九条を念頭に議論しますと、即座に徴兵制の話題をもちだして子供が戦場で死ぬという、論理の飛躍がありすぎるような展開が、これはWeb上などで散見されます、そして何度も同じ方が同じ投稿をしている場合もみられ、これはいわゆる認知戦なのか無知なのかというところが傍目にはみえなくなってしまうのですけれども。

認知戦や接近拒否領域阻止という概念、憲法の安全保障を巡る問題で難しいのは日本国憲法施行当時には核兵器さえアメリカ一国が独占している状態であり、確実なパックスアメリカーナ、自由と公正という意味で、成り立っていた瞬間があるのですが、日本国憲法施行から僅か2年後にソ連が核実験に成功し、ここで平和憲法の土台は崩れていたのですね。

1950年の警察予備隊創設、1951年の日米安全保障条約締結、1956年の集団安全保障機構である国際連合加盟、本来ならばここで解決しておくべきであった安全保障との向き合い方ではあるのかもしれませんが2020年代、ロシアウクライナ戦争と台湾海峡、そして朝鮮戦争という日本に影響が及ぶ緊張を背景に、今一度向き合い方を考えるべきなのでしょう。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)