■米海兵隊二〇三〇年代への挑戦
アメリカ海軍の艦艇と云えば巨大な艦艇の大艦隊という印象ですが近年は小回りというものも併せて艦隊計画が進められています。

LAW軽揚陸艦。アメリカ海軍が小型揚陸艦というべきものを模索しているようです。主として海兵隊の揚陸支援用にあたるもので、艦内に車両甲板を有するものの、ビーチング能力、海上自衛隊の輸送艦ゆら型のような艦首に観音扉状の揚陸ランプを設置し敵前に上陸するようなものではなく、ランプを船体後部に配置した支援船のような設計の揚陸艦です。

LAW軽揚陸艦は30隻程度を量産する計画で、造船各社に提案書を要求している段階ですが、その設計はシーステート5という4m程度の波浪で運用でき、機動力は巡航速度14ノットで3500海里の航続距離を有し、乗員は40名以下で兵員75名程度の居住区画を有し、艦内に最低でも全長60mの車両甲板を有しM-1A1戦車などの重車両を輸送、というもの。

アメリカ海軍といえば巨大なアメリカ級強襲揚陸艦やワスプ級強襲揚陸艦といった四万t級の、諸外国の航空母艦さえ凌駕する全通飛行甲板型船体のものや、二万t級のサンアントニオ級ドック型揚陸艦などがありますが、いわゆる支援任務的な要素、定期整備を終えた重車両の兵站拠点間の輸送や管理替による装備の輸送などにはいかにも大きすぎます。

陸上自衛隊は現在、南西諸島防衛への独自の輸送船を検討中です。海上自衛隊の作戦輸送に用いる輸送艦ほど戦闘を念頭としたものではありませんが、現在、政府傭船の高速フェリーはくおう等、そして民間フェリーなどに間借りして訓練輸送などを実施しています。訓練輸送とは輸送訓練が輸送の訓練に対して北海道等訓練移動する為の機動、ということ。

アメリカ海兵隊への支援用となる今回のLAW軽揚陸艦計画、細部を見てみますと、自衛隊向きの揚陸艦なのですね。輸送船ではなく揚陸艦としているために、港湾での役務に重点を置いていますがランプを有しており、そして航続距離も充分、日本海や太平洋での厳しい波浪にたいしても台風でも来ていない限り、十分対応でき、そして何より安価である。

ウエストパックエクスプレスやスピアヘッド級遠征高速輸送艦、アメリカ海軍はオーストラリア製高速フェリーを軍事支援輸送用に活用していますが、用途としてはこちらにちかいもようです。ただ、LAW軽揚陸艦は建造費用を抑えることも併せて重視しており例えば商船設計を多用することで船体構造寿命を10年程度に妥協も要求仕様に盛り込まれました。

フランクベッソン級輸送揚陸艦やラニーミード級支援揚陸艇、アメリカ陸軍も海軍とは別に独自の輸送艦を有しています、こちらは艦首に揚陸扉を配置しており、こちらを導入したフィリピン海軍などは戦車揚陸艦として活用していますが、アメリカ陸軍の場合は上陸作戦で先陣を切って動員する用途は考えておらず、やはり平時を中心に支援用、という。

ラニーミード級であればアメリカ陸軍が横浜ノースドックに配備している様子がみなとみらい地区などから望見できます。1200t規模の使いやすそうな揚陸艇ですが、しかし港湾地区での役務作業を想定しており浄水施設や海水濾過設備を有しておらず、つまり手洗いや入浴など長期間の運用は想定していません。しかし、LAW軽揚陸艦の要求は少し厳しい。

LAW軽揚陸艦、LAWというとM-72/66mm軽対戦車弾を思い出してしまう、この揚陸艦は上記の通り海兵など75名程度の便乗者を想定し、また航続距離も3500海里が要求されていますので、ハワイから横浜までの4020海里は直行できませんが、サンディエゴからハワイまでは2340マイル、つまりグアムなどを経由することで太平洋横断も可能となります。

沿岸連隊。LAW軽揚陸艦のような装備が必要となっている背景には、アメリカ海兵隊が2030年代を見越して進めている部隊改編が挙げられます。この沿岸連隊とは一種の諸兵科連合部隊であり、戦車大隊などを全廃し統合、沖縄駐留第3海兵師団を大規模に改編し3個沿岸連隊へ改編予定となっています。もっとも第3海兵師団に戦車大隊はありませんが。

海兵師団の沿岸連隊とはAAV-7両用強襲車やM-1A1戦車をもともと編成に内部化し海兵軽装甲偵察中隊や海兵大隊とともに一つの戦闘団単位を基本とする、いわばMEU海兵遠征群のような即応部隊の編成を常設化する、自衛隊の即応機動連隊を大型化したような編成です。これにより即応部隊の作戦単位が増加するのですが、即ち展開の細分化にもつながる。

LAW軽揚陸艦と沿岸連隊。この整備の目的とすることは海兵隊の原点回帰といえるのかもしれません、海兵隊が船舶警備部隊から現在の水陸両用部隊となった背景には太平洋に1920年代から日本との緊張を背景に島嶼部の戦闘を重視する必要性が高まったためです。ただ、LAWや沿岸連隊は日本とは敵対せず寧ろ伍して、新しい脅威へ向けられています。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
アメリカ海軍の艦艇と云えば巨大な艦艇の大艦隊という印象ですが近年は小回りというものも併せて艦隊計画が進められています。

LAW軽揚陸艦。アメリカ海軍が小型揚陸艦というべきものを模索しているようです。主として海兵隊の揚陸支援用にあたるもので、艦内に車両甲板を有するものの、ビーチング能力、海上自衛隊の輸送艦ゆら型のような艦首に観音扉状の揚陸ランプを設置し敵前に上陸するようなものではなく、ランプを船体後部に配置した支援船のような設計の揚陸艦です。

LAW軽揚陸艦は30隻程度を量産する計画で、造船各社に提案書を要求している段階ですが、その設計はシーステート5という4m程度の波浪で運用でき、機動力は巡航速度14ノットで3500海里の航続距離を有し、乗員は40名以下で兵員75名程度の居住区画を有し、艦内に最低でも全長60mの車両甲板を有しM-1A1戦車などの重車両を輸送、というもの。

アメリカ海軍といえば巨大なアメリカ級強襲揚陸艦やワスプ級強襲揚陸艦といった四万t級の、諸外国の航空母艦さえ凌駕する全通飛行甲板型船体のものや、二万t級のサンアントニオ級ドック型揚陸艦などがありますが、いわゆる支援任務的な要素、定期整備を終えた重車両の兵站拠点間の輸送や管理替による装備の輸送などにはいかにも大きすぎます。

陸上自衛隊は現在、南西諸島防衛への独自の輸送船を検討中です。海上自衛隊の作戦輸送に用いる輸送艦ほど戦闘を念頭としたものではありませんが、現在、政府傭船の高速フェリーはくおう等、そして民間フェリーなどに間借りして訓練輸送などを実施しています。訓練輸送とは輸送訓練が輸送の訓練に対して北海道等訓練移動する為の機動、ということ。

アメリカ海兵隊への支援用となる今回のLAW軽揚陸艦計画、細部を見てみますと、自衛隊向きの揚陸艦なのですね。輸送船ではなく揚陸艦としているために、港湾での役務に重点を置いていますがランプを有しており、そして航続距離も充分、日本海や太平洋での厳しい波浪にたいしても台風でも来ていない限り、十分対応でき、そして何より安価である。

ウエストパックエクスプレスやスピアヘッド級遠征高速輸送艦、アメリカ海軍はオーストラリア製高速フェリーを軍事支援輸送用に活用していますが、用途としてはこちらにちかいもようです。ただ、LAW軽揚陸艦は建造費用を抑えることも併せて重視しており例えば商船設計を多用することで船体構造寿命を10年程度に妥協も要求仕様に盛り込まれました。

フランクベッソン級輸送揚陸艦やラニーミード級支援揚陸艇、アメリカ陸軍も海軍とは別に独自の輸送艦を有しています、こちらは艦首に揚陸扉を配置しており、こちらを導入したフィリピン海軍などは戦車揚陸艦として活用していますが、アメリカ陸軍の場合は上陸作戦で先陣を切って動員する用途は考えておらず、やはり平時を中心に支援用、という。

ラニーミード級であればアメリカ陸軍が横浜ノースドックに配備している様子がみなとみらい地区などから望見できます。1200t規模の使いやすそうな揚陸艇ですが、しかし港湾地区での役務作業を想定しており浄水施設や海水濾過設備を有しておらず、つまり手洗いや入浴など長期間の運用は想定していません。しかし、LAW軽揚陸艦の要求は少し厳しい。

LAW軽揚陸艦、LAWというとM-72/66mm軽対戦車弾を思い出してしまう、この揚陸艦は上記の通り海兵など75名程度の便乗者を想定し、また航続距離も3500海里が要求されていますので、ハワイから横浜までの4020海里は直行できませんが、サンディエゴからハワイまでは2340マイル、つまりグアムなどを経由することで太平洋横断も可能となります。

沿岸連隊。LAW軽揚陸艦のような装備が必要となっている背景には、アメリカ海兵隊が2030年代を見越して進めている部隊改編が挙げられます。この沿岸連隊とは一種の諸兵科連合部隊であり、戦車大隊などを全廃し統合、沖縄駐留第3海兵師団を大規模に改編し3個沿岸連隊へ改編予定となっています。もっとも第3海兵師団に戦車大隊はありませんが。

海兵師団の沿岸連隊とはAAV-7両用強襲車やM-1A1戦車をもともと編成に内部化し海兵軽装甲偵察中隊や海兵大隊とともに一つの戦闘団単位を基本とする、いわばMEU海兵遠征群のような即応部隊の編成を常設化する、自衛隊の即応機動連隊を大型化したような編成です。これにより即応部隊の作戦単位が増加するのですが、即ち展開の細分化にもつながる。

LAW軽揚陸艦と沿岸連隊。この整備の目的とすることは海兵隊の原点回帰といえるのかもしれません、海兵隊が船舶警備部隊から現在の水陸両用部隊となった背景には太平洋に1920年代から日本との緊張を背景に島嶼部の戦闘を重視する必要性が高まったためです。ただ、LAWや沿岸連隊は日本とは敵対せず寧ろ伍して、新しい脅威へ向けられています。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)


























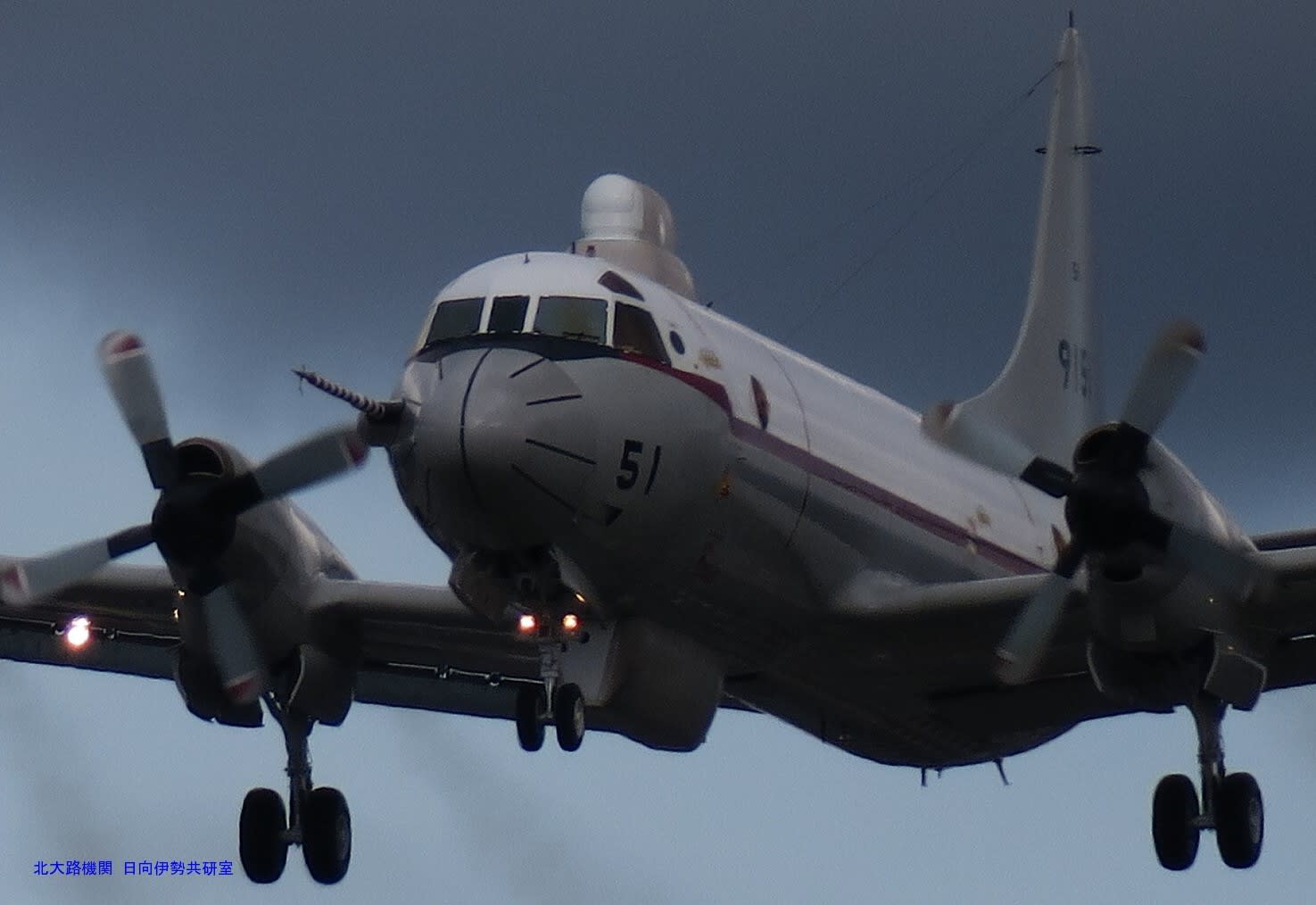























































 す。しかし、こうしたとおり弱点はある、そして暗視装置や通信の重要性を理解していない火星人は、技術力は多少高くとも戦争にかんする戦術や戦略というものを持ち合わせていなかったのかもしれません、ここが最大の弱点であり、そもそも戦争を繰り返す人類には勝てなかったようにも思います。
す。しかし、こうしたとおり弱点はある、そして暗視装置や通信の重要性を理解していない火星人は、技術力は多少高くとも戦争にかんする戦術や戦略というものを持ち合わせていなかったのかもしれません、ここが最大の弱点であり、そもそも戦争を繰り返す人類には勝てなかったようにも思います。









































































