寛永九年七月廿三日妙解公より御奉行江御書之内 全文御書付並御書部御家中江之御書通之条下ニ出
一 肥後之熊本被請取候八代も同日ニ被受取筈候条是も別
儀有間敷と存候 城受取候との儀上使衆可有御注進候間
我等かたより注進申間敷由右ニ年寄衆へ申入候而置候条
無其儀候事
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
七月廿四日四ツ時分ニ首尾能隈本御請取候由目出度存候 江
戸へ之御状箱二ツ廿三日牛之下刻ニ参著仕則大坂へ両使を
相添舟二艘ニて差上せ申候 右両通之内一通ハ因幡殿ニ被留
置候様ニ申遣候 恐惶謹言
七月廿三日
稲葉丹後守様
伊丹播广守様
石川主殿頭様
尚/\八代御請取候御注進可有御座と待申候而罷有候已上










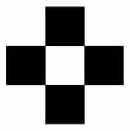 四つ石畳紋
四つ石畳紋





