福岡県史・近世史料編‐細川小倉藩 元和九年覚書から
| 七月朔日 午ノ刻ニ雨フル、半時程大雨也、
|
小人小頭ヲ差上ス | 一、御小人小頭孫六、便舟次第ニ可差上由、横権左・真下七兵衛方ゟ、六月十二日之状、七月朔日巳
| (沢村吉重)
| ノ刻ニ、大学殿ノ使持下り候事 御小人→幕府植生の中での位置
|
採銅所金山ノ報告 | 午ノ刻ニ御鉄炮衆 (井上)
ヲ命ズ | 一、採銅所御金山之様子、言上被仕候へと、宗和へ飛脚遣申候事 採銅所・地図
|
| (林)弥五右衛門・(河田)八右衛門ニ、さしかミ遣候事
| 一、呼野(御)金山へ遣手伝之事、例汰ノ手伝五人 呼野鉱山・地図
| (陶汰)
| 井門亀右衛門くミ 同与 佐兵太くミ
| 児玉角助 十左衛門 半助
| (筑紫重門室、細川幸隆女)
菜園場ノ瓜を上グ | 一、御さいゑん場ノ瓜十一、平次郎持参候ヲ、おかね様へ上ケ申候事
|
利息弐割 | わき/\の利足ノひつかけニ不成事ニ候間、弐わりニして、かし可申ニ相定申事也
作事用ノ米ヲ大工 | 一、御作叓之御用ニ残置候米之事、弐わりニして、御大工衆ニかし、作料ニさし次可申との談合、相
等ニ貸ス | 究候事
|
| 一、和田伝兵衛手伝之事
|
|
| 七月二日 晴天 戌ノ刻ヨリ雨フル、
|
| 一、上田忠蔵、巳ノ刻ニ出船仕候
| さしかミ遣候事
| 採銅所
金山米奉行ノ手伝 | 一、金山米奉行手伝共へ、四人ニ御荒仕子壱人遣事
|
| 村田儀兵衛ニ遣候て、同三日採銅所へ持参事
| 一、採銅所御金山へ、長持遣事
|
| 吉田茂左衛門ニ、直ニ申渡ス也
| 一、しい村之新左衛門、よびニ遣候事
| (志井、規矩郡) 福岡県北九州市小倉南区志井
|
北ノ丸路地ノ用品 | 一、北ノ御丸御路地ニ入申、さうきん・水こし布の事 豊前国小倉城絵図
雑巾水漉布 |
路地箒 | 一、しづらはうき・拾本入申事 しづら→地面(じつら・じめん)か
|
荒仕子死跡ノ借米 | 一、荒仕子ノ内、相果候者之御借米之事
|
|
| 七月三日 晴天 夜前之雨(ニゟ)水出ル也
|
| 松ノ葉無之候て、三拾九俵ひろい候て、帰候由候事、御郡奉行返事、同八日来候事
岩石山ニ松葉採集 | 一、かんしゃく山ニ而、松ノは五十俵取度ノ由、式ア殿ゟ披仰候付、御郡奉行迄切手遣候事
| (岩石・田川郡) (松井興長)
|
石灰 | 一、石ばい三石、式ア殿ゟ、御かり有度ノ由被仰候付而、弥五右衛門・八右衛門へ切手遣候事
|
志井村庄屋ト新左 | (志井、規矩郡) (中津郡)
喧嘩ノ詮議 | 一、しい村庄やと新左衛門と引合、双方口を聞届、新左衛門も親子共ニ御しちへやへ入置候、節丸ノ
質部屋ニ入置 | 彦兵衛事、可尋とて、せつ丸庄や・頭百姓呼ニ被遣候へと、佐方少左衛門・宮部久三郎へ申遣候
惣奉行目付等籠へ | (小篠) (横山重嘉)(米田是次)(矢野)
尋問ニ趣ク | 事、籠へ参、承衆次太夫・太兵衛・助進・左兵衛・助二郎、
|
|
| 七月四日 晴天
宇佐郡ノ加損米郡 | (野田幸長)(田中氏久)
奉行ノ扶持ヲ知行 | 一、宇佐郡畠方ノ御加損米ノさしかミ、御郡奉行ふち取置候ニ付、小左衛門・猪兵衛手前惣積りノ目
方奉行惣積リノ目 | 録ノ高ニ入申候所、百弐十石余ノ米之事
録ニ入ル |
|
大坂蔵奉行ノ用状 | 一、明石源左衛門下着ノ由候て、大坂御蔵本奉行衆ゟノ状持せ被上候、六月十八日之日付也
|
呼野ノ銀否 | 一、呼野ノワキこもり二銀杏在之候■間、納候へと可申付事
|
津川辰珍ノ賄続キ | 一、津川四郎右衛門尉殿留之賄難続由、重畳被申候二付、又、■八月分之御ふちかた、明日相渡候へ
カタシ | と申付候也
|
| 七月五日 晴天
|
松井友好桜井某ノ | (友好)
人ノ出入 | 一、松井宇右衛門・桜井五兵衛人ノ出入二付、松井■采女書物被上候事 出入→俗に、争いごと。もめごと。けんか。
|
吉田茂左下代ト住 | 一、吉田茂左衛門下代之儀二付、住江甚兵衛と出入有之由候て、茂左衛門尉書物幷下代在々にてかり
江元明ノ出入 | 候米銀之書物、三枚被上候事
|
加子走ル二ツキ請 | 一、舟瀬六郎左衛門御預りノ御加子九介、五月廿二日走候付而、請人御のほり衆半介、手前ゟ可相
人昇衆ノ状 | 立儀と、鏡善右衛門被申、半介儀状持参候事
|
| (細川忠興乳母・中村新助妻) (野田幸長)(田中氏久)
大局貸付米 | 一、大御つほね借付米ノ儀、山本小左衛門所ゟ、小左衛門・猪兵衛所へ申来候事
|
| 七月六日 晴天
| (矢野)
| 一、呼野御金山にて、竹内吉兵衛組内田久左衛門尉儀、矢利斎ゟ披申渡、承届候事
| (猪兵衛) (井門重元) (源左衛門)
採銅所金山金奉行 | 一、冨嶋組上田六右衛門・井戸組権兵衛、昨日、採銅所御金山御金奉行手伝二遣候事、明石組池田次
手伝 | 兵衛ハ未遣候事
|
吉田茂左住江元明 | 一、井上加兵衛召寄、茂左衛門訴状之趣申渡、返答候様ニと申うら事判つき候て、書物相渡ス也、茂
| 左衛門へ明石二郎九郎・住江四郎兵衛状茂左衛門返事ノ案見届候
|
三淵好重貸米 | 一、山路太左衛門・桑原主殿・坂崎半兵衛下着候て、御城へ被上候、伊賀殿米之儀ニ付、 御口上之
| 趣被申渡候
|
| (志井・規矩郡) (中津郡)
志井村ノ新左ノ詮 | 一、しい村之新左衛門手前せんさくの儀ニ付、節丸ノ伊井関伝蔵百姓参候て、書物仕らせ、佐方(少)左衛
儀 | 門かた書ニて、書物取置、百姓共在所へ返し申候
|
| 竹木借り候儀
採銅所金山小屋場 | 一、採銅所御金山之儀ニ付、小屋場〇地子之儀覚書ニかた書仕、本書ハ此方ニ取置、うつしヲ仕、
ノ竹木ノ借料地子 | 遣也
|












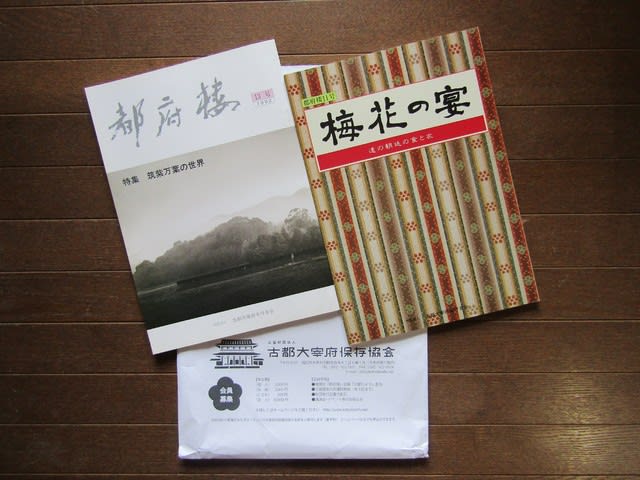




 「~より」は環境依存文字として「ゟ」と表記されるが、三齋公の養女にして宇土細川家初代・行孝公室の源立院の書状にある「......
「~より」は環境依存文字として「ゟ」と表記されるが、三齋公の養女にして宇土細川家初代・行孝公室の源立院の書状にある「......





