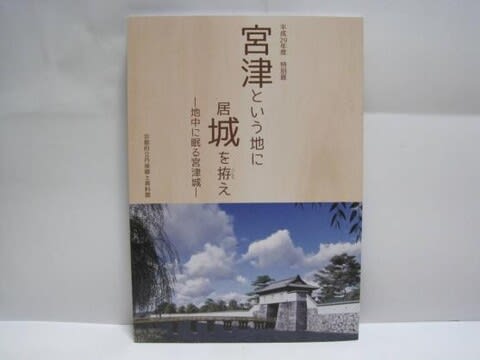日帳(寛永六年八月)廿四日~廿六日
|
| 廿四日 安東九兵衛
|
清心円一貝ヲ伊藤 |一、伊藤金左衛門ニ被遣清心円一かい、御封ノまゝ、金左衛門内櫛坂孫右衛門ニ相渡候、
金左へ渡ス | 伊藤金左衛門内
請取 | 櫛坂孫右衛門(花押)
三斎ノ上洛延期ヲ |一、三斎様御上洛相延候間、其心得被仕候へと、鏡善右衛門・白井兵介に申渡候事、
船頭惣奉行へ告グ |
神西某別苻へ湯治 |一、桑原主殿・神西與三右衛門尉、中津へ参上仕候由被申候、與三右衛門尉ハ豊後之別苻へ湯治仕見
| (長門豊浦郡)
| 可申候、別苻ニ而快気も無之候は、俵山へ湯治可仕と存候通、被申候事、
| (曽根村、規矩郡) (同郡)
曽根・今井・大橋 |一、そね・今井・大橋御作事之儀、河田八右衛門尉ニ申渡候事、
村作事ノ命 | (中津郡)
筑前へ走リシてん |一、一昨日、東小倉ノてんりうの小者筑前へ走越候ヲ、今村之新百姓とらへ来候ニ付、右ノ小者さ
りう寺小者一件 | し候て居申候大わきさしヲ壱腰、右とらへ候百姓ともニ為褒美遣候也、請取切手をとり、御闕所
| 奉行大靏六左衛門尉・波多里右衛門ニ渡置候也、
|
| 廿五日 奥村九兵衛
| (貧僧)
走リシてんりう寺 |一、吉田縫殿登城ニ而被申候ハ、てんりうノ小者町籠ニ入置申、坊主賄費仕候、ひんそうの儀候間、
小者町牢ニ入レ坊 | 何共めいわく仕由、被申候間、急度御誅伐被 仰付候儀にと被申候事、
主ニ賄セシム |
町奉行坊主迷惑故 |
誅伐ヲ望ム |
| (上毛郡) 宕
求菩提山中坊愛宕 |一、求菩提山中坊愛岩堂をたて申候間、材木拝領仕度由被申通、御郡奉行を以被申候間、御年寄衆へ
| (松井興長)
堂ヲ建ツルニ材木 | も其段被申候へと申候処、式ア殿へ申上候ヘハ、御奉行衆へ今日も可被成御談合候へ共、今日は
拝領ヲ願ウ | (清田乗栄) (沢)
家老ノ裁定ニ異見 | 七介殿へ御用御座候而被成御出候間、則少兵衛参候而、此段申候へと被仰候由被申候、此方申候
ハナシ | ハ、御家老衆ゟ遣し候へと被仰上ハ、申分有之間敷候由、申渡候事、
三尺斗リノ打物ニ |一、鍛冶仕事ノ内ニ、弐尺四五寸、三尺斗之打のへ申たる物之ニ、刀ゟ直段たかきもの有之様ニさた
刀ヨリ高直ノ噂 | 〃
鍛冶ノ直ノ吟味ヲ | 御座候間、左様之直段之儀能々吟味被仕候へと、直段奉行衆へ申渡候事、
直段奉行へ命ズ |
|
| 廿六日 安東九兵衛
| (元次) (与脱ヵ)
江戸ヘノ飛脚持上 |一、江戸へ之御飛脚、今日出船仕候、芦田與兵衛与矢野清右衛門・続亀助安藤市右衛門也、右両人持
リシ物ノ覚 | (重政)
| 上り申候物覚
| 一、三斎様ゟ 越中様へ被進候御返書 御文箱一つ幷 三斎様ゟ、江戸にて清田九一郎所へ被遣候
| しふかミ包ノ小箱壱つ、
| 一、中津御奉行衆ゟ、三斎様大坂御蔵本御奉行衆へ被遣候状壱つ、
| (浅山)(田中氏次)
| 一、修理・兵庫言上壱つ、
| 一、金山之衆言上壱つ、
| 一、伊藤金左衛門言上壱つ、
忠利書状下ル |一、江戸ゟ御飛脚両人、寺本八左衛門与久野弥兵衛・山河惣右衛門与内田七左衛門、今日下着申候、
大阪ニ詰小早ナク | 我々共へ之 御書成被下候、大阪ニ詰小早無之候て、かり小早にて罷下候也、江戸を去十五日ニ
借小早ヲ用フ | 立、大阪へ廿日ニ着、其まゝ大坂ゟ廿日ニ出船仕候事、
飛脚ノ行程 |
| (三淵重政)(松井康之女)
|一、右ノ御飛脚中津御奉行衆貴田権内・高橋兵左衛門へ之 御書壱通、右馬助殿御内へ 御書壱通持
| 参候事、
請取 |一、右馬助内へ被成下 御書壱通、私請取申候、 右馬助内
| 竹内市兵衛(花押)