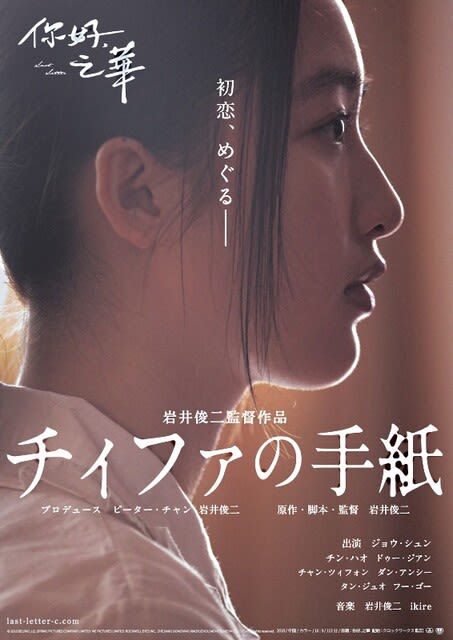映画「こんにちは、私のお母さん」を映画館で観てきました。

中国の喜劇俳優ジアリンによる自身の体験をもとにした脚本を監督して自演した作品だ。母と2人乗りの自転車に乗っているときに交通事故に遭い、重体の母のそばで泣いていたら気がつくと20年前にタイムスリップして自分が生まれる前の母に出会う話だ。母と交わす交情でお涙頂戴の世界である。
期待して映画館に向かったが、もう一歩かなあ。ジアリン演じる主人公が母親に出会う1981年の中国は鄧小平により市場原理を取り入れた経済体制となって間もない時期だ。ひと時代前にTVで見た中国の映像がよみがえる。太っていてコミカルなジアリンは表情豊かで決して悪くないし、若き日の母親役チャン・シャオフェイはひと時代前の三田佳子を思わせる美貌で、存在感がある。だけどちょっとなあ。

明るく元気な高校生ジア・シャオリン(ジア・リン)と優しい母リ・ホワンインは大の仲良し。ジアの大学合格祝賀会を終え、二人乗りした自転車で家に帰る途中、交通事故に巻き込まれてしまう。病院で意識のない母を見てジアは泣き続け、そして気がつくと…20年前の1981年にタイムスリップしていた!
独身の若かりし母(チャン・シャオフェイ)と〝再会〟したジアは、最愛の母に苦労ばかりかけてきたことを心から悔やみ、今こそ親孝行するチャンスだと奮起。自分が生まれなくなっても構わない。母の夢を叶え、幸せな人生を築いてもらうことが、娘としてできる「贈り物」なのだ!だが、やがてジアは“ある真実”に気づく……。(作品情報より)
映画でもカラーTVが一般家庭に普及していないというセリフもある。まだ文化大革命体制の貧しい世界から脱却できていない。いわゆる公営工場での集団労働、大きなスローガン看板が掲げられる社会主義中国の原風景が映る。当時の中国人民のとっぽい服装は90年代に入っても大きくかわっていなかった。香港に90年代初めに行ったとき、大陸人と香港人とはそのどんくささで見分けがすぐついた。1981年ならなおさらだ。

でも、そんな昔を懐かしむ中年以上の中国人たちには受けるだろう。中国ではずいぶんとヒットしたようだ。習近平主席も格差是正で「共同富裕」のスローガンをあげる。まさか、この頃に戻れとは思っていないとは思うけど。

ただ、自分の理解度が弱いからかもしれないが、途中で現実と虚実の境目がぐちゃぐちゃにになり、訳がわからなくなる。人間関係のつながりは見ていて消化不良になってしまうような世界だ。ここ最近、中国の裏社会を描く作品に傑作が目立ったが、これは中国当局が推奨する人民映画みたいな感覚を得てしまう。だからのれないのかな?

中国の喜劇俳優ジアリンによる自身の体験をもとにした脚本を監督して自演した作品だ。母と2人乗りの自転車に乗っているときに交通事故に遭い、重体の母のそばで泣いていたら気がつくと20年前にタイムスリップして自分が生まれる前の母に出会う話だ。母と交わす交情でお涙頂戴の世界である。
期待して映画館に向かったが、もう一歩かなあ。ジアリン演じる主人公が母親に出会う1981年の中国は鄧小平により市場原理を取り入れた経済体制となって間もない時期だ。ひと時代前にTVで見た中国の映像がよみがえる。太っていてコミカルなジアリンは表情豊かで決して悪くないし、若き日の母親役チャン・シャオフェイはひと時代前の三田佳子を思わせる美貌で、存在感がある。だけどちょっとなあ。

明るく元気な高校生ジア・シャオリン(ジア・リン)と優しい母リ・ホワンインは大の仲良し。ジアの大学合格祝賀会を終え、二人乗りした自転車で家に帰る途中、交通事故に巻き込まれてしまう。病院で意識のない母を見てジアは泣き続け、そして気がつくと…20年前の1981年にタイムスリップしていた!
独身の若かりし母(チャン・シャオフェイ)と〝再会〟したジアは、最愛の母に苦労ばかりかけてきたことを心から悔やみ、今こそ親孝行するチャンスだと奮起。自分が生まれなくなっても構わない。母の夢を叶え、幸せな人生を築いてもらうことが、娘としてできる「贈り物」なのだ!だが、やがてジアは“ある真実”に気づく……。(作品情報より)
映画でもカラーTVが一般家庭に普及していないというセリフもある。まだ文化大革命体制の貧しい世界から脱却できていない。いわゆる公営工場での集団労働、大きなスローガン看板が掲げられる社会主義中国の原風景が映る。当時の中国人民のとっぽい服装は90年代に入っても大きくかわっていなかった。香港に90年代初めに行ったとき、大陸人と香港人とはそのどんくささで見分けがすぐついた。1981年ならなおさらだ。

でも、そんな昔を懐かしむ中年以上の中国人たちには受けるだろう。中国ではずいぶんとヒットしたようだ。習近平主席も格差是正で「共同富裕」のスローガンをあげる。まさか、この頃に戻れとは思っていないとは思うけど。

ただ、自分の理解度が弱いからかもしれないが、途中で現実と虚実の境目がぐちゃぐちゃにになり、訳がわからなくなる。人間関係のつながりは見ていて消化不良になってしまうような世界だ。ここ最近、中国の裏社会を描く作品に傑作が目立ったが、これは中国当局が推奨する人民映画みたいな感覚を得てしまう。だからのれないのかな?