最近の若い日本人は素晴らしいと思う。尊敬しています。これこそ日本人の誇りと思う。
特に世界の僻地で、ボランティア活動をしている若い日本人が非常に増えたことを心強いと感じています。
今日はカンボジアの僻地に学校を作り、病院を建設しようとしている若い葉田甲太さんをご紹介したいと存じます。彼は30歳前後の若い医師です。
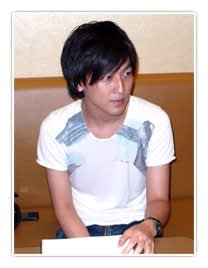
1番目の写真が葉田甲太さんです。彼は2004年にカンボジアに小中学校を作りました。

2番目の写真は農村の通学風景です。

3番目の写真は農村の住宅の様子を示す写真です。
さて若い葉田甲太さんが何故カンボジアに学校を作り、病院まで建設しようとしているかを説明します。
彼のHPから抜粋してその経緯を説明致します。
詳しくは、「カンボジアの僻地に病院を建設し、8000人の命を守りたい!!」
(https://readyfor.jp/projects/npoaozora )をご覧下さい。
(1)何故、彼は学校を作ったか?
彼の文章をそのまま転載します。しみじみと心に響く文章なので、どうぞごゆっくりお読み下さい。
・・・2004年、当時大学生だった僕は、「カンボジアに150万円あれば小学校が建ちます。」というパンフレットを、渋谷の郵便局で見かけ、仲間を募り、お金を集め2005年、カンボジアのコンポントム州に小学校を建設しました。その経緯を綴った『僕たちは世界を変えることができない。』は書籍化され、2011年に東映より映画になりました。
そして、その後もたくさんの方のおかげで支援は継続され、現在、小学校教師6人、中学校教師11人の体制で、小学生220人、中学生280人の子供達が学校に通えています。改めて感謝致します。本当にありがとうございました。

4番目の写真は彼が作った学校の生徒達と先生達です。
(2)何故、病院まで作ろうとしているのか?
2014年、社会人となり、継続支援のため、小学校のある村を訪れたときに、生後22日目の赤ちゃんを肺炎で亡くしたお母さんに出会いました。亡くなる前に、赤ちゃんの呼吸が早くなっていることにお母さんは気付いていたようですが、病院までの交通費がなく、お母さんは受診をためらったそうです。いよいよ、赤ちゃんの状態が深刻になった時に、村長に借金をして州の大きな病院に向かったそうですが、病院に向かうバイクタクシーの途中で、赤ちゃんはもう亡くなっていました。
お母さんは赤ちゃんの呼吸がとまっていることに気付かず、遺体を抱えたまま、州の病院に着くと、お医者さんに赤ちゃんが亡くなっていることを告げられたそうです。それから、お母さんはバイクタクシーにもう一度乗り自宅に帰り、自宅の近くに赤ちゃんの遺体を埋めました。お母さんには、バイクタクシーの借金だけが残りました。
現地の救急車(バイクタクシー)に乗るためには高額なお金が必要です。
支援というのはとても、難しいものです。現地の自立や持続可能性を考えなければなりませんし、支援が現地にとって有害になる事も時にあります。人の幸せはそれぞれですし、自分が思う「幸せ」も、現地にとっての「幸せ」とは限りません。
それでも、一つだけ確かなことは、お母さんはこの話をする時に、ずっと泣いていました。
肌の色や、信じていることは違っても、よほど特殊な状況でない限り、自分の子供を亡くし、悲しくないお母さんは、世界中でいません。
その涙は適切な行動さえすれば、減らせる「涙」のような気がしましたし、減らなきゃいけない「涙」のような気がしました。

5番目の写真は赤ちゃんを亡くした夫婦です。
亡くなった赤ちゃんや、泣いていたお母さんに何かできないかと、カンボジアから帰国後、臨床医として地域で働き、長崎大学大学院の熱帯医学講座にて、亡くなっていく赤ちゃんをどうやったら減らせるかについて学びに行きました。
肺炎には抗生剤、下痢には経口補水塩(ORS)、マラリアには診断キットや蚊帳などが整備されたこともあり、5歳未満死亡率は、減少しています。しかし、生後1ヶ月未満、いわゆる新生児死亡率の減少は、世界的にまだまだ緩慢で、未だに世界で出産当日に100万人の赤ちゃんが亡くなり、期待されたほど減少していないことを知りました。
そして、医学的に教育を受けた熟練された助産師さんが出産に立ち会い適切な処置を施せば、適切な医療サービスがあれば、新生児の死亡を約4割減らすことができることも分かりました。
それと同時にある迷いも生まれました。
いわゆる国際協力といった世界で、研究や、行政機関や、現場レベルで素晴らしい活動をされている方は、既にたくさんいらっしゃいます。
そんな中で、自分が行動したところで、なんの意味があるのだろう。ある国の、ある州の、ある村の、ある事柄が改善したところで、世界の何が変わるというのだろう。結局自分は微力じゃないか。自分の自己満足なんじゃないだろうか。
そんなことを考えていたある日、長崎での日々が終わり、日本の離島の診療所で働いていた時に、ある女子中学生に出会いました。
(3)離島に住む女子中学生に教わったこと。
「映画『僕たちは世界を変えることができない。』を見て、将来私もお医者さんになって、途上国の医療に貢献したいと思うようになりました!」と、その女の子は、自分の夢を語ってくれました。
僕はその時、初めて知りました。自分の活動や、書いた本や映画で、時に人に影響を与えられることがある事を。
行動すればするほど、自分の力が微力であることを、知ります。
勉強すれば勉強するほど、世界はとても複雑で、自分の力ではどうしようもないことが、無数にあることを知ります。
それでも、その活動が微力でも、誰かに影響を与え、まわりまわって、世界は少しづつゆっくり良くなっていくんじゃないか。
たとえ自分の力が微力でも、自分の行動がきっかけで、誰かが新たな行動を起こしてくれるかもしれないこと。
そして、その力が合わされば、時に大きな力になるかもしれないこと。
恥ずかしながら、そんなことを、何歳も年下の日本の中学生の女の子が、逆に僕に教えてくれました。
カンボジアでのお母さんとの出会い、長崎大学大学院の熱帯医学講座、日本での臨床医の経験、島のお医者さんを目指す女子中学生との出会いを経て、「どうやったら赤ちゃん・お母さんの命を守ることができるか」をもう一度考え行動しました。
建設した小学校にワールド・ビジョンという国際NGOが支援してくれていた経緯もあり、ただ情熱のままに連絡を取り、話し合いの末、国際NGOワールド・ビジョン協力の元、母子の命を守るための病院建設を進めていくことになりました。
候補に上がったのはバンティ・ミエンチャイ州のサンブール保健センターでした。
・・・以下省略します。
この活動は2014年に始まりました。もう病院は完成していることでしょう。
今日の記事も長くなってしまいましたが、最後に何故、カンボジアを取り上げたかを書かせて下さい。
それは私の幼馴染がカンボジアが好きで足繁く通っているからです。その理由は、2018年03月05日に掲載した次の記事に書いてあります。
平野茂樹著、「カンボジアの夕日と子供達の瞳に魅せられて」です。
それにしても若い葉田甲太君の次の言葉が感動的でした
「私の活動が微力でも、誰かに影響を与え、まわりまわって、世界は少しづつゆっくり良くなっていくんじゃないか」。
老人の私は、最近の若い日本人は素晴らしいと思います。尊敬しています。
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)
===追記、病院は2018年2月に完成しました=============
「サンブール保健センター開院式のご報告」2018年02月28日
2018年2月11日、サンブール保健センターの開院式がありました。
産前産後待機室を含む8部屋を完備し、雨季の洪水対策のため、6mほどの高床式の病院が完成しました。

6番目の写真は完成したサンブール保健センターの写真です。

7番目の写真は開院式の様子です。
以下は葉田甲太さんの話です。(https://readyfor.jp/projects/npoaozora/announcements/72605 )
・・・ 本プロジェクトに関わって頂いた、すべての皆様本当にありがとうございました。
ご寄付を頂いた方、ツイッターやFBで拡散して頂いた方、応援して頂いた方、すべての方のおかげでセカンドゴールを達成する事ができました。
開院式の日は、とても晴れた日でした。
以前、出会った時は、お子さんを失い、涙を流していたMaoさんも開院式に来てくださいました。
今回の開院式で再会すると、今は妊娠八ヶ月となり、初めての女の子だと、喜んでおられました。
そして、住民、ヘルスセンタースタッフのたくさんの笑顔を見ることができました。
新生児蘇生法の講習会では、日本の小児科医の先生が、本当に尽力してくださいました。
ふとしたキッカケで、2005年に僕はカンボジアと出会いました。そこから、小学校に通い続け、赤ちゃんを亡くしたお母さんと出会い、今度は医師として、何かできないかと、探し続け、自分の無力さ、ご協力いただいた方への感謝を、とても感じる数年間でした。
そんな中、僕が、クラウドファンディングやこのプロジェクトで、一番驚いたのは、ご協力いただいた方から、「ありがとう」と言われた事でした。
ご寄付を頂いたり、たくさんご協力いただいたにも関わらず、ありがとうと言ってくださる方がいました。
こういうことをやってみたかったから、関われて嬉しいとのことでした。
僕は、そういった方々に、どれだけお世話になっているのだろうと、思いました。
どうやったら、そういった方々に、御恩を返していけるだろうと、考えました。
ご報告するのは、もちろんですが、僕はその御恩を返していけるように、やっぱりこれからも行動を続けていこうと思います。
たくさん、ご協力いただき、本当にありがとうございました。
皆様の一人一人の、ご協力のおかげで、無事、写真にあるようなサンブール保健センターを開院させる事ができました。
そして、この病院で母子の健康を守り、たくさんの方の笑顔をつくる事ができそうです。
そんな瞬間に携われた事を、僕はこの先も、きっと忘れることはないと思います。
ありがとうじゃ足りないかもしれませんが、ご協力いただき、本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。 葉田甲太
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特に世界の僻地で、ボランティア活動をしている若い日本人が非常に増えたことを心強いと感じています。
今日はカンボジアの僻地に学校を作り、病院を建設しようとしている若い葉田甲太さんをご紹介したいと存じます。彼は30歳前後の若い医師です。
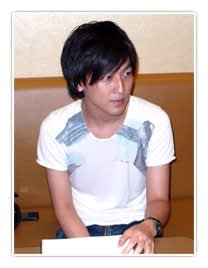
1番目の写真が葉田甲太さんです。彼は2004年にカンボジアに小中学校を作りました。

2番目の写真は農村の通学風景です。

3番目の写真は農村の住宅の様子を示す写真です。
さて若い葉田甲太さんが何故カンボジアに学校を作り、病院まで建設しようとしているかを説明します。
彼のHPから抜粋してその経緯を説明致します。
詳しくは、「カンボジアの僻地に病院を建設し、8000人の命を守りたい!!」
(https://readyfor.jp/projects/npoaozora )をご覧下さい。
(1)何故、彼は学校を作ったか?
彼の文章をそのまま転載します。しみじみと心に響く文章なので、どうぞごゆっくりお読み下さい。
・・・2004年、当時大学生だった僕は、「カンボジアに150万円あれば小学校が建ちます。」というパンフレットを、渋谷の郵便局で見かけ、仲間を募り、お金を集め2005年、カンボジアのコンポントム州に小学校を建設しました。その経緯を綴った『僕たちは世界を変えることができない。』は書籍化され、2011年に東映より映画になりました。
そして、その後もたくさんの方のおかげで支援は継続され、現在、小学校教師6人、中学校教師11人の体制で、小学生220人、中学生280人の子供達が学校に通えています。改めて感謝致します。本当にありがとうございました。

4番目の写真は彼が作った学校の生徒達と先生達です。
(2)何故、病院まで作ろうとしているのか?
2014年、社会人となり、継続支援のため、小学校のある村を訪れたときに、生後22日目の赤ちゃんを肺炎で亡くしたお母さんに出会いました。亡くなる前に、赤ちゃんの呼吸が早くなっていることにお母さんは気付いていたようですが、病院までの交通費がなく、お母さんは受診をためらったそうです。いよいよ、赤ちゃんの状態が深刻になった時に、村長に借金をして州の大きな病院に向かったそうですが、病院に向かうバイクタクシーの途中で、赤ちゃんはもう亡くなっていました。
お母さんは赤ちゃんの呼吸がとまっていることに気付かず、遺体を抱えたまま、州の病院に着くと、お医者さんに赤ちゃんが亡くなっていることを告げられたそうです。それから、お母さんはバイクタクシーにもう一度乗り自宅に帰り、自宅の近くに赤ちゃんの遺体を埋めました。お母さんには、バイクタクシーの借金だけが残りました。
現地の救急車(バイクタクシー)に乗るためには高額なお金が必要です。
支援というのはとても、難しいものです。現地の自立や持続可能性を考えなければなりませんし、支援が現地にとって有害になる事も時にあります。人の幸せはそれぞれですし、自分が思う「幸せ」も、現地にとっての「幸せ」とは限りません。
それでも、一つだけ確かなことは、お母さんはこの話をする時に、ずっと泣いていました。
肌の色や、信じていることは違っても、よほど特殊な状況でない限り、自分の子供を亡くし、悲しくないお母さんは、世界中でいません。
その涙は適切な行動さえすれば、減らせる「涙」のような気がしましたし、減らなきゃいけない「涙」のような気がしました。

5番目の写真は赤ちゃんを亡くした夫婦です。
亡くなった赤ちゃんや、泣いていたお母さんに何かできないかと、カンボジアから帰国後、臨床医として地域で働き、長崎大学大学院の熱帯医学講座にて、亡くなっていく赤ちゃんをどうやったら減らせるかについて学びに行きました。
肺炎には抗生剤、下痢には経口補水塩(ORS)、マラリアには診断キットや蚊帳などが整備されたこともあり、5歳未満死亡率は、減少しています。しかし、生後1ヶ月未満、いわゆる新生児死亡率の減少は、世界的にまだまだ緩慢で、未だに世界で出産当日に100万人の赤ちゃんが亡くなり、期待されたほど減少していないことを知りました。
そして、医学的に教育を受けた熟練された助産師さんが出産に立ち会い適切な処置を施せば、適切な医療サービスがあれば、新生児の死亡を約4割減らすことができることも分かりました。
それと同時にある迷いも生まれました。
いわゆる国際協力といった世界で、研究や、行政機関や、現場レベルで素晴らしい活動をされている方は、既にたくさんいらっしゃいます。
そんな中で、自分が行動したところで、なんの意味があるのだろう。ある国の、ある州の、ある村の、ある事柄が改善したところで、世界の何が変わるというのだろう。結局自分は微力じゃないか。自分の自己満足なんじゃないだろうか。
そんなことを考えていたある日、長崎での日々が終わり、日本の離島の診療所で働いていた時に、ある女子中学生に出会いました。
(3)離島に住む女子中学生に教わったこと。
「映画『僕たちは世界を変えることができない。』を見て、将来私もお医者さんになって、途上国の医療に貢献したいと思うようになりました!」と、その女の子は、自分の夢を語ってくれました。
僕はその時、初めて知りました。自分の活動や、書いた本や映画で、時に人に影響を与えられることがある事を。
行動すればするほど、自分の力が微力であることを、知ります。
勉強すれば勉強するほど、世界はとても複雑で、自分の力ではどうしようもないことが、無数にあることを知ります。
それでも、その活動が微力でも、誰かに影響を与え、まわりまわって、世界は少しづつゆっくり良くなっていくんじゃないか。
たとえ自分の力が微力でも、自分の行動がきっかけで、誰かが新たな行動を起こしてくれるかもしれないこと。
そして、その力が合わされば、時に大きな力になるかもしれないこと。
恥ずかしながら、そんなことを、何歳も年下の日本の中学生の女の子が、逆に僕に教えてくれました。
カンボジアでのお母さんとの出会い、長崎大学大学院の熱帯医学講座、日本での臨床医の経験、島のお医者さんを目指す女子中学生との出会いを経て、「どうやったら赤ちゃん・お母さんの命を守ることができるか」をもう一度考え行動しました。
建設した小学校にワールド・ビジョンという国際NGOが支援してくれていた経緯もあり、ただ情熱のままに連絡を取り、話し合いの末、国際NGOワールド・ビジョン協力の元、母子の命を守るための病院建設を進めていくことになりました。
候補に上がったのはバンティ・ミエンチャイ州のサンブール保健センターでした。
・・・以下省略します。
この活動は2014年に始まりました。もう病院は完成していることでしょう。
今日の記事も長くなってしまいましたが、最後に何故、カンボジアを取り上げたかを書かせて下さい。
それは私の幼馴染がカンボジアが好きで足繁く通っているからです。その理由は、2018年03月05日に掲載した次の記事に書いてあります。
平野茂樹著、「カンボジアの夕日と子供達の瞳に魅せられて」です。
それにしても若い葉田甲太君の次の言葉が感動的でした
「私の活動が微力でも、誰かに影響を与え、まわりまわって、世界は少しづつゆっくり良くなっていくんじゃないか」。
老人の私は、最近の若い日本人は素晴らしいと思います。尊敬しています。
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)
===追記、病院は2018年2月に完成しました=============
「サンブール保健センター開院式のご報告」2018年02月28日
2018年2月11日、サンブール保健センターの開院式がありました。
産前産後待機室を含む8部屋を完備し、雨季の洪水対策のため、6mほどの高床式の病院が完成しました。

6番目の写真は完成したサンブール保健センターの写真です。

7番目の写真は開院式の様子です。
以下は葉田甲太さんの話です。(https://readyfor.jp/projects/npoaozora/announcements/72605 )
・・・ 本プロジェクトに関わって頂いた、すべての皆様本当にありがとうございました。
ご寄付を頂いた方、ツイッターやFBで拡散して頂いた方、応援して頂いた方、すべての方のおかげでセカンドゴールを達成する事ができました。
開院式の日は、とても晴れた日でした。
以前、出会った時は、お子さんを失い、涙を流していたMaoさんも開院式に来てくださいました。
今回の開院式で再会すると、今は妊娠八ヶ月となり、初めての女の子だと、喜んでおられました。
そして、住民、ヘルスセンタースタッフのたくさんの笑顔を見ることができました。
新生児蘇生法の講習会では、日本の小児科医の先生が、本当に尽力してくださいました。
ふとしたキッカケで、2005年に僕はカンボジアと出会いました。そこから、小学校に通い続け、赤ちゃんを亡くしたお母さんと出会い、今度は医師として、何かできないかと、探し続け、自分の無力さ、ご協力いただいた方への感謝を、とても感じる数年間でした。
そんな中、僕が、クラウドファンディングやこのプロジェクトで、一番驚いたのは、ご協力いただいた方から、「ありがとう」と言われた事でした。
ご寄付を頂いたり、たくさんご協力いただいたにも関わらず、ありがとうと言ってくださる方がいました。
こういうことをやってみたかったから、関われて嬉しいとのことでした。
僕は、そういった方々に、どれだけお世話になっているのだろうと、思いました。
どうやったら、そういった方々に、御恩を返していけるだろうと、考えました。
ご報告するのは、もちろんですが、僕はその御恩を返していけるように、やっぱりこれからも行動を続けていこうと思います。
たくさん、ご協力いただき、本当にありがとうございました。
皆様の一人一人の、ご協力のおかげで、無事、写真にあるようなサンブール保健センターを開院させる事ができました。
そして、この病院で母子の健康を守り、たくさんの方の笑顔をつくる事ができそうです。
そんな瞬間に携われた事を、僕はこの先も、きっと忘れることはないと思います。
ありがとうじゃ足りないかもしれませんが、ご協力いただき、本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。 葉田甲太
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・









