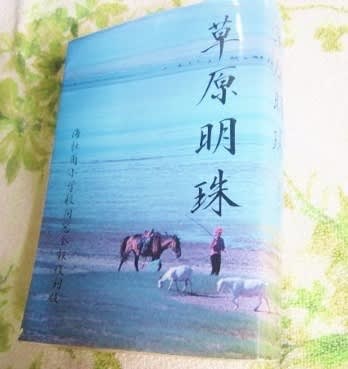多摩の横山の中の雑木林の奥にひっそり建っている禅寺があります。
多摩の横山に平行している多摩尾根幹線道路を町田市の小山田緑地への脇道に下ります。
暫く走ると大泉禅寺という鎌倉時代のお寺が雑木林の奥にあります。
何度か行きましたがそのお寺を散策していると心が静まり座禅をしているような気分になります。
私の好きなお寺なので今日も行って写真を撮って来ました。
写真をお楽しみ頂けたら嬉しく思います。





この大泉寺のある小山田の一帯は小山田氏に支配されていたのです。
小山田氏が1200年前後に大泉寺のある土地に本拠の城を作りました。小山田氏は本拠の城(大泉寺)の他に小野路城、小山田東砦(図師)升 形城(登戸) 小沢城(稲城市川崎市境)を作り、狼煙で連絡を取り合ったといわ れていいます。
この詳しい歴史は、http://www.machida-tky.ed.jp/e-zushi/zushirekishi/pdf/zusinorekisi.pdf に出ています。
1228年創建大泉寺の歴史;
曹洞宗寺院の大泉寺は、補陀山水月院と号します。大泉寺は、小山田別當有重が開基となり、小山田有重が居住していた当地に安貞元年(1228)に起立、無極(永享2年1430年寂)が曹洞宗寺院として開山したといいます。江戸時代には寺領8石の御朱印状を拝領していました。武相卯歳観音霊場四十八ヶ所11番です。
多摩の横山に平行している多摩尾根幹線道路を町田市の小山田緑地への脇道に下ります。
暫く走ると大泉禅寺という鎌倉時代のお寺が雑木林の奥にあります。
何度か行きましたがそのお寺を散策していると心が静まり座禅をしているような気分になります。
私の好きなお寺なので今日も行って写真を撮って来ました。
写真をお楽しみ頂けたら嬉しく思います。





この大泉寺のある小山田の一帯は小山田氏に支配されていたのです。
小山田氏が1200年前後に大泉寺のある土地に本拠の城を作りました。小山田氏は本拠の城(大泉寺)の他に小野路城、小山田東砦(図師)升 形城(登戸) 小沢城(稲城市川崎市境)を作り、狼煙で連絡を取り合ったといわ れていいます。
この詳しい歴史は、http://www.machida-tky.ed.jp/e-zushi/zushirekishi/pdf/zusinorekisi.pdf に出ています。
1228年創建大泉寺の歴史;
曹洞宗寺院の大泉寺は、補陀山水月院と号します。大泉寺は、小山田別當有重が開基となり、小山田有重が居住していた当地に安貞元年(1228)に起立、無極(永享2年1430年寂)が曹洞宗寺院として開山したといいます。江戸時代には寺領8石の御朱印状を拝領していました。武相卯歳観音霊場四十八ヶ所11番です。