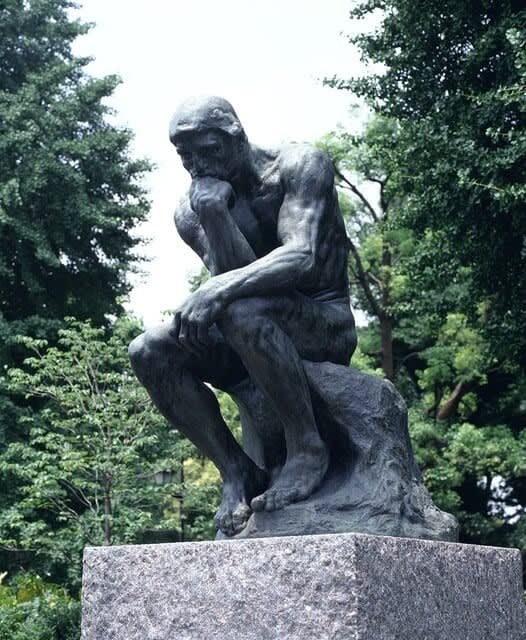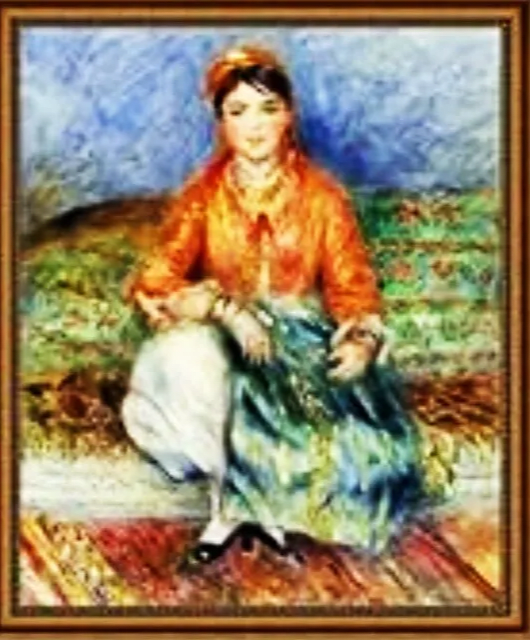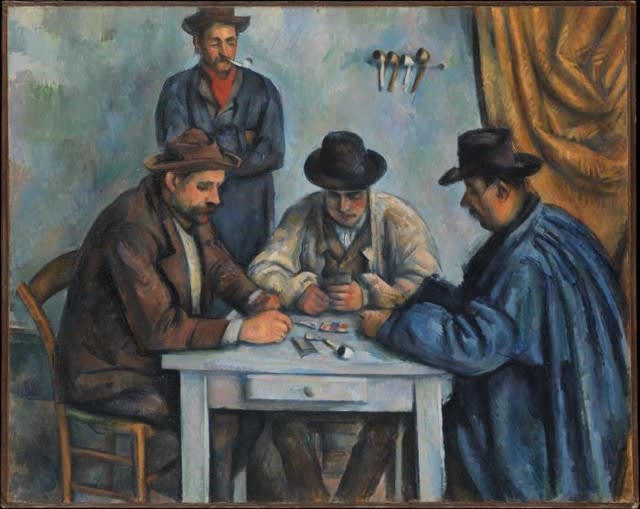今日は「何故日本の藝術に独創性が無いのか?」という問題を考えてみます。その原因はいろいろですが、今日は特に小学校の教育が日本人の独創性を殺してしまうということを具体的に書いてみたいと思います。記述を分かり易く個条書きにしますのでお気軽にお読み下さい。
(1)運動会のような集団行動が子供の独創性を弱くする
まず小学校では国語、算数、理科、歴史、地理以外の科目は教えない方が良いという提案です。
そして学芸会や修学旅行や運動会などといった集団で行う学校行事は一切止めるべきだという問題提起なのです。
日本の学校は協調主義を強要するあまり発達障害を持つ子供の人権を踏みにじっている恐れがあるのです。発達障害を持つ子供だけではありません。いろいろな意味でのマイノリティの人権が軽視されているのです。学校が地獄になっているのです。
以下にある母親から頂いたフランスの小学校の実態を示します。
1、小学校では、遠足や運動会、学芸会と言った集団で行う学校行事はなく、親の参観日も無いのが普通のようです。
2、そもそも、体育とか、音楽、図工、家庭科と言った授業は無いのです。第一そのための設備もありません。
スポーツ、芸術などは、フランスでは各家庭で楽しむことで、学校の集団教育の中で教えることではないらしいのです。
3、水曜日には各地区の学校とは別の施設で、“スポーツやレジャー”という自由な活動があり、スポーツや絵画、焼き物、工作、手芸などの図工から好きなものを選んで、学校の外の指導者もついて、楽しんだり、技術を磨いたりする。参加は全く自由だが、学校ではできない体育、図工の経験がここで補っている。
以上のようにフランスの公的な小学校では余計な学校行事はしないが普通です。日本のように全体主義的な雰囲気がありません。個人の人権を大切にしているようです。
(2)日本の小学校では人権意識が低い教育をしている
日本人には人権意識があまり無いように私は感じています。戦後、マッカーサーのくれた憲法には「基本的人権の尊重」が格調高く謳われていいましたが、日本人は重要視しませんでした。現在でも人権が軽ろんじられています。
その原因の一つに日本の学校教育があると考えられます。
学校では協調性のない子供は差別され冷遇されます。特に発達障害の子供は差別されます。いじめの対象にもなりがちです。
このような教育で成人した人は、他人の苦しみや悲しみが分らない人になります。職場でも、いじめや差別をする人になってしまいます。
イギリスの小学校で子供さんを育てたMionFさんという女性の方から頂いたコメントをご紹介します。
・・・学校と言うのは不思議な場所です。不登校や引きこもりをする子はもちろん少数ですから、そんな子達こそ異常だ、何か問題がある、と言う見方もありますが、そもそも毎日ハッピーに問題なく学校に通う子供の方がおかしいんじゃない?と言う考え方もできませんか?
発達障害があってもなくても学校と言う集団生活にうまくはまれない子達の方が、感情面では成長が早くて大人だったりすることもあります。知能指数(IQ)が高い場合もありますよね。
そんな事実があるにもかかわらず、日本の学校の集団教育にはまらない子ども達は恐ろしく不幸で混迷した学校生活を送ることになります。・・・
(3)発達障碍者の人権軽視の風潮
日本の学校は集団行動の重要性を教えます。それが出来ない生徒を先生は叱ります。先生は自分の言うことに従わない生徒を憎みます。それを見た同級生がその生徒を虐めます。
当然、その生徒の個人的な人権は蹂躙されます。これが現在、日本の学校の虐めや不登校の原因の一つになっています。
ところが発達障害の生徒は先生の言うことに従いたいのですが体が動かないのです。同級生と集団行動をしたいのですが体は別の動きをします。先生は感情的になるばかりで発達障害の生徒の苦しみにまったく無理解なのです。同情の片鱗もありません。
欧米の学校で飛び級をした日本人の生徒が帰国すると、日本では虐めの対象になり潰れされてしまいます。
(4)個性を消し独創性を抹殺す教育とは?
日本人は先天的に独創性が無いのでしょうか?
結論を先に書けば、日本人にも本来は独創性があったが明治維新以後の富国強兵を目的にした集団行動重視の教育が独創性を抹殺したというのが私の主張なのです。そして西洋の科学技術を導入して軍事技術を強化していった社会体制が個人の独創性を必要としなかったのです。
学校教育では先生が協調の重要性を教え生徒の集団行動を訓練します。
勿論、協調性は人間の社会生活を円滑にする大変重要なものです。ですからこそ入社面接では協調性を厳しく評価されるのです。
しかし小学校からあまりにも協調性を押し付ける教育をすると生徒は自分でものを考えないようになります。先生の言う事に従ってさえいれば先生が喜びます。会社に入社しても上司の言うことをよく聞き、同僚と協調する人は出世が早いのです。
しかしこれでは個人の独創性は邪魔になります。こんな教育や社会なので日本人の独創性は育たないのです。
この様子を分かり易く書いた小文を以下に示します。イギリスに長年住んでいる石山 望さんが2017年02月18日にコメントとして送って下さったものです。
・・・基本的に、日本人は、「自分の考え」を持つように教育されていないと思います。
学校でも(高校までならば)、先生の言われることを、金科玉条みたいに信じて、生徒は、質問すらしません。少なくとも私の行った公立学校ではそうでした。
為政者には、こういう国民、実に御し易い。
尤も、あくまで一般論ですが、こういう日本人のあり方にも、勿論、いいところはあります。
極端に、「とんでもない」人が出てこないということです。
私が住む英国では、大抵の子供が、まるで小さな大人みたいに、はっきりと自分の意見を述べる代りに、中には「とんでもない」のがいます。・・・
このようなイギリスの教育は日本に導入されにくいものです。
何故ならイギリスの教育はその社会と密接に関係しているからです。それは日本と同様です。
今日は「日本の藝術や学問に何故独創性が無いか?」という問題にかんして私の考えの一端を書きました。今日は学校における集団教育や協調性の過度な教育が原因ではないかという主張です。
今日の挿絵代わりの写真は岡山県の奈義の菜の花畑です。
詳しくは、、https://www.jalan.net/kankou/spt_33623cb3512096741/ をご覧下さい。
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)