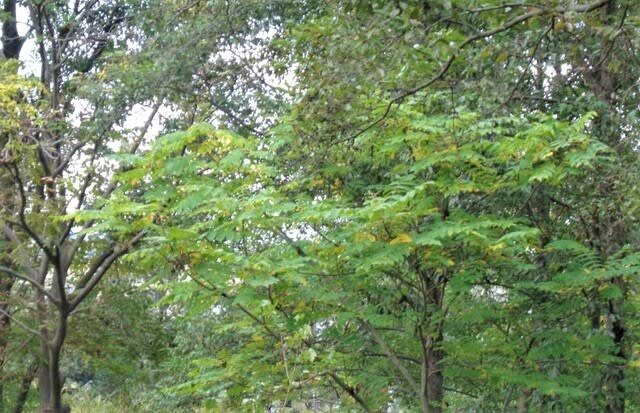東京都の地名は江戸時代の以前の城や 館の名前に由来するものが多いのです。今日は現在の立川市のもとになった立川氏館と町田市の小山田緑地が由来するた小山田城をご紹介したいと思います。
立川市は東京駅から電車で約60分の西方にあります。戦前は陸軍の立川飛行場があり戦後は米軍の立川基地になりました。その基地の拡大に反対した「砂川闘争」は規模と期間が長かったので記憶にある方も多いと思います。
さて立川市という名は明治維新の後につけられた名前です。それまでは南半分は柴崎村と呼び、北半分は砂川村と呼んでいました。
それでは、立川という地名はどういう経緯で出来たのでしょうか?
鎌倉時代から1590年の豊臣秀吉の関東平定までの約370年間、この地方は豪族の立川氏に支配されていたのです。立川氏は立河氏とも書かれていました。現在の立川市は1590年まで立川氏の領地だったのです。
その立川氏の館は現在の立川市柴崎町4丁目の普済寺と同じ敷地にあったのです。立川氏が秀吉によって滅ぼされる直前に普済寺が立川氏の館の敷地の中に移築されたのです。
近年行われた発掘調査の結果、この普済寺の土地には西暦1400年代前半から1500年代前半にかけて立川氏の居館があったことが判明したのです。
一方西暦1252年には立川氏の氏神として八幡神社(柴崎町1丁目)が建てられたことも文書に残っています。すなわち立川氏(立河氏)は鎌倉時代の初期から地方豪族として現在の立川市一帯を統治していたのです。
そこで昨日も、この普済寺のある現地に行ってみました。そこは多摩川の支流の根川の北岸の高台の広い場所です。
南側は根川とその向こうの多摩川が敵の侵入を防いでいます。高台なので西に丹沢の山並みから北の奥多摩の山稜が見渡せます。豪族の館を建てるにはふさわしい場所です。その場所に関東では珍しい規模の臨済宗の普済寺が建っています。それでは昨日、撮って来た写真を示します。

1番目の写真は長い参道の奥にあった本堂の前の楼門です。写真の右下に国宝の六面石幢がありますと書いてます。

2番目の写真は堂々とした庫裏の写真です。左の大屋根は本堂です。

3番目の写真は国宝の六面石幢です。緑泥片岩製の石幢で、延文6年(1361年)に作られました。コンクリート製の覆堂内に保存されてます。石幢は六角形で上部には笠石を乗せ、高さは204.5センチもあります。六面石幢は阿吽の仁王像と四天王像を板石に刻んで組み合わせたもので造立年代は、刻文により延文六年(1361年)7月6日と分ります。この六面石幢は江戸時代から広く知られ、大正二年(1913年)国宝に指定され、戦後、改めて新国宝に指定されました。
さて普済寺は現在は臨済宗建長寺派の寺院で本尊は聖観音菩薩です。この寺は、文和年間(1352年 - 1356年)地頭だった立河(立川)宗恒の開基です。
このお寺は、寺伝によると開創は文和二年(1335)と伝えられており、臨済宗建長寺派に属して、大本山巨福山建長興国禅寺の別格地として多摩一円に末寺十八ケ寺を有する同派屈指の名刹です。
開山当時の場所は明らかではありませんが、永禄六年(1563)に立川氏の居住地に移されたと伝えられています。
普濟寺の境内には土塁の一部が今でも残っており、特に本堂前のものは雄大で一端に数百年を経たと思われる大銀杏があり、壊れを防ぐために石垣で補強をしてあります。
立川氏の政治的立場を分りやすくを箇条書きにします。
(1)鎌倉時代も室町時代も現在の立川市一帯の農民を直接支配していたのは豪族の立川氏であった。
(2)立川氏は鎌倉幕府に忠誠を誓いその隷下にあった。
(3)室町時代の後半に北条氏昭が八王子城に君臨すると北条氏昭の配下になり、秀吉の関東平定で1590年に北条氏昭と共に滅んだ。
(5)立川氏の館の跡地に現在は国宝を持っている臨済宗の普済寺が建っているのです。
それにしても明治時代に立川氏の名前を思い出して砂川村と柴崎村を立川市という名にした人の見識に感銘を受けます。
さて町田市の山間にあった小山田城をご紹介します。
このお城は鎌倉時代が始まる前の承安元年(1171年)、小山田有重によって築かれました。現在は小山田城の跡地には大泉寺があります。 小山田氏は桓武平氏で、秩父重弘の次男の有重が小山田荘に住んで小山田氏を名乗ったのです。
その小山田氏一家は相模国二俣川で討死し、元久2年(1205年)に小山田一族は離散したのです。小山田城は34年の短い悲劇の城だったのです。
この小山田城のあった山を所有し城跡を保存しているのが曹洞宗の大泉寺です。東京都町田市の小山田緑地公園の隣にあります。詳しくは、http://www.hb.pei.jp/shiro/musashi/oyamada-jyo/ をご覧下さい。

4番目の写真は大泉寺の大泉寺の本堂です。
小山田城はこの本堂の裏山にありました。本堂の説明版によると寺の裏山を補陀山(ほださん)と言うそうです。

5番目の写真は補陀山の頂上にある二の丸跡です。写真の出典は次の通りです。http://gi001.gokenin.com/tanbou/13_tokyo/06_minami_tama/005_machida/oyamada/oyamada_jou.html
大泉寺は小山田城の跡地に建てた寺院です。大泉寺は補陀山水月院と号します。小山田城を作った有重が開基となり、小山田有重が居住していた当地に安貞元年(1228)に建てたと言います。そして後に無極和尚が曹洞宗寺院として開山したといいます。江戸時代には寺領8石の御朱印状を拝領していて武相卯歳観音霊場四十八ヶ所11番だったお寺です。
さて鎌倉時代の山にある城は戦いのある時だけ使い、普通は領主は城のある山の下の館に住んでいたのです。その館の下の方には武装した家来たちが住んでいたのです。
ですから現在の小山田緑地あたりには家来の武士たちが住んでいたと考えられます。
今日は現在の立川市のもとになった立川氏館と町田市の小山田緑地が由来する小山田城をご紹介いたしました。
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)