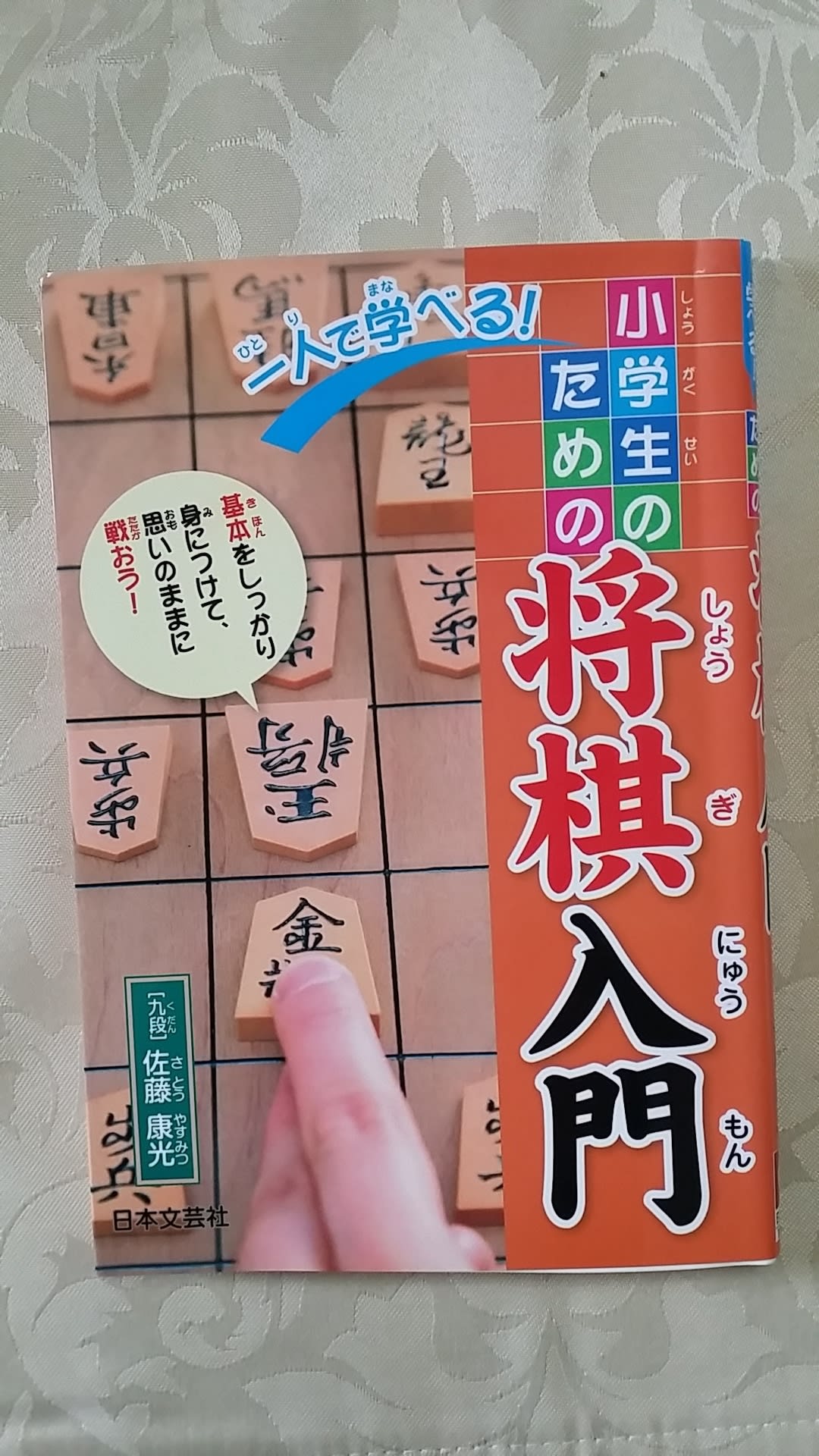今夜は中秋の名月。陰暦の8月15日の名月を芋名月というそうです。
先週、テレビでもクイズ形式で「来週は中秋の名月です。この名月は別名なんと言うでしょうか?」とやっていました。
答えは「芋です。里芋をお供えする芋なづきです!」とのこと。
「いもなづき???」
あまりに堂々とおっしゃるので「そういう言い方もあるのかな?」と思いました。
これってやはり「芋めいげつ」ですよね。
その昔は、名月の夜は子供達が竿の先に釘などをつけて他人のお供え物をとったり、畑の芋を盗んでも大目にみるといった風習もあったとか。言い間違いくらい大目に見なければいけませんね!
ちなみに満月はあさって17日。栗名月は10月13日。十三夜。「後(のち)の月」とも言うそうです。
十五夜のお月見をしたら十三夜のお月見もする方がいいとのこと。一方が欠けるのを「片月見」
と言って嫌ったそうです。
今夜は雲の合間からお月さまが見えるといいですね♪
心地よい秋風に吹かれてのお月見は夏の疲れも吹き飛ぶことでしょう。里芋、すすきや団子を飾られますか?うちは、里芋のお味噌汁でも作ることにしましょう。
里芋を買い物かごに入れる午後 麗
先週、テレビでもクイズ形式で「来週は中秋の名月です。この名月は別名なんと言うでしょうか?」とやっていました。
答えは「芋です。里芋をお供えする芋なづきです!」とのこと。
「いもなづき???」
あまりに堂々とおっしゃるので「そういう言い方もあるのかな?」と思いました。
これってやはり「芋めいげつ」ですよね。
その昔は、名月の夜は子供達が竿の先に釘などをつけて他人のお供え物をとったり、畑の芋を盗んでも大目にみるといった風習もあったとか。言い間違いくらい大目に見なければいけませんね!
ちなみに満月はあさって17日。栗名月は10月13日。十三夜。「後(のち)の月」とも言うそうです。
十五夜のお月見をしたら十三夜のお月見もする方がいいとのこと。一方が欠けるのを「片月見」
と言って嫌ったそうです。
今夜は雲の合間からお月さまが見えるといいですね♪
心地よい秋風に吹かれてのお月見は夏の疲れも吹き飛ぶことでしょう。里芋、すすきや団子を飾られますか?うちは、里芋のお味噌汁でも作ることにしましょう。
里芋を買い物かごに入れる午後 麗