■主権者たる日本国民の責務
憲法議論は憲法解釈というわかりにくい部分が、実定法ではなく司法府と行政府と立法府が運用する憲法故に存在しますが、この視点について。

子供の日という事で考えたいのは、憲法問題をもう少し明確にして子供でも分かるようにしなければならない、というもの。この為には憲法上やっていけない事と自国民を保護する観点から容認される事を明確に示す事で、例えば義務教育にて教わる平和憲法の内容と我が国防衛力という視点に児童生徒が矛盾を感じず済む法体系を構築するべきでしょう。

自衛隊法と日米安全保障条約、PKO協力法に武力攻撃事態法や安全保障協力法、集団的自衛権行使、司法府の結論は全て合憲です。司法府は統治行為論として判断は司法府が行うものではなく行政府管轄であるとして判断を委任した上で、行政府内閣法制局が統一解釈として合憲と判断している為、法的には上記全て合憲です。しかし独自解釈は多々ある。

市民団体等には自衛隊は違憲、に始まり、武力攻撃事態法は違憲、安全保障協力法制は違憲、果ては新護衛艦は違憲に普天間基地は違憲、と自らが一人司法府となり憲法判断を行う事例を散見、いや丸山公園や百万遍では多見します。言い換えれば一人司法府違憲判断は不法判断ですので鳩時計時報の如く受け止める事が自然なのですが制度の欠缺でもある。

違憲ならば改憲、合憲ならばそのまま、という視点からはそれほど違憲を主張するならば合憲となるよう改憲を提案してみてはどうかとも考えつつ、憲法第一主義を掲げる方々は、言い換えれば天皇制を含む日本の現行制度そのものを支持している、国体護持の視点も含むので、この視点はどうかな、と思いつつやはり平和主義の上限明確化が先決とも考える。

一国平和主義は響きこそ美しいのですが、周辺国の軍事恫喝、日本の周辺は核兵器国と核保有国に包囲されている特に厳しい状況下で、その恫喝に耐えて主権を維持する事には限界があります。核武装による一国平和主義、スウェーデン等で戦後真剣に議論された命題を含め考えるならば別ですが、通常戦力だけでも一国で均衡を維持する事は非常に難しい。

重武装中立政策を含む一国平和主義を貫く場合にも、日本は環太平洋火山帯弧状列島故に海洋を防衛正面として守るには有利な立地である一方、火山性地形から食料自給率とエネルギー自給率が限られ、国土の地形上自国の排他的経済水域を防衛するだけでも長大な海軍力が必要で、その上で上記命題に取り組みには最低限シーレーン防衛が不可欠となる。

一国平和主義は地域大国との二極関係を考えるならば均衡主義を、つまり中国に対抗できる兵力均衡、ロシアに対抗できる兵力均衡、というものを維持すればよいのですが我が国の立地は両国と排他的経済水域を接している状況ですので、二国標準主義、イギリスがかつて掲げたような壮大な防衛力が必要となり、このような重武装中立では、現実味が無い。
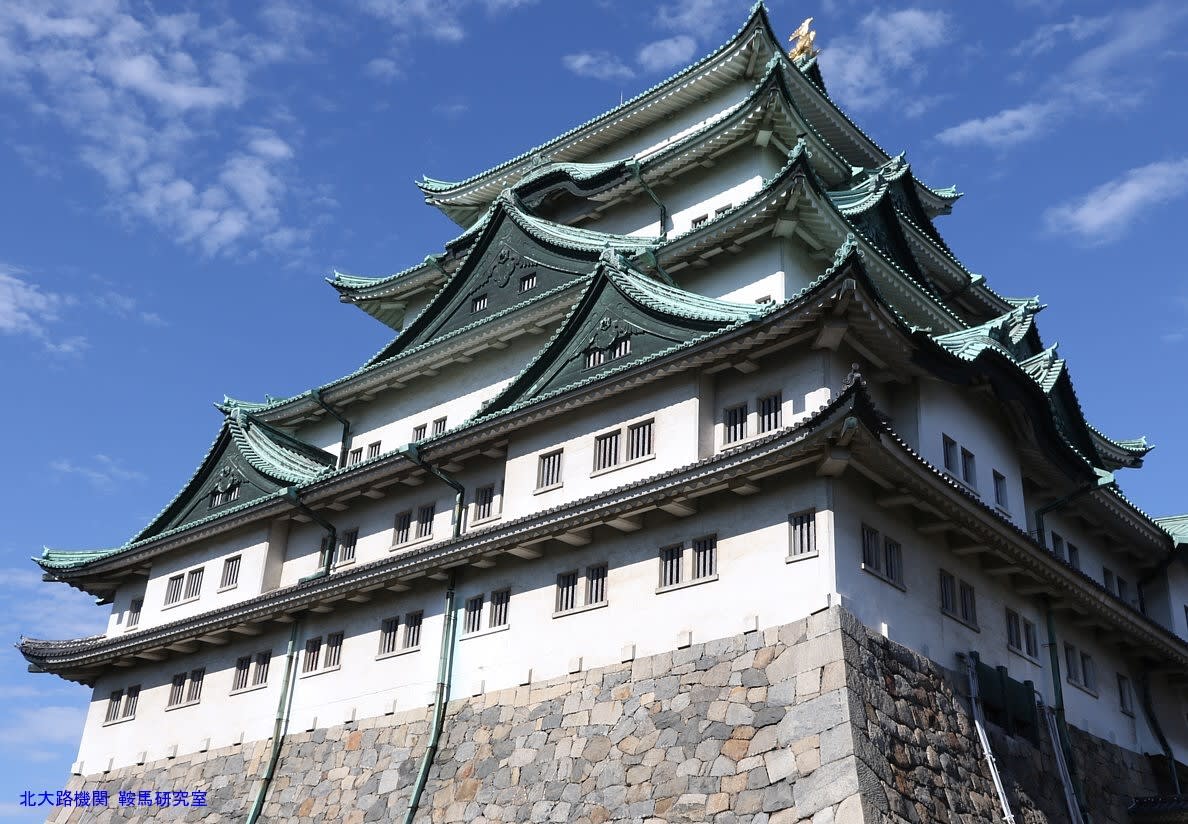
集団安全保障の枠組みの中で、これも繰り返しになりますが日本国は集団的自衛権行使への判断を今世紀まで曖昧としつつ1956年に純然たる集団安全保障機構である国連に加盟しているのですが、集団安全保障の枠組みの中で地域を超えた環太平洋地域における均衡体制や相互抑止の体系を構築せざるを得ない、ここが平和主義の上限を必要とする背景です。

陸海空軍は有さないが自衛軍や防衛軍という呼称ならば合憲か、国際法上の自然権として且つ国際慣習法上の自衛権における集団的自衛権行使に米英仏有志連合のシリア対処や米英有志連合のイラク対処に当たる措置は合憲であるのか、国際慣習法上の自衛権に自衛権の先制行使は何処まで認められ且つ憲法上合憲であるのか、平和憲法の上限はどこまでか。

限定列挙として違憲行動を明確に示す、こうした施策が平和憲法の上限を明確化する施策として考えられます。具体的には領土割譲目的での第三国進出禁止や策源地攻撃における人口密集地に対する絨毯爆撃の禁止、核爆発装置開発と移転導入の禁止や国連安全保障理事会決議に基づかない第三国への武力攻撃の禁止、有事の無制限潜水艦作戦の禁止など。

勿論こうした限定列挙は、明示しますと周辺国の軍事行動に、特に攻撃する側の本土が攻撃や占領されないのならば、と日本に対する過度な軍事行動を行う事に繋がりますので、交戦規則、というような形で部内に明示する形にて、その限定列挙の様式は我が国が加盟する国際法により軍事行動を限定してゆく、という方式がある種自然ではないか、と。

本特集では政治参加の重要性を前述しましたが、重要なのは合憲違憲の論争に終始し不可思議な個人的憲法解釈を吹聴するのではなく、国民主権の国家なのですから憲法解釈以前に、主権者の代表を選挙にて選ぶ際に、判断を委任するに相応しい代表を送る為の努力の在り方、考える事が肝要ではないでしょうか。こうした意味で主権者は責任があるのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
憲法議論は憲法解釈というわかりにくい部分が、実定法ではなく司法府と行政府と立法府が運用する憲法故に存在しますが、この視点について。

子供の日という事で考えたいのは、憲法問題をもう少し明確にして子供でも分かるようにしなければならない、というもの。この為には憲法上やっていけない事と自国民を保護する観点から容認される事を明確に示す事で、例えば義務教育にて教わる平和憲法の内容と我が国防衛力という視点に児童生徒が矛盾を感じず済む法体系を構築するべきでしょう。

自衛隊法と日米安全保障条約、PKO協力法に武力攻撃事態法や安全保障協力法、集団的自衛権行使、司法府の結論は全て合憲です。司法府は統治行為論として判断は司法府が行うものではなく行政府管轄であるとして判断を委任した上で、行政府内閣法制局が統一解釈として合憲と判断している為、法的には上記全て合憲です。しかし独自解釈は多々ある。

市民団体等には自衛隊は違憲、に始まり、武力攻撃事態法は違憲、安全保障協力法制は違憲、果ては新護衛艦は違憲に普天間基地は違憲、と自らが一人司法府となり憲法判断を行う事例を散見、いや丸山公園や百万遍では多見します。言い換えれば一人司法府違憲判断は不法判断ですので鳩時計時報の如く受け止める事が自然なのですが制度の欠缺でもある。

違憲ならば改憲、合憲ならばそのまま、という視点からはそれほど違憲を主張するならば合憲となるよう改憲を提案してみてはどうかとも考えつつ、憲法第一主義を掲げる方々は、言い換えれば天皇制を含む日本の現行制度そのものを支持している、国体護持の視点も含むので、この視点はどうかな、と思いつつやはり平和主義の上限明確化が先決とも考える。

一国平和主義は響きこそ美しいのですが、周辺国の軍事恫喝、日本の周辺は核兵器国と核保有国に包囲されている特に厳しい状況下で、その恫喝に耐えて主権を維持する事には限界があります。核武装による一国平和主義、スウェーデン等で戦後真剣に議論された命題を含め考えるならば別ですが、通常戦力だけでも一国で均衡を維持する事は非常に難しい。

重武装中立政策を含む一国平和主義を貫く場合にも、日本は環太平洋火山帯弧状列島故に海洋を防衛正面として守るには有利な立地である一方、火山性地形から食料自給率とエネルギー自給率が限られ、国土の地形上自国の排他的経済水域を防衛するだけでも長大な海軍力が必要で、その上で上記命題に取り組みには最低限シーレーン防衛が不可欠となる。

一国平和主義は地域大国との二極関係を考えるならば均衡主義を、つまり中国に対抗できる兵力均衡、ロシアに対抗できる兵力均衡、というものを維持すればよいのですが我が国の立地は両国と排他的経済水域を接している状況ですので、二国標準主義、イギリスがかつて掲げたような壮大な防衛力が必要となり、このような重武装中立では、現実味が無い。
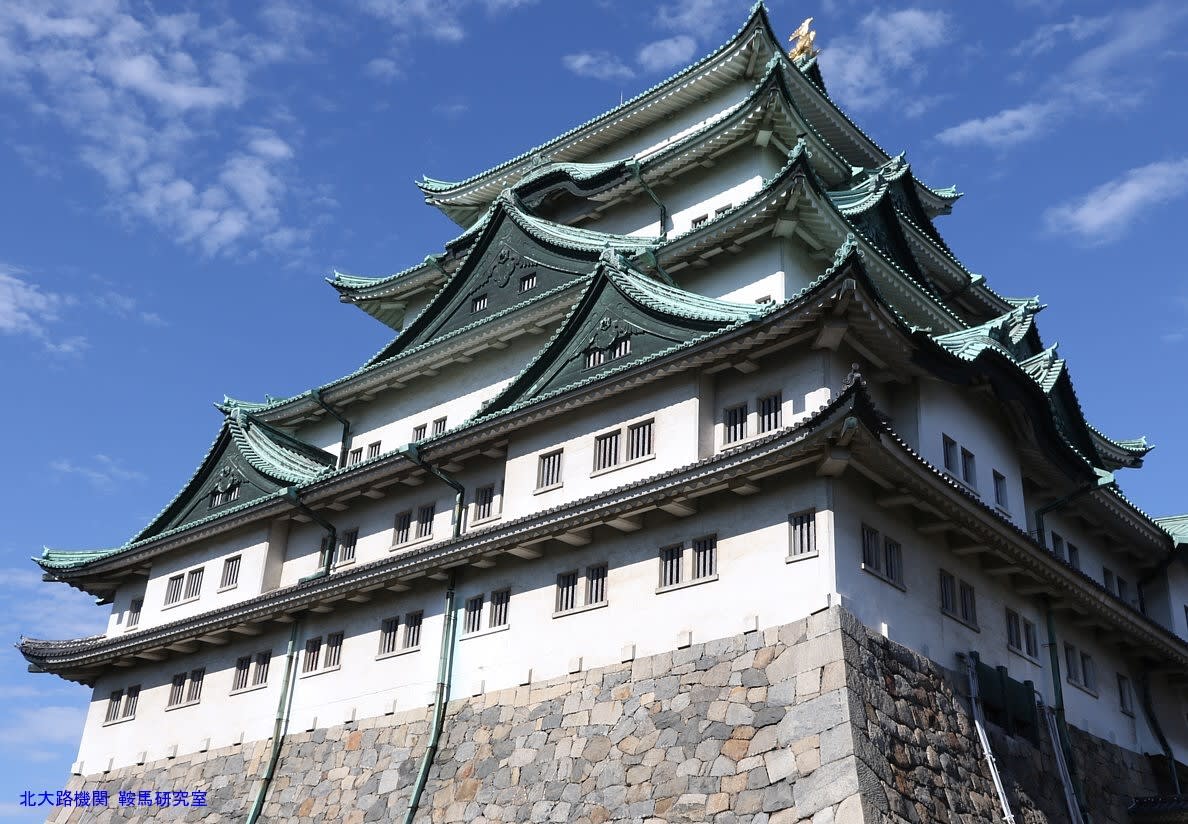
集団安全保障の枠組みの中で、これも繰り返しになりますが日本国は集団的自衛権行使への判断を今世紀まで曖昧としつつ1956年に純然たる集団安全保障機構である国連に加盟しているのですが、集団安全保障の枠組みの中で地域を超えた環太平洋地域における均衡体制や相互抑止の体系を構築せざるを得ない、ここが平和主義の上限を必要とする背景です。

陸海空軍は有さないが自衛軍や防衛軍という呼称ならば合憲か、国際法上の自然権として且つ国際慣習法上の自衛権における集団的自衛権行使に米英仏有志連合のシリア対処や米英有志連合のイラク対処に当たる措置は合憲であるのか、国際慣習法上の自衛権に自衛権の先制行使は何処まで認められ且つ憲法上合憲であるのか、平和憲法の上限はどこまでか。

限定列挙として違憲行動を明確に示す、こうした施策が平和憲法の上限を明確化する施策として考えられます。具体的には領土割譲目的での第三国進出禁止や策源地攻撃における人口密集地に対する絨毯爆撃の禁止、核爆発装置開発と移転導入の禁止や国連安全保障理事会決議に基づかない第三国への武力攻撃の禁止、有事の無制限潜水艦作戦の禁止など。

勿論こうした限定列挙は、明示しますと周辺国の軍事行動に、特に攻撃する側の本土が攻撃や占領されないのならば、と日本に対する過度な軍事行動を行う事に繋がりますので、交戦規則、というような形で部内に明示する形にて、その限定列挙の様式は我が国が加盟する国際法により軍事行動を限定してゆく、という方式がある種自然ではないか、と。

本特集では政治参加の重要性を前述しましたが、重要なのは合憲違憲の論争に終始し不可思議な個人的憲法解釈を吹聴するのではなく、国民主権の国家なのですから憲法解釈以前に、主権者の代表を選挙にて選ぶ際に、判断を委任するに相応しい代表を送る為の努力の在り方、考える事が肝要ではないでしょうか。こうした意味で主権者は責任があるのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)















