
(午前9時前)
きょうで霜月・11月もお仕舞です。あしたからは師走・12月に入ります。12月ですよ、もう今年もお仕舞ということです。いやはや何ともかんとも。・・・・。長嘆息してみたところでどうなるわけでもないのですが、何となく気忙しくなることは確かですね。

なんかこれは日本人に特有?な現象とか。まあそれだけ大晦日から新年を迎える時期というのは日本人にとって特別なものがあるということなのでしょうね。でもこれもそのうち大きく変わってくるのでしょうね、われわれが消えて行って、若い人たちが多くなって来れば。


それにしても11月の後半は気温の上下が激しいですね。 きのうあるサークルの忘年会があったのですが、オーバーコートを着て行って正解だった。帰りは寒かったです。逆にマフラーも欲しかったくらいです。マフラーを巻いて手袋もして行きたかった。

まあ今は旧暦では、「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」 小雪次候 です。我が家の貧弱な柿の木の葉ももうほとんど落ちて、残りは数えるくらいとなっています。もうすぐいわゆる裸木となります。柿の実は1個ちゃんとくっついています。鳥用ですね。でも渋かったら鳥も食べませんので、熟すまで残っているかと思います。


(小魚の2枚の写真はきのうのものです。下水の排水口の水溜りにいました。)
いやはや驚きましたね、宮崎県の6人の惨殺事件にもびっくりしましたけど、アメリカの大量殺人事件には圧倒されてしまいました。変なところでさすがアメリカとそのスケールの大きさにたじろいだりして。
1970年から2005年の間に、何となんとナント90人の女性を殺害していたというのですから。いろいろ社会的に問題のあるような女性を狙っての犯行のようですが、それにしても90人とは、絶句です。

水道法の改正(改悪)について国会でもいろいろ動きがあるようです。きのうの続きで「堤未果 日本が売られる」のお知らせ・その2です。ひとつひとつがあまりに衝撃的で、うまくまとめることができません。だから重要な事実等を紹介していくより他はありません。
・水道民営化のスローガン;<民間企業のノウハウを活かし、効率の良い運合榮と安価な水道料金を!>
・21億人(世界人口の10人中3人)が安全な飲み水を手に入れられず、45億人(10人中6人)安全に管理されたトイレを使えないこの世界で、貧乏金持ちも関係なく、いつでもどこでも蛇口をひねれば、綺麗に浄水されたみずが24時間出てきて飲める恵まれた国はそう多くない(ユニセフ+WHO、2017年)。
・国土交通省が発表している水道水が飲める地域は、アジアでは日本とアラブ首長国連邦の2カ国のみ、その他はドイツ、オーストリア、アイルランド、スウェーデン(ストックホルムのみ)、アイスランド、フィンランド、ニュージーランド、オーストラリア(シドニーのみ)、クロアチア、スロベニア、南アフリカ、モザンビーク、レソトの15カ国(106ヵ国中)だ。
・公営から企業運営になった途端、水は「値札の付いた商品」になる。・・・。運営権を手に入れた民間企業がまず最初にやることは、料金の改定だ。世界の事例を見てみると、民営化後の水道料金は、ボリビアが2年で35%、南アフリカが4年で140%、オーストラリアが4年で200%、フランスは24年で265%、イギリスは25年で300%上昇している。
・フィリピンでは水企業群(仏スエズ社、米ベクテル社、英ユナイテッド・ユーティリティーズ社、三菱商事)によって、水道代が払えない人に市民が水を分けることも禁じられた。
ベクテル社に運営を委託したボリビアでは、採算の取れない貧困地区の水道管工事は一切行われず、月収の4分の1にもなる水道料金を払えない住民が井戸を掘ると、「水源が同じだから勝手にとるな」と、ベクテル社が井戸使用料を請求してくる。困った住民が水を求めて公園に行くと、先回りしたベクテル社が水飲み場の蛇口を使用禁止にし、最終手段で彼らがバケツに雨水を溜めると、今度は一杯ごとに数セント(数円)徴収するという徹底ぶりだった。
・世界中のどこでやっても、じゃぶじゃぶ儲かる水道ビジネスは、「開発経済学」の概念を全く新しいものに上書きしてゆく。開発とはもはや「そこに住む人々の生活向上と地域発展のため」ではなく、「貴重な資源に市場価値をつけ、それをいかに効率よく使うか」という投資家優先の考え方になっていった。
・世界銀行やアジア開発銀行、アフリカ開発銀行などの多国間開発銀行とIMFは、財政危機の途上国を「救済する」融資の条件に、必ず水道、電気、ガスなどの公共インフラ民営化を要求する。世界銀行の「民間開発戦略」の中心はあくまでも「投資家のための環境改善策」(民営化、競争、規制緩和、<企業の>所有権強化)であり、そちらの方がはるかに優先順位が上なのだ。
・現在瀬化の3大水企業は、水男爵と呼ばれる仏のヴェオリア社とスエズ社、英のテムズ・ウォーター社だが、世界水会議が3年に一度開催する「世界水フォーラム」には、彼らを筆頭に世界銀行やIMF,アジア開発銀行に大手グローバル水道企業、各種投資家などが集まり、いかに世界に水ビジネス市場を広げてゆくかを話し合う。2000年に行われた第二回世界水会議では、水道ビジネスにかかったコストは、全てその地域の消費者から回収すべきだとする「フルコスト・プライシング」という新ビジョンが打ち出された。
⇒水道などの公共部門で民営化を推進している内閣府民間資金等活用事業推進室で、水道サービス大手仏ヴェオリア社日本法人からの出向職員が勤務している (きょうのニュースから)
・多くの国際協定もまた、国境を越えた水ビジネスを精力的に推進している。例えばNAFTA(北米自由貿易協定)は締結国に対し、フェアな競争を維持するという名目で、商業用水源利用における国内企業優遇政策を禁止した。さらに3国間での大規模な水の輸出入によって環境被害が発生しても、企業側には輸出量削減や輸出停止などの措置は一切課されない。
・2018年の経産省のデータによると、2015年に84兆円だった世界の水ビジネス市場は、2020年には100兆円を超えると予測されている。
・PSIRU(公共サービス国際研究所)のデータによると、2000年から2015年の間に、世界37カ国235都市が、一度民営化した水道事業を、再び公営に戻している。主な理由は、①水道料金高騰、②財政の透明性欠如、③公営が民間企業を監督する難しさ、④劣悪な運営、⑤過度な人員削減によるサービス低下など。
・契約打ち切りで予定していた利益が得られなくなる企業側も、黙っていないからだ。・・・。再公営化のために一度結んだ契約を解除する際、得られるはずの利益を侵害したとして、企業側から訴えられるケースも少なくない。(数十億から百億円台の違約金や賠償金の例は略)
・巨額の賠償金を支払ってでも水道を公営に戻したいという国は後を絶たず、1990年代から本格化した水の民営化は、その後2000年代半ばをピークに減り始める。








































































 (トンボも数えるほど)
(トンボも数えるほど)

 (下流に飛びました。)
(下流に飛びました。)





































 (分流にサギがいてびっくりです。)
(分流にサギがいてびっくりです。)






















































 区役所にありました。
区役所にありました。



 これからの季節は温泉が最高です。
これからの季節は温泉が最高です。
 県北なら鳴子温泉でしょうか
県北なら鳴子温泉でしょうか
 (裏から)
(裏から)


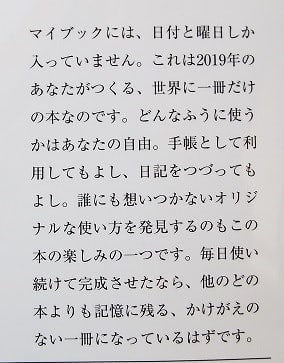















 体をきれいにしています。
体をきれいにしています。
 (南東)
(南東) (南)
(南) (西)
(西)




 (トンボの日向ぼっこ)
(トンボの日向ぼっこ)
 (逃げません)
(逃げません)









































