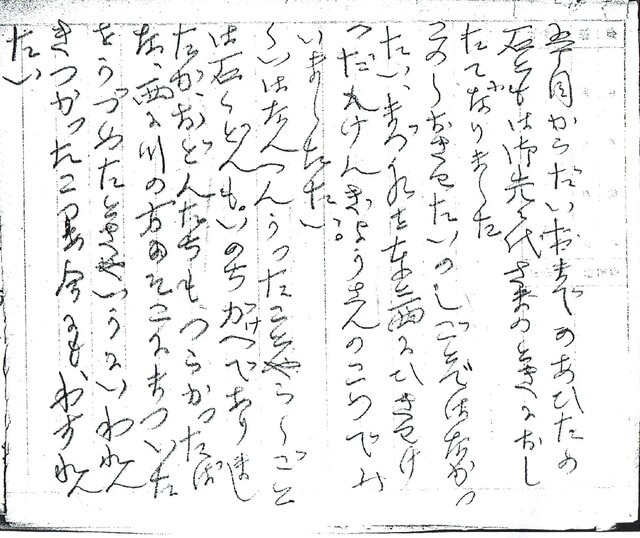慶長19年(1614)3月末、江戸城普請の惣奉行に長岡内膳が指名され人数を引き連れて江戸へ下っている。
慶長の頃の内膳家当主は忠興の長子・忠隆ののはずでこれは勘当の身であり話がおかしい。
「綿考輯録」をよくよく眺めてみると、これは有吉家4代目の興道のことであった。興道は元和4年(1618)36歳で死去しているから、19年当時は32歳の働き盛りであった。興道の「興」の字は拝領名である。武勇の士であり、忠興は愛娘・萬(後・烏丸光賢簾中)の婿にと考えて居たらしいが、なぜか興道はこれを断ったらしい。忠興の機嫌を損なわせたようだ。
石垣普請は知行壱万石に対し、45坪であったとされるから、細川家29万石では1,300坪(4,300㎡)という途方もないものであった。内膳(与太郎・興道)の働きぶりは秀忠公の称賛する処となり、御前に召し出されている。
内膳の居所が判る様にとの御意を以て、白熊茶筅の鑓を拝領して、これを有吉の丁場に押し立てた。
処で名城熊本城の普請に当たった穴太衆の内、百閒石垣を築いた原田茂兵衛なる者が、清正の勘気を蒙り浪人しているとの報をうけて、内膳の祖母・妙鏡尼(有吉立言室・立行生母)が、孫内膳の為にとこの者と対面して、100石を以て召し抱え江戸へ遣わしたとされる。加藤家では130石取りであったが、まずは100石で即断しのちに内膳の意をもって130石としたという。
妙鏡尼とは、忠興出陣の折に必勝を願って餅を差し上げたという有名な話が残る。細川家に於いては、戦場での働きについて由緒ある家には「御鏡頂戴の家」として定められ、例年餅を頂戴するが、その由来の許である。
有吉家には家司に葛西家がある。出京町に有吉家の屋敷があるが、これは表面上の事であり葛西家が住まい、出京町口の警護に当たったとされる。
大名並みの18,000石を知行する有吉家本家は、この内膳の死により弟・英貴が父武蔵の遺領を継ぐ形で相続したが、内膳の子が成人に至ると英貴女・梅をめあわせ嫡家を相続せしめた。貞之である。
英貴室は三渕好重女で細川三斎養女・古屋(霊樹院)だが、この人は豊臣秀頼女とも言われる人物であり、有吉家でも特別扱いされた人物であるという。
嫡家に対しその子孫は英貴家として別流がある。また、英貴の妹が戸田家に嫁いだが、その三男重時が有吉氏を名乗り明治に至っている。熊本城西大手門右手に屋敷があった。
本家は現・国立病院が建つあたりの高石垣上の広大な屋敷であった。