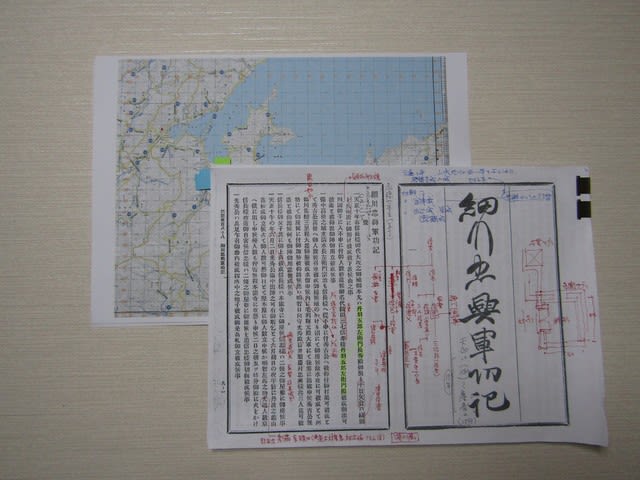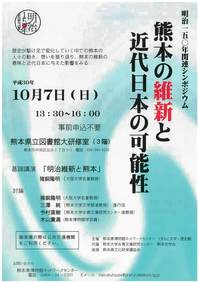八〇〇
覺
百姓之衣類、男女共木綿之外絹類ハ襟・帯・袖へりニも
用ひ不申、幷布も上方染用ひ不申様従前々被仰付置候處、
近年ハ猥敷不都合之衣類相用候様相聞、不届之至候間、
稠敷御吟味有之、彌以従前々被仰付置候通可有御申付候、
依之以來御停止之衣服着用之者は、其品ニ應夫々過料可
被仰付候條、急度其通可有御取計候、此方より差出候横
目役も令沙汰候事
寶暦二年正月
八〇一
下方風俗年々奢ヶ間敷相成、衣服之儀は別て心得違いた
し、間ニハ袴上下着いたし候者も有之由相聞、不都合之
至候、百姓衣類之儀ハ追々被仰付候通候得は、袴上下着
不仕筈之儀ハ勿論之儀ニ付、御紙面ニも相見申事ニ候、
以來急度相改、上下袴着不仕、常服之儀も被仰付置候通
彌堅相守候様御申付可有候、尤宿町別當共御上下之節為
御目見罷出候時分、上下着用致來候者共幷祭禮之節規式
懸候者共ハ、只今迄之通可有御申付候
但、前々より御免又ハ譯有之、袴上下着用致來候得共
ハ、此節御吟味候て相達被置ニて可有之候、已上
五月日 郡 方
八〇二
口ノヶ條書、元文年御達の通ニ〆奥書左之通
右は元文三年被及御沙汰候ヶ條ニて、委細其節の趣何そ
略儀無之候、右之節も被仰付置候條々寫置、一村限ニ村
庄屋居宅へ張置、常々無断絶相守候様被仰付候處、近年
いつとなく忽セニ相成候趣相聞、不届之至候、費ヶ間敷
儀有之候てハ自身/\之為ニも相成不申、且衰微之所よ
りハ上ノ御為ニも相成不申事ニ候條、随分萬事勘略仕手
輕相心得、専農業を出精仕御百姓取續候様可有御沙汰候、
畢竟御惣庄屋其外在役人共、先銘々より相慎、支配/\
を平生不致吟味所より、追々被仰付候趣其節限之様ニ相
心得、百姓共奢ニ長し不■ニ相成候、此以後急度相改、 ■扌偏に乄=締
御法度之趣彌相守風儀不亂様可有御沙汰候、尤右之條々
書寫村庄屋居宅へ張置、毎月御高札之面讀聞せ候節、一
同ニ惣百姓共へ申聞、奉得其意候との判形取置、月々御
惣庄屋へ差出可申候、左候て御惣庄屋より之書附御郡奉
行衆え相達候を、御郡方へ可被相達候、向後御横目役被
差出候事ニ候、不心得之者有之候ハヽ被差通間敷候、委
細ハ先年被仰付候通被相心得、可有御沙汰候事
寶暦二年二月廿三日
八〇三
衣服御制度
一士席以上衣服、裏付上下・羽織・袴等總て表は紬・木綿
を可被用事
但、裏は可為勝手次第、且又單羽織・袴ハ紗・綾・加
賀・日野之類勝手次第
一獨禮以下諸役人段以上衣服、羽織・袴等裏表共ニ總て布
木綿可被用事
但、下着幷單羽織ハ加賀・日野之類勝手次第
一足輕以下衣服、帯等ニ至迄總て布木綿可用事
一夏之衣服、冬之服ニ應質素可被相心得事
一獨禮以下、越後紬帷子・纑紋紗之羽織・絹平類之袴等被
禁候事
一火事羽織、革木綿可被用事
但、着座以上羅紗勝手次第
一雨羽織は總て木綿類可被用事
一陪臣知行取ハ士席ニ准、中小姓以下は獨禮以下二可准事
一商家は獨禮以下二可准事
一七十歳以上十歳以下幷醫師諸出家は制外之事
旅詰衣服
一羅紗、火事羽織・雨羽織
一羽二重縮緬
右着座以上勝手次第、其以下被禁候事
但、江戸御留守居ハ着座可准事
一紗綾、加賀・日野・丹後・郡内之類士席以上勝手次第
獨禮以下被禁候事
一獨禮以下諸役人段以上衣服、羽織・袴等表ハ都て紬木綿
過用事
但、裏幷單羽織ハ日野・加賀之類勝手次第
一足輕以下は旅詰たり共、萬ニ布木綿可用事
一陪臣知行取は士席ニ准、中小姓已下ハ獨禮以下二可准事
一於江戸御供被相勤候衆之内、御制度之服にて差支候面々
幷歩段以下御借羽織等ハ其節御制外被仰付筈之事
於御國婦人之衣服
一純子 一繻子 一綸子 一縮緬 一繻珎
右之衣服惣て被禁之候、此外異類之上品幷縫入御制禁之
事
但、士席以上之妻子純子・繻子類之事は勝手次第、且
また歩行之節は今迄之通木綿上着を可被用事
一獨禮以下之妻子幷家中之女、木綿之上着ニ帯を可用事
但、純子・繻子以上之帯被禁之、且又半下女ハ萬ニ布
木綿可用事
一陪臣知行取之妻子ハ士席之妻子ニ准、同中小姓已下之妻
子は獨禮以下之妻子と可准事
一商家之妻子は獨禮以下之妻子ニ可准事
但、農業之衣服は只今迄萬布木綿を用ひ候御制度ニ付
不被改
一武具・薬器之外、雑器ニ金銀被用間敷事
一金拵之刀脇差、獨禮以下被禁之事
但、焼付金幷萬ニ金紋等用申間敷事
一鼈甲・象牙・金銀之櫛笄、御國中御制禁之事
御國旅詰共衣服之表御制禁
一緞子 一繻子 一毛留 一綸子 一繻珎
右之外衣類之上品
但士席以上帯は勝手次第