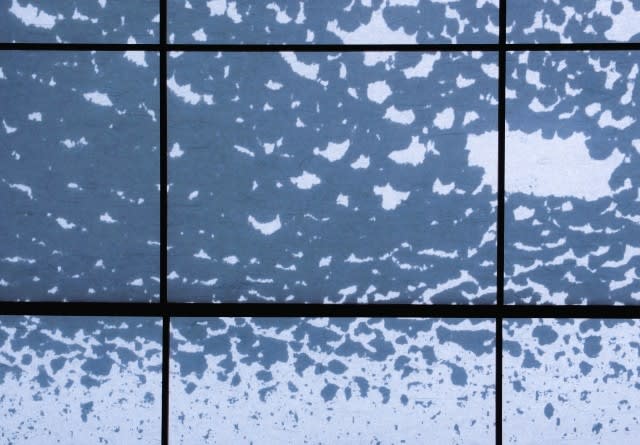小学生の頃の漫画月刊誌といえば、「少年画報」「まんが王」それに「冒険王」が思い出される。ここで「冒険」という語が使われたのは、読者対象の心を強く揺さぶると考えられたからだろう。昭和30年代後半から40年代、広い意味で冒険は未来だったとも言える。そして今、限られた者の強烈な光を指している。

読み応えのある一冊だった。対談と記事・解説のエッセイが集められていて、内容として重複する箇所も散見されるが、それでも著者たちの熱い思いが伝わってくる。角幡唯介の文章に惹かれ、昨年秋に古雑誌の記事に対する雑感を記したこともあった。今回、彼の活動のほぼ全貌を知ることができて、益々納得した。
彼は「初めから文章や本を書くことを前提に探検や冒険に出かけている」とずばり記している。登山や極地探検等それ自体も「表現」であることに違いないが、その「行動」を書き手としても真摯に見つめるという…そう記せば格好はいいが、実際は「行為と表現のジレンマ」を乗り越える葛藤は想像を超えるだろう。
全く縁のない「登山」。書籍などからなんとなく、目指す人は危険を伴う行為を乗り越えることによる「生の実感」が魅力だろうなと感じていた。表現の仕方は違うがそれに近いことも書かれている。しかし著者は登山ブームはもちろん、著名な探検家たちのアプローチについても、その行為の意義を徹底的に詰める。
それはいわば「生の燃焼度」を視ていると言ってもいい。予定調和化され、スポーツ化していく登山とは発想が違う。根本的には「自由」とは何かを問うているのだろう。文章だけで想像する世界だが、非常に魅力的に映る。この本に取り上げられた複数の書籍を買い求め読んでみようと思う。良き導き手に出逢えた。

読み応えのある一冊だった。対談と記事・解説のエッセイが集められていて、内容として重複する箇所も散見されるが、それでも著者たちの熱い思いが伝わってくる。角幡唯介の文章に惹かれ、昨年秋に古雑誌の記事に対する雑感を記したこともあった。今回、彼の活動のほぼ全貌を知ることができて、益々納得した。
彼は「初めから文章や本を書くことを前提に探検や冒険に出かけている」とずばり記している。登山や極地探検等それ自体も「表現」であることに違いないが、その「行動」を書き手としても真摯に見つめるという…そう記せば格好はいいが、実際は「行為と表現のジレンマ」を乗り越える葛藤は想像を超えるだろう。
全く縁のない「登山」。書籍などからなんとなく、目指す人は危険を伴う行為を乗り越えることによる「生の実感」が魅力だろうなと感じていた。表現の仕方は違うがそれに近いことも書かれている。しかし著者は登山ブームはもちろん、著名な探検家たちのアプローチについても、その行為の意義を徹底的に詰める。
それはいわば「生の燃焼度」を視ていると言ってもいい。予定調和化され、スポーツ化していく登山とは発想が違う。根本的には「自由」とは何かを問うているのだろう。文章だけで想像する世界だが、非常に魅力的に映る。この本に取り上げられた複数の書籍を買い求め読んでみようと思う。良き導き手に出逢えた。