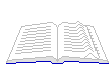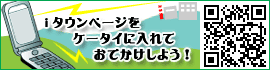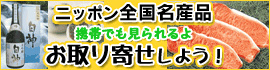| 竜馬がゆく〈3〉文藝春秋このアイテムの詳細を見る |
■【一口紹介】■
出版社/著者からの内容紹介
青春小説の名作が読みやすくなって再登場。
前半は、奥手だった幼年期から、剣術修行、脱藩、勝海舟との出会いと海軍塾設立までを描く
■内容(「BOOK」データベースより)■
浪人となった竜馬は、幕府の要職にある勝海舟と運命的な出会いをする。勝との触れ合いによって、かれはどの勤王の志士ともちがう独自の道を歩き始めた。
生麦事件など攘夷熱の高まる中で、竜馬は逆に日本は開国して、海外と交易しなければならない、とひそかに考える。
そのためにこそ幕府を倒さなければならないのだ、とも。
【読んだ理由】
司馬遼太郎作品・知人に奨められて。
【印象に残った一行】
『もっともこの日本観は、幕末だけでなく、すでに、それより三百年前の戦国初期、鹿児島に上陸した最初の宣教師、聖フランシスコ・ザビエルが、おなじ観察をしている。上陸後、すぐ耶蘇会に報告書を送り、「非キリスト教国のうちいまだに日本人にまさる国民を見ない。行儀よく温良である。が十四歳より双刀を帯び、侮辱、軽蔑に対しては一切容赦せぬ」とかき、また日本征服の野望のあったスペイン王に忠告し、「かれらはどんな強大な艦隊でも辟易せぬ。スペイン人をみなごろしにせねばやめないだろう。」幕末にきた外国勢力も、おなじ実感をもったわけである。』
『世の中の 人は何とも云はばいへ
わがなすことは われのみぞ知る
とは、父親の八平にさえ「ついに廃れ者になるか」と嘆ぜしめた竜馬の十代のころにつくった歌である。城下で低能児よばわりされた竜馬のさびしさが、歌にこもっている。』
『竜馬は、議論はしない。議論など重大なときにでないかぎり、してはならぬ、と自分にいいきかせている。もし議論に勝ったとせよ。相手の名誉をうばうだけのことである。通常、人間は議論に負けても自分の所論や生き方は変えぬものだし、負けたあと、持つのは、負けた恨みだけである。』
『大鵬丸のマストには、山内家の舟旗「三つ葉柏」がたかだかとひるがえっている。この三つ葉柏は別称土佐柏とよばれ、山内家の定紋で、のち、旧制高知高校(いま高知大学)の校章になった。
いや、三菱会社を興した岩崎弥太郎は、土佐藩の財産を初期の会社資産にしたため、この三つ葉柏をよりいっそう図案化して、三菱の社章にした。読者の家庭にある電気製品などにその紋がついておれば、かって土佐藩士が「柏章旗のもとに死なん」としたその山内家の家紋がもとである。』
【コメント】
読みやすく、読み出したら止められない面白さ。