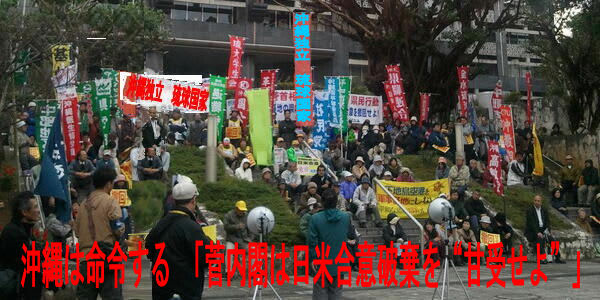
昨14日(2011年3月)夜になっても殆んどのテレビが孤立状態で避難生活を余儀なくされている被災者の食糧不足・水不足・暖房燃料、毛布等の暖房資材不足・医薬品不足等々を訴えていた。
いくつかの病院も患者用食糧がまもなく切れる、医薬品が不足しつつあると訴えていた。特に人命に直接関わるゆえに緊急を要する人工透析用の生理食塩水や酸素の不足、人工呼吸器などを動かすためのポータブル発電機、滅菌精製水、幼児のミルク等の不足の訴えもあった。
15日の朝になっても、NHKニュースは水や食糧が一度も届いていない場所があると言っていた。
3月11日午後2時46分頃の地震発生から3日以上経過していながら、この物資不足状況は政府支援の遅滞を示す有様なのだろうか。それとも様々な事情から回避不可能な止むを得ない事態なのだろうか。
菅首相が一昨日13日の夜8時前に国民向けのメッセージを発した。《首相官邸HPから》から冒頭発言の生活物資に関する言及部分のみを取上げてみる。
菅首相「地震発生から3日目の夜を迎えました。被災された皆さん方に心からのお見舞いを申し上げます。また、被災地を始め、国民の皆様には大変厳しい状況にある中で、冷静に行動をしていただいていることに対して、感謝と心からの敬意を表したいと、このように思います。
昨日に続いて今日一日、人命の救出に全力を挙げてまいりました。これまで自衛隊や警察、消防、海上保安庁あるいは外国からの支援も含めて、約1万2,000名の方を救うことができました。本日の救援体制を少し紹介いたしますと、自衛隊は陸海空で5万人が展開し、10万人体制を準備いたしております。また、警察官は全国から2,500名を超える皆さんが被災地に入っていただいております。消防、救急隊は1,100隊を超える隊が現地に入っております。さらに災害派遣医療チームも200を超えて現地にお入りいただいております。
食料、水、毛布などの搬送は陸路がかなり制約をされておりますので、空路、さらには海路も検討しておりますけれども、そうした搬送に力を入れております」――
「地震発生から3日目の夜を迎えました。被災された皆さん方に心からのお見舞いを申し上げます」云々。
生活必需品不足から空腹や寒さに耐えている被災者にとっては言葉のお見舞いよりも現に困窮している水・食糧・医薬品・暖房資材等の現物のお見舞いを願いたいと多くの被災者は確実に思ったに違いない。
被災者となった国民の衣食住困窮の原因が例え政治の責任ではないとしても、また物資支援の遅れが回避不可能な事態だったとしても、現に困窮している状況が存在する以上、「心からのお見舞い」よりも、「陸路がかなり制約をされて」いるという回避不可能な状況を具体的に説明して、支援が届かないことの謝罪から入るべきではなかったろうか。
だが、“陸路の制約”を言い、そのための空路・海路の検討を言うのみで、謝罪の欠けらも示さなかった。被災者の心労を心底思い遣るのではなく、「心からのお見舞い」が形式的な挨拶に過ぎなかったということだろう。
このことは“陸路の制約”が巨大災害につき物の既定事実だとする視点を存在させていないところに先ず現れている。その視点がないから、「空路、さらには海路も検討しております」といった検討段階とすることができる。
確かに米軍の協力を得て自衛隊の大型輸送ヘリコプターで物資の輸送等を行っているし、陸路でも自衛隊の輸送トラックが巡回して配布に努めているが、不足状況は収まらないまま現に推移している。
次に「昨日に続いて今日一日、人命の救出に全力を挙げてまいりました。これまで自衛隊や警察、消防、海上保安庁あるいは外国からの支援も含めて、約1万2,000名の方を救うことができました」の成果発言に「心からのお見舞い」が形式的な挨拶に過ぎないことが現れている。
「約1万2,000名の方」とはブルの屋上や建物内に孤立していた被災者の救出のことを言うのだろうが、必要な救出ではあっても、避難所で物資不足のまま避難生活を送っている被災者の命を心身共に十全な形で守ることも“命の救い”に入る国の重大な務めでもあるはずである。
後者の成果を示すことができる状況を生み出し得ないままに、このことを抜きに孤立被災者救出の成果のみを具体的な人数を挙げてさもたいしたことを成したように言う。「心からのお見舞い」が形式的な挨拶でなければ言えない「約1万2,000名の方を救うことができました」の片手落ちとなる成果誇示であろう。
“陸路の制約”が巨大災害につき物の既定事実だと書いた。当然、道路の寸断、渋滞等は物資支援遅滞の理由にはならない。海路輸送は余震による津波の危険性から遅れるとしても、なぜ最初から空路輸送を選択しなかったのだろうか。自衛隊の輸送トラックで通行可能な道路を探しながら進むよりも自衛隊の大型輸送ヘリコプターで孤立被災者の救出と併行させて物資輸送を行い、孤立避難場所に投下する方法を採ったなら、迅速な不足解消に役立ったはずだ。
殆んどのテレビ局が孤立地帯に入って、被災者の不足を代弁している。首相官邸に設置した災害対策本部はどこの孤立地域に何人が避難生活を送り、何がどのくらい不足だと報告の提供を求めているのだろうか。またテレビ局も自らが得た非難状況を役立つ情報として首相官邸に報告しているのだろうか。
こういったことの情報収集によって、ヘリコプターを飛ばして、目的地の庭や空きの上空にホバーリング状態にして必要物資をロープで吊るし降ろすことをしたら、必要量に応じた的確な配布ができたはずだ。
だが、今までテレビが放送する場面からそういった光景を見ることはない。
政府は14日になってヘリコプターからの食糧投下を計画したという。計画から本格的実施までに時間を要することになる。15日の今日中に実現するのだろうか。
《食糧、毛布など搬送急ぐ 孤立地には食糧投下》
(サーチナニュース/2011/03/14(月) 17:14 )
14日、政府は緊急災害対策本部を開催。14日午前8時半現在の要緊急物資調達状況を発表。
〈宮城、岩手、福島の物資受け入れ拠点施設への搬送を急いでいる。〉
〈現地で孤立している住民らに対してはヘリコプターから食糧投下をして提供する手立てを始めた。〉
孤立避難住民からのからの〈食糧・食料品(パン、おにぎり、即席ラーメン、ビスケットなど)213万4776個のうち、62万142個は輸送中、または配布拠点施設に配達済み。〉
〈50万4000個は輸送業者を手配中〉
〈110万4634個は入手先を手配中〉――
これは〈必要な量の半分については手配が急がれている状況〉だと記事は書いている。
〈飲料水については要望のあった93万7258本〉は調達済み、輸送業者を手配中。
〈寒さをしのぐ毛布29万7187枚、おむつ1万枚など要望数を確保。〉
〈トイレについては3821基の要望に対し、1721基は入手先を手配中。〉
輸送中と輸送業者を手配中はトラック輸送のことを言うのだろう。どちらも時間がかかる。後者はより時間を要することになる。なぜ在日米軍にも依頼して、自衛隊の大型輸送ヘリコプター共々フル稼働させて、物資集積場所から直接ヘリコプターを飛ばして投下を選択しないのだろうか。
不足物資の入手先を手配中となると、なおさら遅れることになる。各地方自治体は防災対策としてレトルトご飯や乾パンの缶詰等の非常食、簡易トイレ、その他の備蓄を行っているはずである。自治体の人口に応じて、かなりの量となるはずだ。自治体の中には賞味期限が近づくと、防災訓練の日などに炊き出し訓練の一環として住民に放出したりする。
政府が後刻弁償の約束で各自治体に備蓄品の放出を求めたといったニュースは聞かない。県や市などの自治体が独自に提供を決め、独自に輸送するといった記事は存在する。だが、こういった動きにも関わらず、取り掛かったばかりといった事情といったこともあるのだろう、生活物資の飢渇状態は依然続いている。
政府自らが被害状況を知った時点で備蓄品の放出を求め、トラック輸送に頼らずにヘリコプター輸送、ヘリコプター投下を実施してこそ、迅速な入手、迅速な配布の経緯を辿ることとなって、菅首相が言っていた「命を救うことを最優先する」の言葉が実体を持つことになる。
だが、そういった実体を持たせもせずに、国民向けメッセージの締め括りで、「果たしてこの危機を私たち日本人が乗り越えていくことができるかどうか、それが一人ひとりすべての日本人に問われていると、このように思います。私たち日本人は、過去においても厳しい状況を乗り越えて、今日の平和で繁栄した社会をつくり上げてまいりました。今回のこの大地震と津波に対しても、私は必ずや国民の皆さんが力を合わせることで、この危機を乗り越えていくことができる、このように確信をいたしております」と、日本人の誇り、日本人の勤勉さに訴えたとしても、訴えている本人の人間的胡散臭さしか発散しないことになる。
今日3月15日(2011年)朝、菅首相が統合対策本部を設置したことについてツイッターに投稿した。
政府と東電が統合対策本部へ http://nhk.jp/N3ui69pV 菅首相、東電側の情報の不正確・遅滞・混乱の問題に過ぎないのに自身のアイデアで「事業者である東電と政府の対策本部がリアルタイムで対応するためには両者を一体化した方がいい」と東電本店に本部設置、そこに詰めるという。 約3時間前 webから
いくら何々チームだ、何々会合だ、何々本部だの立ち上げオタクだとしても、「この危機を乗り越えるための陣頭指揮に立ってやり抜きたい」の決意表明に関係なく東電本社に詰めて問題となっている原発の事故解決に有効なアイデア提供の一体化を担えるわけではない。事故解決そのものは東電の役目。 約3時間前 webから
東電側の情報がいくら正確になった、迅速になったと情報の正常化を果たしたとしても、原子炉自体の機能が正常化を果たさないことには無意味。菅首相自身が後者に役立たなければ、本部を立ち上げたことも詰めることも無意味。理解できない菅首相の存在自体も無意味。バカな男だ。 約3時間前 webから
東電の今日午前9時前の記者会見。長テーブルの前に横一列に並び立ち、一斉に頭(こうべ)を垂れる日本式謝罪から入った。これは最早謝罪以外に逃げ場を失ったときの儀式。かなり追いつめられている証拠。 約1時間前 webから
合理的判断能力を持ち合わせていないことから指導力を欠き、このことが致命的となって、いくら言葉を尽くそうと、すべてに亘って今ある実態とかけ離れることになる。にも関わらず、市民活動家当時からのお得意の言葉でどうにか自分を持たせようとしている。
持たせれば持たす程始末に悪いことになるが、本人は何一つ気づいていないのだから、最悪の始末の悪さということになる。
|