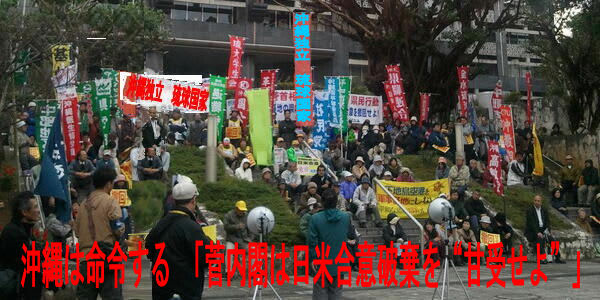
14メートル、あるいはそれ以上の高さに達した場所もあるという今回の大津波では地域の指定避難場所に逃れたものの津波が押し寄せ、2階にまで達した、あるいは津波に建物ごと流されて犠牲となった等の報道を目にする。普段の防災訓練で避難場所として利用していて、避難場所はそこだと固定観念としていた無理もない行動性がまさかの悲劇に襲われることになった。
昨3月26日(2011日)の、と言っても22時48分発信のネット記事「47NEWS」――《大津波、2年前に危険指摘 東電、想定に入れず被災》が、調査した平安時代前期869年の貞観(じょうがん)津波の痕跡から東電に対して大津波の危険性を指摘していたと報じている。
指摘したのは独立行政法人「産業技術総合研究所」岡村行信活断層・地震研究センター長だそうだが、869年というと1142年前となる。
「Wikipedia」には、地震規模は推定8.3以上。〈津波堆積物調査から岩手県沖 - 福島県沖、または茨城県沖まで震源域が及んだ連動型超巨大地震の可能性が指摘されている。〉と書いてある。
指摘は2009年の審議会。他のネット記事によると、この審議会というのは電力会社が実施した「耐震性再評価の中間報告書案を検討する審議会」(毎日jp)だそうだ。なぜ「耐震性再評価中間報告書案検討審議会」と名付けなかったのだろうか。記事の方で「耐震性再評価中間報告書案検討審議会」と名付けてあるものをわざわざ「耐震性再評価の中間報告書案を検討する審議会」と言い替えるはずはないから、天下っている元役人が勿体振ってわざと長たらしい上になおさら長たらしい名前にしたのかもしれない。
大津波指摘に対して、〈東電側は「十分な情報がない」として地震想定の引き上げに難色を示し、設計上は耐震性に余裕があると主張。津波想定は先送りされ、地震想定も変更されなかった。この時点で非常用電源など設備を改修していれば原発事故は防げた可能性があり、東電の主張を是認した国の姿勢も厳しく問われそうだ。〉と記事は書いている。
岡村研究センター長「原発の安全性は十分な余裕を持つべきだ。不確定な部分は考慮しないという姿勢はおかしい」
記事は、〈06年改定の国の原発耐震指針は、極めてまれに起こる大津波に耐えられるよう求めるなど大幅に内容を改めた。東電は、新指針に基づき福島第1原発の耐震設計の目安となる基準地震動を引き上げると経済産業省原子力安全・保安院に報告。保安院は総合資源エネルギー調査会の原子力安全・保安部会で研究者らに内容の検討を求めた。〉と書いているが、その報告があったのか、未だ検討中なのかまでは記事は書いていない。
但し東電側は津波に関して「十分な情報がない」という姿勢だったのだから、地震震度に対する耐震性に重点を置いた対策だったのだろう。
記事は最後に次のように解説している。
〈委員の岡村氏らは04年ごろから、宮城県などで過去の津波が残した地中の土砂を調査。貞観地震の津波が、少なくとも宮城県石巻市から福島第1原発近くの福島県浪江町まで分布していることを確認した。海岸から土砂が最大で内陸3~4キロまで入り込んでいた。
貞観津波についての研究は1990年代から東北大などが実施。岡村氏らの研究チームは、津波を伴う地震が500~1000年間隔で発生してきたとしているが、震源断層の規模や形状、繰り返し期間をめぐっては研究者間でも異論がある。〉――
要するに東電側は今回の津波の高さ・強さを想定外としているが、実際は2009年に指摘を受けていた時点で既に“想定外”としていて、今回津波を受けて後の祭りとなった“想定外”だったことになる。
あくまでもその意味での「想定外」でなければならない。
貞観津波の指摘は東電に対してだけではなく、一般にも伝えられていたことを、《“避難所変更を”署名実らず》(NHK/2011年3月26日 23時4分)に見ることができる。
仙台市若林区六郷地区では海岸から2キロ余り離れた地区の小学校が「津波が達しない場所」として指定避難場所となっていた。だが、1000年以上前に、と書いてあるから、貞観津波のことだろう、この地域一帯にも津波が及んだ形跡があるという最新の研究結果を基に専門家と勉強会を開き、この専門家というのが上記「47NEWS」記事が紹介している独立行政法人「産業技術総合研究所」岡村行信活断層・地震研究センター長なのかどうかまでは書いてないが、指定避難場所を海岸から2キロ余り離れた地区の小学校から盛土上に通した仙台東部道路への変更を仙台市に求め、去年4月には「仙台東部道路に登るための梯子(はしご)を設置してほしい」と1万5000人分の署名を提出したという。
だが、この要望が生かされる前に今回の地震と津波が発生。指定避難場所だった2階建ての小学校は2階まで浸水、1階や校庭に避難した人たちは津波に流されてしまったと、避難した人の話として伝えている。
指定避難場所を小学校から仙台東部道路に変更を求める活動をしていた住民は最初から小学校は危険と考えて、仙台東部道路に逃げて助かったという。その一人の大友文男氏(78)の話を伝えている
大友文男氏「私たちの呼びかけが広がっていれば、もっと多くの人が救えたはずで、残念だ」
勉強会を開いていた専門家かどうかは分からないが、東北大学の今村文彦教授の発言も伝えている。
今村教授「今回の津波を教訓に、避難場所の指定を見直していくことになるだろう」
だが、教訓の代償は余りにも大きく、残酷である。
1万5000人分の署名を仙台市に出したのは去年4月。少なくとも10ヶ月は経過している。記事は、〈この要望が生かされる前に津波は起きてしまい〉と書いているから、仙台市は承諾・却下のいずれの決定もしていなかったことを示している。検討中だったのか、放置していたのかどちらかということになるが、10ヶ月も検討中ということはないだろうから、放置され、忘れられていた可能性がある。
実際のところはどうだったのかの検証が必要となる。もし役所の習いとして放置していたなら、人命を間接的に奪った責任を問わなければならない。
テレビで被災者が、また戻ってきて家を建て、街が復興したとしても、津波が再度襲ってきたら何もならないことになると絶望的な顔で話していた。それ程にも衝撃的な津波の来襲であり、津波一過の無残な災害の爪跡ということに違いない。
いくら耐震に気を使って家を建てても、津波が簡単に持っていってしまう。例えコンクリートで頑丈な家を建てても、津波が窓のガラスを一旦破ったなら、そこから浸水して、あっという間に2階、3階にまで達することになりかねない。窓ガラスという窓ガラスを防弾ガラス並みの強度に保たなければ、安心できないことになる。
問題は資金ということになる。政府がすべての家庭に補助金を出して、そういったちょっとした城のような頑丈な家を建てて地震と津波の備えとするのか。
この方法による補助金の範囲は今回の被害地域のみにとどまらず、首都直下型地震や東海地震、南海地震、その他の予想される地震域すべての家庭に給付しなければならないことになって、自ずと国家予算との兼ね合いの問題が生じる。
そこまで補助金が出せないということなら、別の方法を津波の備えとしなければならない。
一つは指定避難所の建物を津波の高さと勢いに耐え得る高さと強度を持った建造物とする方法がある。《「安全地帯を二重三重に」釜石市長、津波に耐える避難所必要》(MSN産経/011.3.22 12:38)がその覚悟を持った岩手県釜石市野田武則市長の発言を伝えている。
3月22日、自衛隊のヘリコプターで空から市内を視察後、記者団に語っている。
野田釜石市長「安全地域を二重三重に組み立てる仕組みを作りたい」
記事は、〈具体的には、防潮堤を越える津波に対処できる避難場所の確保などを挙げた。〉と書いている。
「安全地域を二重三重に組み立てる仕組み」という発言と今回の津波の高さから解釈できるイメージは指定避難場所とする建物を鉄筋コンクリートの4階、5階の高さとし、その周りに15メートル程の高さの、どんな津波にも耐えうる分厚い塀を360度隙間なくめぐらして、出入口を鉄製の小さな扉として、そこから出入りするといった構造が浮かんでくる。
私自身が考えているのは街づくりを通して大地震・大津波が来ても住民が助かる工夫である。但し街づくりに関しては素人だから、効果的かどうかは分からないし、また既に誰かが出しているアイデアかもしれない。そうであったなえら、ご容赦願いたい。
かなり以前から、地方の小都市は国鉄(現在のJR)の駅を中心に街は発展し、中には駅前のみ商店街らしい光景が現出するだけで、駅前から一歩街中に足を踏み入れると閑散とした風景が広がるといった小都市もかなりあるが、そういった小都市も含めて、駅前にはその街のメインストリートというものがあるだろうから、駅前の四つ角に土地代がゼロの交差点を吹き抜けにした四足の高層ビルを建て、そこに喫茶店から書店から金物屋からスーパーから、すべての商店、映画館がるなら映画館、美術館があるなら美術館、図書館があるなら図書館、そして各種事務所や交番までをビルに街を入れる発想で纏めて入れた、街の機能を持たせたビルを建て、ビルの周囲の土地を美しい公園とすることを考えていた。
この考えの一端を2009年10月8日の当ブログ記事――《八ッ場ダム、生活の発展的原状回復で国の中止に妥協してはどうか - 『ニッポン情報解読』by手代木恕之》と2008年2月21日エントリーの《地方自治体病院赤字脱却はPFI方式による商業・住居施設併設の複合施設化から - 『ニッポン情報解読』by手代木恕之》に取り入れている。
前者の内容は前原誠司が国交相時代、就任早々八ッ場ダム建設中止を表明。対して関係知事や地元住民が強硬に反対した。そこで住民に対する呼びかけとして、届かないことは分かっていたが、温泉宿を一軒の大きな建物に纏めて、ジムナジウムや卓球ルームやバトミントンルーム、室内テニスルーム、室内ミニバスケットルームを併設し、建物外は広々とした公園として、公園の中にハーフゴルフ場、室外テニスコート、高齢者用のゲートボール場を設けて活気を呼び込むことで国の中止に賛成してはどうかといったものである。
広い公園を設け、公園の中にハーフゴルフ場、室外テニスコート、高齢者用のゲートボール場を設置する敷地の確保は80年代には22軒あった旅館が現在残っている7軒を一つの建物の中に纏めることによって可能となる。
後者の内容は赤字経営に悩む公立病院を高層ビル化し、そこにスーパーやコンビニ、百円ショップ、小さな映画館、書店、喫茶店、ラーメンショップ等、客数が多く望める店を対象にテナントとして募集・入店させ、上層階は一部を賃貸マンションとして、そのテナント料と部屋賃貸料から病院の赤字を補填して病院経営を成り立たせてはどうかというものである。
記事の中に、〈マンションの一部賃貸部分はワンルームとし、独身の看護師や医者を対象に安く賃貸する。彼らは独身であるゆえに階下の商業施設を出会いの場とする恋愛や結婚を目的とした一般の若い男女を集める魅惑的な誘蛾灯となってくれるだろう。中には一緒のマンションに住みたいと一部屋買う男女も出てくるかもしれない。〉と悪いことまで書いた。
このメインストリートの広い道路の交差点上に四足ビルを建てるという発想はフランスの凱旋門から思いついた。凱旋門は一本の道路を跨いで建ててあるが、四足ビルは東西南北の二本の道路を四つ角で跨ぐ形を取る。
だが、2010年10月3日の「47NEWS」記事――《国交省、道路空間を民間に開放 有効活用で収益還元》(2010/10/03 15:47 【共同通信】)が、国土交通省が道路の高架下や上空スペース(道路空間)の利用制限を緩和し、民間に広く開放する方針を決めたこと、路空間活用事業企画を6月下旬から7月末に募集したこと、それに対して道路をまたぐ商業ビル建設のほか、道路の高架下への物産店開設、高架側面を利用した太陽光発電など計166件の提案が寄せられたこと、歩道上のオープンカフェや、広告付きの案内看板の設置、レンタサイクル用の自転車置き場開設などの提案もあったと伝えたことから、そこで素人の出る幕はなくなった。
記事は最後に、〈道路空間の利用は道路法などで制限されているが、国交省の成長戦略会議は5月、「財政出動を伴わない成長戦略」として道路空間のオープン化を打ち出していた。〉と解説している。
私自身の考える「大地震・大津波が来ても住民が助かる街づくり」とは海岸線近くの地域に住民が地震発生から指定避難場所まで余裕を持って逃げることができる距離に15~20メートルの高さの津波が襲ってきても破壊されない鉄筋コンクリートの縦長の10階建て程度のビルを建て、そこにいくつかの事務所や商業店舗を入れて複合ビルとし、ちょっとした街の機能を機能を持たせる。
昇降にはエレベーターは地震が発生して電気が止まると使えなくなるから、エレベーターは設置せずに、例え場所を取ることになったとしても、一度に大勢の人間が扱ってもいいように一般よりも幅の広いエスカレーターを設置。地震で停止したとしても、階段として使用可能となる。
勿論、カネと場所の余裕があるなら、エレベーターを設けてもいいことになる。
欲を言えば、建物の四方にエスカレーターを設置したなら、それだけ早く階上に逃げ込むことが可能となる。一つしか設置できない場合はエスカレーターの乗り場を探しているようでは逃げ遅れる危険性が生じるから、建物の正面内部真正面背後のすぐと分かる場所に設ける必要がある。
ビルの出入口は東西南北、四方に取り、どこから逃げてきても最短でビルの中に逃げ込むことができるようにする。出入口を四方に取り、エスカレーターも四方の出入口に合わせてそれぞれ真正面に4箇所のエスカレーターが設置可能なら、エスカレーター上り口に到達できる時間をより短くすることができる。
勿論、エスカレーターは停止していることを予想して、上っていかなければならないが、幼い子どもや高齢者は大人が助けて登っていく必要がある。
津波は地震発生後30分程で襲ってきたとされているが、〈津波の第1波の到達は地震発生から15~20分との見方もある〉(asahi.com)ということだが、その地域に住むすべての住民が10分以内に逃げることができる場所に、そこに郵便局があるなら、郵便局をベースに銀行や病院、その他の施設、消防署でも警察署でも、何でもいいから複合施設として纏めて、縦長の10階程度のビルを建て、上記と同じように指定避難場所としての設備を備えるようにする。
教育機関も同じように保育園・幼稚園、小学校、中学校、英会話教室、ピアノ教室、あるいは介護施設等々、集めることができる施設、経営体を集めて、縦長のビルに纏めて、指定避難場所とする。現在あるような横長の2階建て、3階建ての建物は津波が予想される地域では一切廃止する。勿論、予想地域は万が一を考えて大きく取る必要がある。
幼児から中学生まで普段から階段を使う習慣をつけけたなら、車社会によって落ちているとされる運動能力回復に役立つかもしれない。
もし自家発電装置が必要なら、地下に設けて、潜水艦の内部のようにハッチを閉めると海水が浸水しないような仕様の扉を設けて防水とするか、最上階に設ける。
ノッポのビルを建て、外装の色を統一したなら、他処から来た人間も地震・津波の際の指定避難場所とすぐに判断できるのではないだろうか。
この方式は家を守ることよりも人の命を守ることに重点を置いた対策だが、役に立たないアイディアであったり、既に誰かが提案していたなら、再度悪しからずご容赦を。
|