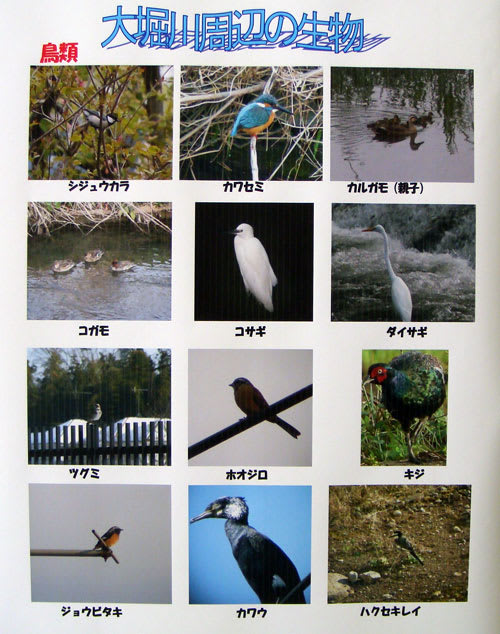|
造成地の裏で沢山のアメリカイヌホウズキが花を付け実を結び始めていた。 |
|
散歩の途中で、民家の塀に、鮮やかな黄色のランタナが咲いていた。 |
|
↓ 鮮やかな黄色のランタナの花。葉は斑入りで美しい。 | |
 | |
 | |
 | |
|
・和名はシチヘンゲ(七変化)。赤、橙、黄、白など鮮やかな色の花をつけ、また花の色が次第に変化することに由来する。 ・乾燥、荒れ地にも栽培可能。 ・花後の茎は切り戻すと新梢を伸ばして再び花を咲かせる。 |
|
造成地の日当たりの良い場所にハハコグサ(母子草)が咲いていた。 |
|
江戸川大学文化祭実行委員会から、今年も近隣住民に招待状が届いた。 |
|
サルビアレウカンサ(アメジストセージ・メキシカンブッシュセージ)の花が、 |
|
↓ 見事に咲いたサルビアレウカンサ。 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
|
・多年草。 ・丈夫で育てやすく,大株になるので、植え付ける場所はよく考え,十分な 間隔をとっておく。 |
|
散歩の途中の民家にある大きなシシユズ(獅子柚子)の実が色づき始めた。 |
|
↓ 大きなシシユズ、人の顔と比較。 | |
 | |
|
↓ 色づき始めた大きなシシユズ。 | |
 | |
 | |
|
↓ ミカン・リンゴ・バナナと比較。 | |
 | |
|
|
|
大堀川遊歩道に、アカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)の花が咲いていた。 |
|
↓ アカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)は | |
 | |
 | |
 |
 |
|
| |
|
大堀川荒れ地のイシミカワ(石見皮)に果実が実り、茎が紅葉してきた。 |
|
↓ イシミカワ(石見皮)の茎が真っ赤になって美しい。 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
|
|