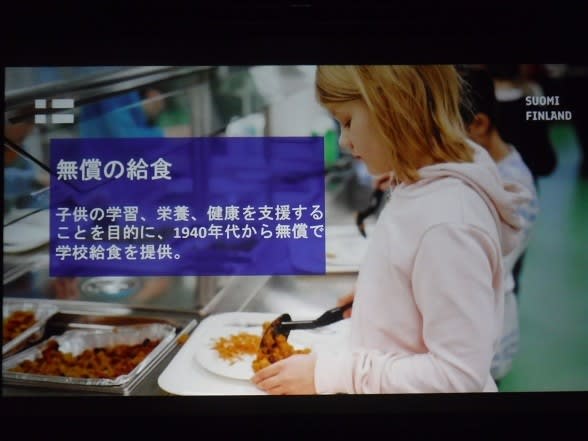講師は「縄文人の高い精神性が世界に評価された」と胸を張った。昨年度、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録にあたり、その中心の一人とした活躍された講師のお話を聴いた。
昨日(6月9日)、石狩市の花川北コミュニティーセンターにおいて「いしかり市民カレッジ」の講座が開催された参加した。実はこの講座は6月7日に行われた縄文遺跡群の現地見学の前に行われる予定だった事前講座が、講師の都合で事後に行われることになった講座だった。
講師は北海道の縄文世界遺産推進室特別研究員の阿部千春氏で「縄文遺跡群は世界遺産としてどのような価値があるのか」と題して講演された。
阿部氏はまず、縄文文化の特色について触れられた。縄文文化とは、「日本列島に多様な自然環境のなかで、漁労・狩猟・採集を生業として定住生活を実現し、1万年以上も大きな争いもなく存続した先史文化である」とされた。他の文明が農耕を主とすることによって定住生活を実現させたのに対して、古の日本では多様な生物に恵まれたこともあり、世界にも類を見ない形で定住生活を実現させたということが言えるようだ。

※ 講演をされた阿部千春氏です。
縄文文化の特徴の一つとして「土偶」の存在がある。この「土偶」は縄文時代の始まりから終焉に至るまで作り続けられ、そのほとんどが壊れた状態で出土しているということだ。さらに「土偶」は潜在的に母性を持った女性像として作られているものが多いという。このことは、土偶づくりは「生」を、それを破壊することは「死」を意味していると阿部氏はいう。さらにそれらは「再生」すると縄文人は信じていたところがあるという。
阿部氏が興味深いお話を披露してくれた。阿部氏が直接発掘に関わった茅部町(現在の函館市)で「中空土偶」が発見されたが、それをMRIで透視したところ内部は見事な空洞だったことが判明したそうだ。その際に画像を子細に見たところ、身体の各部が離れやすいような構造となっていることが分かったという。このことは、土偶が破壊されやすいように、そしてまた再生しやすいようにという縄文人の思いなのではないかということだった。

※ 一躍有名となった中空土偶です。(愛称:カックウくんです)
また、発掘された土器や装飾品からも縄文人の思考が読み取れるという。例えば土器には赤い土器と黒い土器があるそうだ。また、装飾品の一つであるヒスイには白い地の中に碧い斑状のものが広がっているという。あるいは、男性と女性、偶数と奇数、というように縄文人は「二項原理」を意識し、その二項を対立させるのではなく、「二項融合」という考え方をしていたという。言葉を変えていえば、縄文人は全てを受け入れる思考法だったのではないかと思えるのだ。
現地見学の際の投稿でも触れたが、縄文人が遺した貝塚は単なるゴミ捨て場ではなく祭祀場として人だけではなく生きとし生けるものを祀る場であったことが判明している。いや生きとし生けるものだけではなく、縄文人の命を繋いだ生活の道具まで祀ることをしていた可能性があることが分かっている。こうした縄文人のサスティナブル(持続可能性)な考え方が、効率を求め過ぎた現代とリンクしたことが世界遺産登録を後押しした可能性があったと阿部氏は言及した。そして縄文遺跡群が世界遺産に登録されたことにあたって特徴的なことは、何か特異な建造物や、だれか偉人が成し遂げたようなことではなく、ごく一般の人たち(縄文人)が形づくり、遺してきた文化だったという点で特徴があるという点である。

※ 講座の様子を一枚撮りました。
私は毎週日曜日のTBS系の「世界遺産」は私の大好きな番組であり、録画して欠かさず視聴している。その「世界遺産」に取り上げられるには絵的に非常に地味で訴求力にかけるかな?と思われるが、逆にそのことが「北海道・北東北の縄文遺跡群」が注目を浴びるキッカケとなるかもしれない。縄文文化……、深いなぁ。ますます嵌まるかもしれない…。