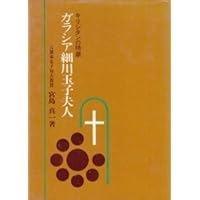一領一疋の佐田家の先祖附(佐田才助)を興味深く読んでいる。
このお宅の遠祖は、楠木正成から「坂東一の弓取り」と賞されたという宇都宮治部大輔公綱であり、祖はその十二代の後胤・勘右衛門なる人物だという。長曾我部盛親に仕え、佐田庄を賜ったので佐田姓にしたという。長曾我部家の没落と共に肥後に下り、加藤清正に仕え(200石)たが忠広改易に伴い浪人した。細川忠利公の熊本入国に伴い、かっての朋輩・立石助兵衛や小崎太郎左衛門を頼み、宇土郡中村の石打という処に永荒地を拝領して居住したという。
立石助兵衛もかっては長曾我部家家臣であり、「長元記(長曾我部元親記)」を残した人物として知られるが、ここでいう「かつて」という関係は共に長曾我部家臣だという事であろう。
一方小崎太郎左衛門との関係は、細川家家臣としてのものであろう。
小崎家に関しては御当代のご子息(教師・当時アメリカ留学中)から、先祖探しの依頼を受けて色々調べたことが有り、現在もご厚誼をいただいている。
小崎家は旧姓岡部氏で、祖とする兵次郎長豊(太郎左衛門)は、細川幽齋公の田辺城籠城に当たり密使・中津海五郎右衛門を手引きするなどの功により、後忠興より感状を受け、五百石拝領した。
実は私はご子息のお誘いにより、ご当代(夫君)のお宅を訪ねたことがある。
旧家らしくいろいろ古いものが残っており、御先祖様や雇人のお墓などが屋敷の近くに在った。
その場所が、佐田甚右衛門が入ったとされる宇土郡中村であり、石打ダムが間近にある。
三角半島の山中と言ってもよい。
佐田家はこの荒地に入り、その御赦免開地は二町五反八畝余となり、三代に亘りこの地に居住したが、享保三年に至り一領一疋に仰せ付けられ、後「飽託郡正院手永(現熊本市植木町)」の惣庄屋を仰せつけられこの地を離れている。
後、中村の地は小崎氏が納めて居られるが、小崎氏と佐田氏のかっての縁により、小崎家が跡を継がれたのであろう。
このような史料に出会うと、思いがけない色々なつながりが見えてくる。だからこそ史料散策がやめられなくなる。