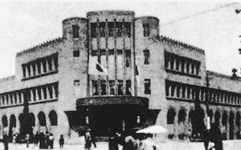
昭和4年に建設された熊本市公会堂
以前■洗馬川(坪井川)沿いを電車が走るで書いたが、熊本市電の開通は大正13年の8月1日である。
種田山頭火が泥酔して市電を止めたという話は有名な話として残されているが、はっきりした日時は判らないが「大正13年の夏」だとされる。つまり山頭火は開通早々の電車を止めたという事になる。
この事実が知られるようになったのは、昭和26年11月山頭火に関する座談会が催された際、元妻のサキノが発言したことによる。
木庭某なる人物が山頭火を助けて報恩寺につれて行った。その人物が特定されたのは平成18年に到り、同姓の木庭實治氏(熊本史談会会員)によってである。
そしてその場所は、現在の熊本市民会館がある辺り、かっての熊本市公会堂の前あたりだと言われている。
この表現はサキノの発言によるものだろうが正解とは言えない。事件当時熊本市役所がかろうじて建設されてはいるが、上の写真の熊本市公会堂はまだ建設されてはないから、「後に建設された熊本市公会堂の前あたり」としなければならないのだろう。
そんな場所に当時はどんな建物が建っていたのだろうか、またこれを調べてみたいという思いが沸々としてきた。
追記:05/06
上記写真の熊本市公会堂が出来る前にはドーム付きの木造の公会堂+日本館がありました。
左の建物は移築され日本館は昭和42年迄現存したと言いますが、私には記憶がありません。
















