忠興文書-元和三年(1617年)
134、正月晦日書状
・秀忠ヨリ鷹ヲ拝領ス
・忠利ヨリ早馬ヲ贈ラル
・不干(佐久間正勝)仕合無残所、八木・屋敷等被遣候事
・忠興二月二日江戸出立ノ予定
・秀忠ヨリ道中ノ鷹狩ヲ許サル
135、二月十八日書状
・十七日吉田ニ到着ス
・秀忠ノ上洛ハ六月ニ定マル
136、三月十六日書状
・忠利ヨリ栗毛馬ヲ譲リ受ル
137、四月十八日書状
・幽齋所持ノ萬代和歌集ヲ烏丸光賢ニ贈リタシ (長岡孝之所ゟ忠利所へ在之)
日本唯一ノ珍書
138、七月十九日書状
・本多忠政父子三人伊勢桑名ヨリ姫路移封(七月十四日)
・小笠原忠眞信濃松本(8万石)ヨリ明石(10万石)移封(七月二十八日)
139、七月廿三日書状
・加々爪忠澄、伯耆・因幡両国受取ニ出立 (姫路城主・池田光政、因幡・伯耆ヲ與へラレ鳥取城ニ移ル)
・前田利家室・芳春院七月十六日江戸デ死去 (細川忠隆室・千世の母ー慶長5年より忠利に先んじて江戸證人となる)
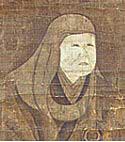 芳春院
芳春院
140、九月廿六日書状
・秀忠伏見ゟ江戸ニ歸ル
・竹千代ノ西丸移徏
・小判二百両ヲ江戸ニ送ル
・領国ノ作毛例年ゟ良シ
141、(九月)書状
・浅野長晟室(家康女・振姫)死去ニ付、浅野長重、加藤忠廣(室・浅野長晟女)ヲ弔問ス
蒲生秀行
‖
家康---振姫
‖-------光晟
浅野長晟
‖-------●
● ‖-------光廣
加藤忠廣
・島津家久松平ノ姓ヲ賜リ薩摩守トナル
・忠利当年下國ノ賜暇アラン
142、十月廿八日書状
・藤堂高虎加封(伊勢度会郡田丸城5万石加増)ノ祝儀
・板倉勝重ヘノ御加増之儀は虚説
・竹千代西丸移徏ノ祝儀
・紫野之儀かたつき珎重
・秀忠ヨリ継目ノ領地判物ヲ下賜サル
・忠利六日ニ江戸到着、八日御目見珎重
・政宗祝言(池田輝政女=秀忠養女・振姫、政宗嫡子ニ嫁ス)ニ人ヲ遣ス
・阿部正次(8,000石)加増
143、十一月十八日書状
・秀忠土氣東金ニ鷹狩ス、進物ノ指図
・忠利、秀忠ヨリ米千俵ヲ拝領
・本多正純、忠利ノ為斡旋ス、又松井興長金子拝領ノ事取合候
・秀忠ノ上洛留守ニハ見舞ノ進物ヲ呈ス要ナシ
・曽我尚祐咳氣
・戸田康長松本移封
・秀忠ヘノ鷹野見舞ニ遅引セシコトヲ釈明ス
144、十一月廿九日書状
・秀忠ヘノ歳暮ノ進物ヲ曽我尚祐・伊藤康勝ニ内談スベシ 極上ノ錦ヲ江戸ニテ求メ土井利勝ノ差図ヲ受ケベシ
145、十一月廿九日書状
・江戸屋敷ノ取土
・藤堂高虎へ返金ス
・東国衆(上杉景勝・佐竹義宣・伊達政宗・南部利直)ノ参勤
・江戸ニ茶湯流行ス 烏丸ノ墨蹟價四千貫
・竹千代西丸移徏ノコトハ土井利勝ヨリ報アラン
・忠利日光社参
・光壽院殿息災・・満足
146、十二月廿一日書状
・秀忠ヨリ鷹ノ鶴拝領
・荒川與三ヲ使者ニ遣ス 以前ニ城主(一戸城=荒川 中比菅野と号す 勝兵衛輝宗守之)タリシ者ノ子ニテ忠興ノ親類
興三口上無調法、田中半左衛門こうけん仕候様ニ・・
寛永四年五月廿七日 荒川與三消息
荒川與三国ヲ払ハル 母親ヲ残ス
一、荒川與三殿儀、筑紫大膳殿をよひ、様子申渡候処ニ、奉得其意候、いつかたへ成共、成次第他国
御頼候
可仕候、母儀ハ爰元ニ残置申候間、万事可然様ニとの儀、大膳殿使ニ〆被仰聞候、得其意申由申
候事、
・竹千代西丸移徏
・土井利勝ト本多正純ノ不和
・曽我尚祐病ム
146、十二月廿一日書状
・曽我尚祐ノ病本復セズ
・半井驢庵ニ用談シテ養生然ルベシ










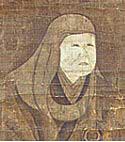 芳春院
芳春院




