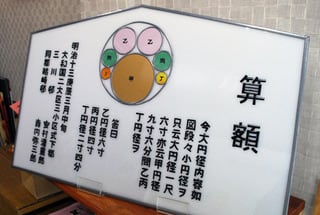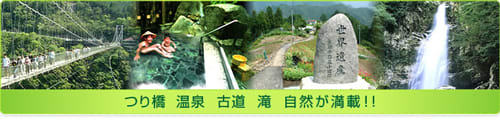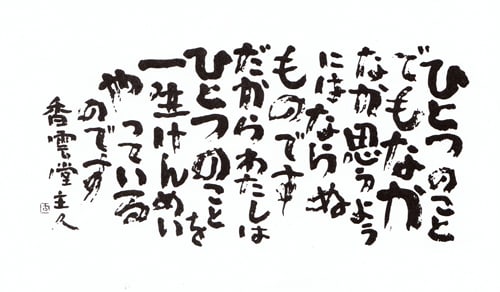6/11(土)、奈良まほろばソムリエ友の会の「発足の集い」が開催された。午後2時から第1回総会(第1部)、2時40分から講演会(第2部)、4時35分から懇親会(第3部)、という3部構成だった。当日の模様が、毎日新聞奈良版(6/12付)に紹介されている。見出しは「まほろばソムリエ友の会発足 奈良の知識集団に」だ。
※写真は、すべてM先輩に撮っていただいた(6/11)
《「奈良まほろばソムリエ友の会」の発足の集いが11日、奈良市の奈良商工会議所であった。今後、ソムリエ同士の交流や研修の他、史跡の解説ボランティア、観光マップ作成などを行っていく。07年から始まった奈良まほろばソムリエ検定(同会議所主催)は、奈良の歴史や文化についての知識を問うもので、奈良通2級、1級とソムリエの3階級がある。今年2月に行われたソムリエの懇親会で、友の会結成が提案され、ソムリエの合格者209人中152人が会員となった》。
《小北博孝会長は「皆様の積極的な活動により、奈良における歴史観光の知識集団として友の会が育っていくようにしたい」とあいさつ。また、奈良文化財研究所の井上和人・副所長が「平城京遷都の真実」と題して記念講演した》。タイミング良く、総会当日(6/11)付の同紙「やまと人模様」欄に、小北会長へのインタビュー記事が掲載された。

私たち友の会役員にとってのメイン行事は、何といっても「総会」だ。総会は会長挨拶、私からの経緯説明、役員紹介、祝電披露、質問タイム、副会長挨拶、とトントンと進んだ。友の会結成の発端は、当ブログでも紹介したように
「合格者の集い」での来村多加史氏(阪南大学教授)からの呼びかけだった。私からはその辺りの説明と、3つの部会(交流部会、広報部会、サポート部会)の紹介、そして「もっとWeb(
ホームページ)を活用してください」と呼びかけた。
私が心配したのは「勝手に11人で会を発足させたのは問題だ。まず発起人による準備会を立ち上げ、ソムリエ全員に諮ってから正式発足させるべきではないか」という意見が出ることだった。株式会社の設立などはそのような手続きを踏むからだ。しかし友の会はあくまで有志の会だし、募集のためのホームページ立ち上げ(発注)や記者発表、朱雀高校との連携など、会として対応すべきことが先にあったので、まず会を発足させ、趣旨に賛同するソムリエだけに入会を呼びかけたわけである。おかげさまで事前に148人、当日は最終的に5人の方から追加の入会申し込みがあり、総勢153人(ソムリエ合格者総数は209人)と、73%ものソムリエにご参加いただいた。
会に出席されたkozaさんは、早速ご自身の
ブログに「奈良まほろばソムリエ友の会。発足」という記事を書かれた。《日程は発会の総会と講演、懇親会となっていました。まずは総会。前後左右、過去未来と見回してしまいいつも論評の多い僕も、今回は素直に受け止めて加わることができました。ゆったりと浸かれば楽しい「友の会」です。頑張ろう、と張り切る方にはもちろんもっと楽しい「友の会」だと思います》。
《懇親会もまた楽しく過ごすことができました。奈良近鉄タクシーの3名のドライバーと元社長が並んで挨拶されたのは最高でした。元社長の北田友の会副会長も立派だが、3名のドライバーの方も輝いておりました。さすが「ソムリエ友の会」です。会をここまで立ち上げた、会長、事務局長などのご尽力に感謝し、拍手申し上げます。すべての議事を進行した長岡光彦さんの力量に敬服します。粘り強かったし、誠実でした》。
これは有り難いお言葉である。ドライバーの皆さんは、溌剌としていた。率先垂範で発破をかけられた北田元社長(友の会副会長)にも、敬意を表する。「走るソムリエ」こと吉田個人タクシーの吉田さんも、短い挨拶だったが、お人柄が表れていた。N先輩こと長岡光彦さん(友の会役員)の司会は、とてもスムーズだったし、熱意にあふれていた。《ビールも呑まずにつまらなそうにしている僕にすぐ声をかけてくれた、佐保台のIさんには心から感謝申し上げます。参加して良かった》。

そのN先輩が、昨夜、
当ブログのコメント欄に、興奮冷めやらぬ勢いでこの日の様子を紹介してくださった。《本日は「奈良まほろばソムリエ友の会・発足の集い」でした。予定された内容(1部 総会・2部 講演会・3部 懇親会)もおかげさまで無事終了し、3月の世話人会立ち上げから約3か月、ともに語り、悩み、準備を重ねた皆様との打ち上げ会で、しこたま頂きまして、今ようやく酔いもさめパソコンが触れる状態まで復活です》。
《祝電ご配慮の奈良商工会議所さま、奈良県ビジターズビューローさま、奈良市観光経済部さま、東京出張からかけつけて本当に熱心にご講演いただいた奈良文化財研究所・井上和人先生、直前まで学生との屋外学習で忙しい中、懇親会に参加いただいた来村多加史教授、細かくご配慮いただいた商議所Uさま、ビジターズビューローTさま、受付ご担当の方、写真ご担当U先輩、M先輩、ご意見発表のⅠさん、懇親会では遠来、東京から、山梨から。奈良近鉄タクシーさま、浪速のパワフルおばちゃま。たくさんの方から前向きの力強いご意見発表で盛り上げていただき、本当に本当に、心から感謝とお礼を申し上げます》。「浪速のパワフルおばちゃま」とは、大阪のご出身(現在は奈良市在住)の肉食系女子・Sさんのことである。「あまり小難しくせず、もっと愉快にやりましょう」という提案をされ、参加者全員が納得していた。
《「友の会」丸は無事船出しました。これから素晴らしい目的地に向かって航海が始まります。皆様、ともにがんばりましょう》。事前準備には、11人の役員全員が仕事を分担して取り組んだが、当日、最もご負担をおかけしたのが、やはりN先輩だった。何しろ1~3部、すべての司会・進行を一手に引き受けてくださったのだから。初回は失敗する訳にはいかないので、ベテランを起用したのだが、その思惑は的中し、kozaさんが書かれたとおり、首尾は上々だった。
役員11人のなかには、どんどん積極的に活動範囲を広げるべきだという「シャカリキ部会」(私が筆頭格)と、奈良好き同士ぼちぼち行こうという「漠然部会」(
てるぼうさんが筆頭格)の2つの流れがある(正式の「部会」ではない、念のため)。来村教授からは「突っ走るときには必ず冷静な第三者が必要なので、2つの流れは好ましい。衆議院と参議院のように、チェック&バランスを利かせてほしい」とのアドバイスをいただいた。
ともあれ、友の会は極めて順調にスタートした。これから徐々に部会の活動が始まる。役員のうち7人は、来年の「古事記完成1300年」に備えて、自主的な古事記(原文)の輪読会「古事記を読もう会」をスタートさせる。半年間で古事記をマスターしたあと、こんどは友の会会員の希望者に対し、ゼミ形式で知識を受けつごう、そして古事記完成1300年を盛り上げよう、という趣旨である。
これからは、シャカリキと漠然のバランスを取りながら、友の会を「愉快に、楽しく」運営して行きたい。会員の皆さん、ご協力をお願いします! そして、これから「奈良まほろばソムリエ」をめざす皆さん、1年でも早く合格され、私たちの仲間にお入りください!
※総会当日(6/11)の毎日新聞奈良版「やまと人模様」。友の会の小北会長が紹介されている