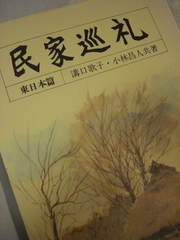■ この本の著者中島義道さんは、商店街(別に商店街に限ったことではないが)のコンクリートの電柱や「黒々と幾重にも絡み合いもつれ合って」延びる電線、広告が醜い!と最も感じている方なのかもしれない。
そして商店街(これも商店街に限らないが)のスピーカーから流れる「音」をうるさい!と最も感じている方なのかもしれない(『うるさい日本の私』)。そんな著者が書いた「日本人の美意識」論とでも紹介したらいいだろうか。
美に敏感な日本人が商店街の電柱を、電線を、巨大な広告を受け入れてしまうのは何故なのか、醜悪で無秩序な街に寛容なのは何故なのか・・・。
日本人に限らずアジア人は混沌とした状態が好きなのだ、という指摘がある。都市の姿はその意識の反映ということだが、なるほどと思う反面、説得力に乏しいとも思う。
著者は多田道太郎の「日本の盛り場の原型は縁日だ」という指摘を紹介して、更にこう書く。**裸電球が揺れる縁日の光景は、横町の赤提灯の光景に連なり、それが自然なかたちで(この部分を著者は強調している)下北沢に、吉祥寺に、渋谷センター街に成長して行く。(中略)村祭りを懐かしむ感受性がそのまま、歌舞伎町や六本木を受け入れる感受性に繋がっている。**
慧眼!
また、日本人は襖の向こうの声は聞かなかったことにするという暗黙の了解があるという指摘(『「しきり」の文化論』柏木博/講談社現代新書)を踏まえて商店街の電線を「見ない」という「心のもちよう」もとり上げている。
著者は電気通信大学の人間コミュニケーション学科の教授。建築や都市計画の専門家ではないので、テーマに対する独自のアプローチが興味深かった。本書は5章から成るが商店街、更に都市の景観については2章しか割いていないのが残念ではあった。
ある写真家の写真集に書いた磯崎新のあとがきに対して **「おいおい、寝言をほざくなよ」と言いたい** と手厳しい。「やかましい」ジイサンぶりはこの本にも出てくる。なかなか面白い本で、一気に読了した。
『うるさい日本の私』を刊行したとき、「うるさい」は「日本」と「私」のどっちにかかるのかと多くの人に面白半分に尋ねられたそうだが、「両方にかかるんです」と答えてきたという。今回のタイトルの「醜い」も両方にかかる、と著者は書いている。










 ①
① ②
②
 ③
③