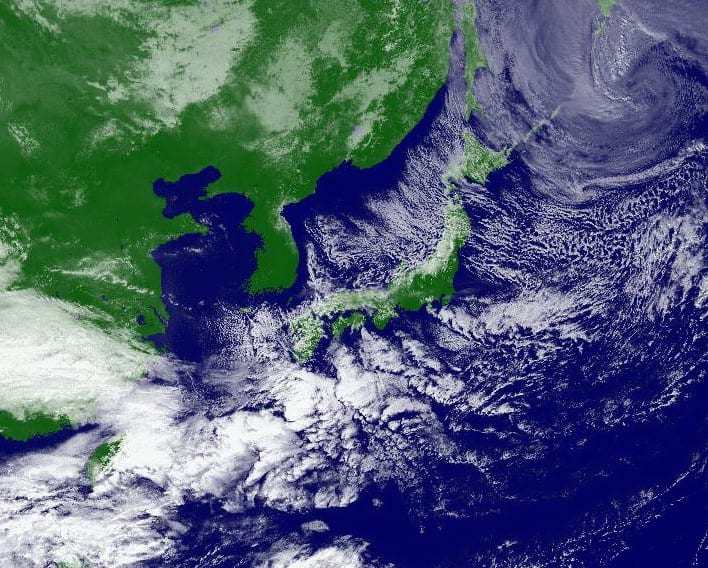昨日はひな祭り寒波で大雪、今日は街中をブリザードが吹き荒れている。
こんな日に年寄りが出歩けば行き倒れになってしまうので、家で大人しく本でも読んでいるか、
パソコンでシコシコと写真の修整なんかしている。
RICOH GX200は、大きさ重さ・カメラデザイン・多機能性なんかが気に入って使っている。
一方、高感度特性が悪く実質ISO200以上ではノイズ出捲りで使い物にならない。
どの様に調整しても画質が悪く、絵作りカメラとしてはペケである。
したがってシコシコと写真の修整なんかしているのであった。

『隠れビーチ』
薄暗い藪の中の小径を辿って行くと、突然ポカッと人っ子一人居ない小さな砂浜に出る事が有る。
これを隠れビーチと言い、見つけた時は何か得した様な気分になる。
明るい砂浜と手前の木の葉の明暗差が強烈なので、原画では手前が黒つぶれしてしまっているので
シャドー部を明るくし修正してある。

『ど根性モクマオウの木』
根元が波に洗われてしまったモクマオウの木、でもしっかり生きている。

『崖上のソテツ』
他の植物が生育出来ない様な所でも生きて行けるのがソテツの木。
そのソテツの実を喰らってでも生きる人間は、一枚上手の生き物なのだ。

『横向きに生えるアダンの木』
熟したアダンの実には良い香りが有るが、食べてみると亀の子タワシの食感だそうだ。
(亀の子タワシを食べた事有る人って居るのかな?)

『珊瑚礁の海とモンパノキ』
この写真は一切無修正、光量豊かな順光条件だとGX200も何とか使い物になる。

『ヤエヤマアオキの花と実』
RICOHのカメラはレンズ性能が良いため、マクロ撮影での画質は素晴らしい。
GX200の場合、1 / 1.7インチの撮像素子に1210万画素も詰め込んでいるため、
せっかくのレンズ性能を殺すというバカなことしている。

『木白香とサンゴの化石』
800×800ピクセルにサイズダウンしても、この程度の解像感が得られるんだから良しとするか。

『アッカンベーのナハエボシグサ』

『しおれたバナナの花』

『クマタケランの葉っぱと実』

『オオタニワタリと拝所』
オオタニワタリの新芽に塩コショウして、バターで炒めると大変美味しい。
沖縄本島の人に「沖縄じゃ食べないの?」と聞いたら「あんな物は八重山の貧乏人が食う物だ」
とは言わなかったが、顔に書いてあった様な気がした。