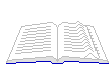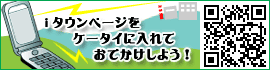| 菜の花の沖〈2〉文藝春秋このアイテムの詳細を見る |
函館にある高田屋嘉兵衛像

【一口紹介】
出版社/著者からの内容紹介
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を描いた名作が、大きな活字の新装版で一挙大登場!
内容(「BOOK」データベースより)
海産物の宝庫である蝦夷地からの商品の需要はかぎりなくあった。そこへは千石積の巨船が日本海の荒波を蹴たてて往き来している。海運の花形であるこの北前船には莫大な金がかかり、船頭にすぎぬ嘉兵衛の手の届くものではない。が、彼はようやく一艘の船を得た、永年の夢をとげるには、あまりに小さく、古船でありすぎたが…。
【読んだ理由】
「播磨灘物語」に続いての司馬遼太郎作品。
【印象に残った一行】
『炊(かしき)という最下級の船員ほどつらいものはなく、乗組員たちから人間扱いにされなかった。
かれらは船内のあらゆる雑役に追いつかわれる。しかもおもなしごとは炊事で、船が湊に入ると、まず食糧の買出しからはじめねばなない。入費は船頭もしく知工(事務長)からそのつど渡され、その範囲内で安くてうまい材料を見つけねばならない。
「なんだ、この牛蒡は、木の根か」
というだけで、若衆からなぐられてしまう。
めしは、乗組員の人数ぶんだけきっちり炊かねばならない。できあがった、飯の量に不足があったり、余ったりすると。
「いったい、どういう料簡で船に乗っているんだ」
と、綱をつけて海へ投げこまれたりする。綱がついているというものの、波頭の上をときに跳ぶようにひっぱられてゆく。そういうときなど、いっそ死んだほうがましだと思うらしい。
唄がある。
船に乗るとも炊にゃなるな
一にいびられ、二に睨まれて
三にさらされ、四に叱られて
五つ御器椀洗わんにゃならぬ
六つ無理なこと言いつけられて
七つ泣いたりなげいたり
というのだが「炊にゃなるな」とはいえ、船に乗る以上、炊からはじめるほかに訓練方法がなかったのである。
この時代の日本社会の上下をつらぬいている精神は、意地悪というものであった。
上の者が新入りの下の者を陰湿にいじめるという抜きがたい文化は、たとえば人種的に似た民族である中国にもあまりなさそうで、「意地悪・いじめ・いびる」といった漢字・漢語も存在しないようである。
江戸期には、武士の社会では幕臣・藩士を問わず、同役仲間であらたに家督を継いで若い者がその役についた場合、古い者が痛烈にいじめつくすわけで、いじめ方に伝統の型があった。この点、お店の者や職人の世界から、あるいは牢屋の中にいたるまですこしも変わりがない。日本の精神文化のなかでももっとも重要なものの一つかもしれない。』
【コメント】
作者の博学には驚かされる。江戸時代の日本の海運を中心とした物流事情や、この物流に支えられた日本各地の特産品産業の発達の様子なども大いに参考になる。