最近、オーケストラを聴きにいくようになり、指揮者への関心を深めています。そこで、フランスの指揮者シャルル・ミュンシュ(1891年~1968年)が書いた「指揮者という仕事」(春秋社)という本を読んでみました。

ミュンシュの略歴ですが、1926年~32年にライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団でフルトヴェングラーの下でソロ・ヴァイオリン奏者を務め、指揮の機会を持つことがあって、指揮者の道へ。1937年にパリ音楽院管弦楽団の指揮者、第二次大戦後の1949年から62年はボストン交響楽団の音楽監督、62年からフランスに戻りフリーで活動し、67年に創立されたパリ国立管弦団の指揮者として活動。68年にこの楽団とアメリカ演奏旅行中に急逝しました。
(目次)
第1章 いくつかの主題による前奏曲
第2章 修行時代
第3章 いかにして指揮者になるのか
第4章 プログラムを作る
第5章 ひとり総譜と向かい合って
第6章 リハーサル
第7章 コンサートの夕べ
第8章 オーケストラ楽員の生活
第9章 指揮者の生活
この本の原著は、フランスで出版された「私の職業」というシリーズの中の一冊です。ミュンシュは、自分の生い立ちや修業時代、仕事の内容や生活までを内情を含めて書いています。シリーズの性格から、これから指揮者を目指して勉強している人へのアドバイスという観点が出ています。音楽的な知識がさほどなくても、指揮者という職業の秘密の一端が披露されているので、面白く読めます。
僕がそうなのですが、クラシック音楽が好きな人なら、指揮者に対しては、畏敬の念とともに憧れを持つ一面があると思います。そんな人向けにミュンシュは、『読者は信じてほしいのだが、コンサートは毎度、頭脳と筋肉と神経のエネルギーを信じ難いほど消耗させるのだ』と本音を述べています。
(勉強の重要性)
勉強の重要性をかなり説いている部分は記憶に残りました。『指揮者になるには、十年勉強してなんらかの天分を示すだけでは充分ではない。音楽院の門をくぐる最初の朝から、疲れ果てて生涯最後のコンサートを終える晩まで、勉強しなければならない』と第1章に記し、第3章では、『何よりもまず、楽器の勉強を深めることが絶対に必要』とし、第5章では、『総譜のあらゆる秘密を熟知していると完全に確信するためには、暗譜にまさる有効な手段はない。」とまで述べています。
(現代音楽への関心)
僕は、ミュンシュは古典的な音楽を中心として指揮した人だと思いこんでいました。しかしこの本では、現代音楽を取り上げることの重要性を説いていて、驚きました。『私としては、いつも自分のプログラムに古典派やロマン派の音楽と並べて、国際的な現代音楽を入れてきた。われわれの世紀の音楽はわれわれが生きている世界の関心事、不安、動向を表現している。』と、第4章に記しています。ルーセル、オネゲル、シュミット、メシアン、デュティユー、マルティヌー、ヒンデミットという作曲家の名前を挙げています。
(小沢征爾さんの先生)
第6章などでは、 オーケストラ団員とのやりとりのノウハウまで披露している部分もあったりして、指揮者志望者へのガイドという役割が主ですが、、オーケストラや指揮のことを知りたいと願う聴衆向けの一冊でもあります。解説にありますが、日本の指揮者の小沢征爾さんの先生の一人がこのミュンシュです。そういう点もあわせ、シャルル・ミュンシュの名前には幾分か親しみを覚えます。CDは何枚か持っていますが、彼が指揮した現代音楽(今となっては古典的なものもあるはずですが)を聴いてみようという気にもなりました。
(僕が持っているCD)
他にも、ブラームスの交響曲第1番も持っていますが、ルーセルなど新しいものを聴いてみるつもりです。
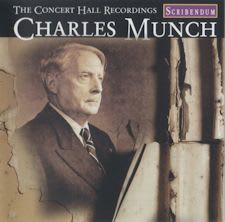
コンサートホールレコーディングス(CD4枚組)。コンサートホールレーベルは、音質が悪いとされていますが、近年いくらか改善されているようです。フランスに戻ったフリーの時期の録音で、フランス国立放送管弦楽団とロッテルダムフィルハーモニーを指揮しています。ベートーヴェン交響曲第6番「田園」、ビゼー交響曲ハ長調、フランク交響曲ニ短調、ドビュッシーやアルベニスの管弦楽曲、ロシア音楽が収録されています。

ラヴェル管弦楽名曲集。パリ管弦楽団との録音です。









