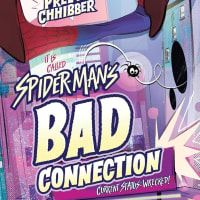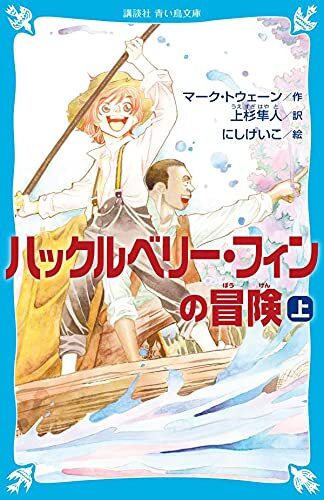「……埋もれ木の、人知れぬ身と沈めども、心の花は残りけるぞや……、花見んと、群れつつある人の来るのみぞ、あたら桜の、咎にはありける……」
己の声は枯れ寂びて、波打つようにしか出ぬが、これもまた自然の理。わが老いも、桜の老いも等しき想いで声にする。
藤沢周『世阿弥最後の花』の一節だ。
この美しい日本語は、不十分な英語ではあるが、
“...Nobody knows buried trees will be fallen down...
A flower in the heart will remain.
We can just see a throng of people who come to see new flowers in full bloom now...”
Since my voice withered, all I can do is to recite undilutedly, but it is the providence of nature.
Accepting both cherry blossom and I have already grown old, I will chant.
くらいに訳せると思うし、外国人に意味は理解してもらえるだろう。
だが、原文のよさはまるで伝わらない。
日本語の古語、漢字の使い分け、憐みの心。
藤沢周『世阿弥最後の花』を読んで、これらを英語にするのは不可能ではないだろうかと改めて思った。
大昔に何度か仕事をした外国人は、自分は日本語がよくわかるということを強調したい一心からだろうが、よく「日本語は簡単。英語のほうむずかしい」と言っていた。
それはある意味あたっているが、ある意味外れている。
英語は同じ単語にいろんな意味があり、状況によって、そして使う人によって意味が使い分けられるので、その意味を特定する(detecting the meaning)のはむずかしい。
だが、日本語のむずかしさは上に書いたようなことであり、これを外国人に理解してもらうのは容易なことではない。
そしてこれが日本語の至上の美しさでもある。
マーク・トウェーン『ハックルベリー・フィンの冒険』のような名作を訳す機会にめぐまれるなど、英語と英語で書かれた文学の楽しさとすばらしさをありがたいことに日々味わっている。
だが、この藤沢周の『世阿弥最後の花』のようなすぐれた日本文学作品とそれを織りなす美しい日本語に触れるたびに、日本語の豊饒さと奥深さを感じる。
そして英語も日本語も学べるわが身の僥倖を噛みしめている。