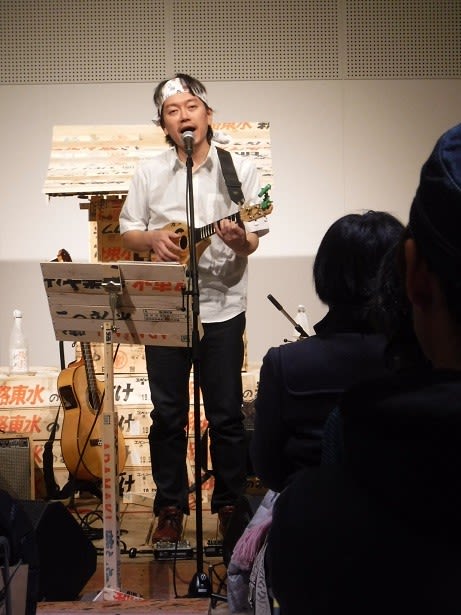今日(12月11日)、過日決定したマラソンコースの前半20キロを歩いてみた。雪が消え、気温8℃と絶好なコンディションで気持ちよく歩くことができた。コースはフラットで、周りの景色も変化に富んでいて素晴らしいコースだと感じた。
(歩きながら撮った写真が60数枚にも達したため、一度の投稿では無理だと分かりましたので前後編に分けてレポートすることにししました。)

※ この大会組織委員会案の一周回目だけが12月4日に認められ、そこを本日歩いてきました。
東京オリンピック2020のマラソンと競歩が札幌で行われることは決定していた。そして12月4日にマラソンコースの前半20キロが決定したと国際オリンピック委員会(IOC)から発表があった。するとその後直ぐに北海道新聞の記者が実際に走ったレポートを掲載した。それを見て、「あっ!自分も歩いてみようか?」と思い立った。
講座や会議などでスケジュールが見いだせなかったが、今日は何も予定か入っていなかったので決行することにした。しかし、数日前に大雪が降りコンディションが心配だった。私は靴に装着する滑り止めを購入し万全を期した。ところが昨日の高温で雪が溶け、今日もけっこうな気温となり、まったくのウォーキング日和の中で歩くことができた。
コースを歩くにあたって、コース図が必要だったのだが詳しいマップがウェブ上を探してもなかなか見つからなかった。そうした中で唯一頼りになるページを探し出すことができ(https://gpscycling.net/marathon/tokyo2020.html)、それをもとに慎重にチェックしてウォーキングに臨んだ。あるいは細かな点で違いのあるポイントがあるかもしれないが、大枠では違いはないコースを歩くことができたと確信している。それでは、写真と共にコースを紹介していくことにしたい。


スタート地点の大通西4丁目(駅前通り)です。テレビ塔の時計は10時29分を指しています。ここからコースは南に向かって伸びています。同じくスタート地点のビルの温度計が8℃を示していました。

スタートして間もなく、ススキノの交差点に差し掛かります。ススキノの名物の大看板が選手たちを見守ります。コースはススキノのど真ん中を中島公園に向かって突き進みます。ススキノも午前7時のスタートではまだ前日の酔いから覚めていないでしょうね。スタートしてしばらくは交差点の信号で待たされるのが悩みでしたが、仕方がないですね。

ススキノを通過すると、中島公園の正面の入り口に差し掛かります。コースは正面を見ながら左折します。

左折してパークホテルの敷地の周囲を巻くように、次の交差点を右折します。



右折すると中島公園の横の通りを南に進みます。選手たちの右手には中島公園の緑が目に入り、選手たちを癒してくれるでしょう。メディアでも紹介されていましたが、中島公園を望むコース上のヘヤーサロンがコースが決定すると直ぐにお店の窓に写真のような歓迎の表示を掲げたそうです。

中島公園の敷地の終点のところの交差点を左折し、幌平橋へ向かいます。

左折して直ぐに特徴のある幌平橋が選手たちを出迎えてくれます。コースは幌平橋を渡り、対岸に移ります。

幌平橋ほ渡って200mほど進むと地下鉄「中の島」駅の表示が見えます。そこの交差点を右折すると「中の島通」に入ります。その「中の島通」をしばらく南下します。

「中の島通」です。写真が全体に暗いのは、この日の天候が全天曇っていたことが原因だと思われます。コース左手には北海道科学大学の豊平キャンバスや北海道科学大学高校の校舎が見えたのですが、写真に撮ることを失念してしまいました。(残念!)

その北海道科学大学豊平キャンバスを過ぎて間もなく交差点が現れます。そこを左折すると通りは「白石・藻岩通」に変わります。

左折すると直ぐに北海道自動車学校が見えます。「白石・藻岩通」は写真のようにやや上り勾配のコースとなっています。今日の20キロコースでは唯一の上りコースです。観戦ポイントとしては絶好かも?

「白石・藻岩通」を上がりきりしばらく行くと、大きな通りの交差点にぶつかります。そこを左折すると「平岸通」です。

左折して直ぐくらいのところがコースの5キロポイントです。通りは「平岸通」です。

「平岸通」はご覧のように中央分離帯があり、そこが植樹帯となっていて、通りも広くなっています。この通りをしばらく北上します。

「平岸通」の途中で見かけた大きな交通安全ダルマ(?)です。季節らしくサンタクロースの衣装を付けています。タクシー会社の前に設置されていました。来年8月にはどんな衣装で選手たちを出迎えるのでしょうか?


通りには北海学園大学、北海道商科大学のキャンバスがありました。後になって気が付くのですが、コース上にはたくさんの大学が点在していることに気が付きました。そのことについては後編で触れたいと思います。

「平岸通」は途中やや左に折れながら進みますが、北海学園大学を過ぎると「豊陵公園」に行き当たります。この公園を左に巻くように進みます。実はこのところが不安でもあったので、近くにいた学生さんに尋ねたところ、大会コースになっていることそのものを知らないということでした。さらに進んで札幌市の外局に勤務する職員にも尋ねたのですが、彼らも大会コースとなっていることを知らないという答えでした。たった二組に聞いただけですから断定的なことは言えませんが、意外に市民にの関心は低いのでしょうか?まあ、大会が近づくとそれなりに盛り上がるのでしょうが…。

豊陵公園を巻いて道なりに進むと、「南七条大橋」に導かれます。コースはこの橋を渡り再び札幌の中心街へと入っていきます。

「南七条大橋」を渡って直ぐにコースは右折し、「創成川通」に入ります。創成川通に入ると、コースはひたすら真っすぐに北上し続けます。


創成川通の入って間もなく、創成川通の混雑緩和のために建設された「創成川アンダーパス」が現れます。(道路右側がその入り口です)以前マラソンコースとしてアンダーパスを通ると聞いた記憶がありますが、実際はどうなっているのでしょうか?私は今のところ何も情報を掴めておりません。アンダーパスは1,100mあるそうです。ちょうど中心街をバスすることになります。

コースがアンダーパスを使うことになると、選手たちはスタート地点で目にした札幌テレビ塔の真下を通ることにはなりません。実際のところはどうなんでしょうかね?

アンダーパスの出口のところを撮るのを失念してしまいました。目の前に見えるのはJR函館本線の高架橋です。

この高架橋のところがスタートから10キロのポイントだということです。ちょうど20キロコースの半分まで達しました。
本日はここまでにして、明日後半の10キロのコースについてレポートすることにします。