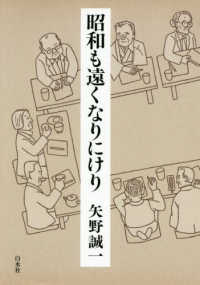
昭和生まれの私が、平成を生き、令和の新しい時代を迎えて、つくづく昭和は遠くなったと思う。
17年生まれの私は19年に祖父母と父が亡くなり熊本へ帰ることを余儀なく仕、幼少期は終戦後の苦難の真っただ中に生きた。
貧乏であったがあまり苦しかったとも思わない。誰もがそういう境遇であったからだ。
28年の大水害で財産の粗方をなくし、母は大いに苦労したのだろう。
私が社会に出たころは、「所得倍増」が謳われ、まさにそれが実現していく面白い時代だった。
東京オリンピックや大阪万博が開催され、高度経済成長で世界の仲間入りをした。
この本の著者・矢野誠一は「やなぎ句会」のメンバーの生き残りである。メンバーのほとんどはあの世に御座る。
それぞれの皆さんは私よりは5歳~10歳年上の方ばかりだが、まさに昭和の匂いをぷんぷんさせた人達である。
粋で洒脱でそれぞれの世界で一流の方々である。時代が下って平成の御代では、こういう粋人たちは出ないのではないか?
出版社の案内に「50年続く「東京やなぎ句会」の句友たちの動向を中心に、多くの藝人や俳優たちが歩んだ人生を生き生きと描く。」とある。
せめてこの本を読んで、その空気感を味わいたいと思うのである。
目次
1 東京やなぎ句会のこといろいろ(十二人の熱気あふれる才人たち;安息日の近況 ほか)
2 日日雑感(閏年の手帳;御籤の効用 ほか)
3 藝という世界(落語とメディア展;この落語が聴きたい ほか)
4 劇場にて(伸の知恵、綺堂の知識;東の万太郎秀司の西 ほか)
5 来し方の…(噫七十年;笑いの飢餓を一気に充足させた、庶民の娯楽 ほか)















