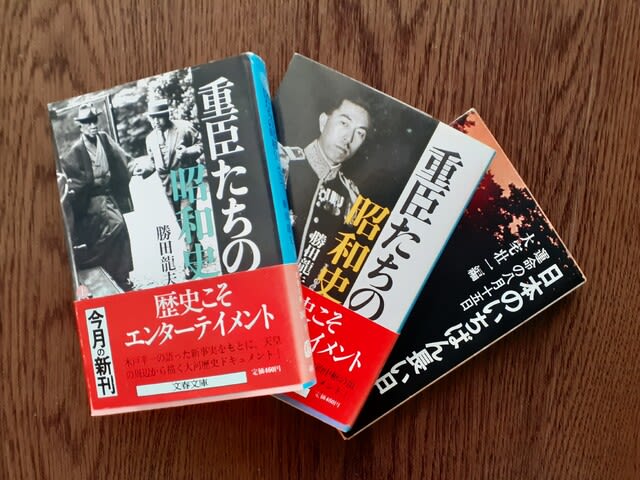綱利の初入国は寛文元年(1661)四月廿八日だが、江戸を出立するときから、行列の見事さが江戸っ子の話題に挙がったという。
そのきらびやかさで肥後入国を果たしたが、財政が悪化の一途をたどる中で大いなる非難を浴びた。
その結果江戸御奉行・堀江勘兵衛(2,000石)が知行召し上げとなった。
正史では見受けられないように思うが、堀内傳右衛門の「旦夕覚書」は、沢村大学の養嗣子・沢村宇右衛門の指図であったと指摘している。
一、初て御入國は拙者十七の時にて未致御目見候 皆とも立田に大勢罷出見物仕申覺申候 後に承候へは
江戸にても道中にても珍敷結構成る御供行列と申たる由其時の江戸御奉行堀江勘兵衛は先御代より
千石被下御奉行一人の埒明と申候 江戸御立の御用意に大分御銀入申候 澤村宇右衛門殿差圖の由に
て熊本の御家老中事の外立腹にて堀江勘兵衛は知行千石被召上四十人扶持被下宇土邊に引籠致病死
候 堀江は唯今の伊藤又右衛門ゟ母方の伯父かと覺申候 惣躰角力御數寄男すき被成候儀も皆宇右衛
門殿召れたる様に後々迄十左衛門殿舎人殿なと御咄承候事
この綱利初入国に際し、筆頭家老・松井興長は病をおして八代から出府している。
そして、綱利の将来を案じながら六月廿八日に死去することになる。前年興長は綱利に対し厳しい諫言を行ったばかりである。
そんな中でのこのような華美な行列への非難は当然であり、当事者への非難は集中したであろう。
しかし、沢村宇右衛門には何の処分もなかったとみられ、堀江勘兵衛が割を食った。
沢村宇右衛門は松井康之の姉の孫・松井二平次の息に当たり、沢村大学の養嗣子となった。
興長からすると従兄弟の子にあたる大事な一族でもあり、家老衆の忖度もあったであろう。
この処分は綱利の江戸への参勤前の事であるから、大事な側近の処分におおいに震え上がった事であったろう。
似たような話で新聞をにぎわす事件はいつの時代にもある。