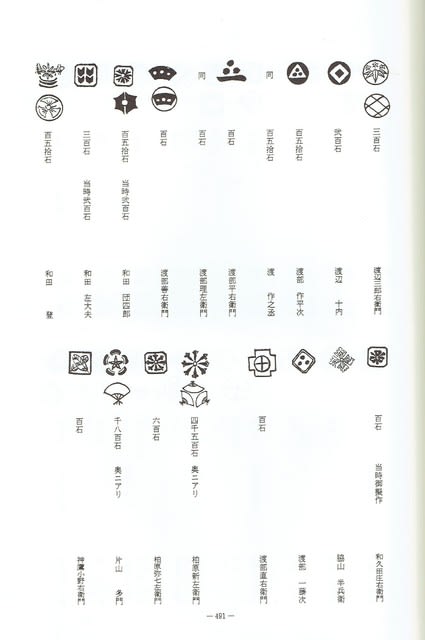(寛永元年十月)十三日・十四日・十五日
|
| 十三日 両人詰 雨
| (ママ)
談合 |一、式ア殿へ民ア殿・御奉行衆、利斎彼寄相候て談候事、
| (幸長)(甚丞) (元高)
薮政三ノ返上米 |一、同薮三左衛門返上之米之儀ニ付、中津へ先日野田・豊岡所ゟ、志水次兵衛所へ遣候目録を、中津
| 御奉行衆へ遣候て、其返事次第ニ可仕之由にて、式ア殿・民ア殿ゟ書状相添、今日八つさかりニ
| (薮正成)(同政直)
| 飛脚被遣候、左候時ハ、図書・小吉知行之口明可申之由候事、
女敵討之詮索 |一、同所ニ而、田川助兵衛・四郎右衛門女房之出入之事、助兵衛ハ三ケ度糺明候へ共、少も口不替
| 候、いかゝ可仕哉と被尋候ヘハ、四郎右衛門きずなおり次第、きうめい可被申付之由ニ候事、
| 少左衛門ニ
盗人誅伐 |一、同所京都郡之者、竹原市蔵奉公仕候へ共、暇を遣候ニ、見廻ニ参候て、ぬすミを仕候とて、御郡
| 〃〃
| 奉行衆小倉へ指出候、于今籠者申付候、いかゝ可仕哉と被尋候ヘハ、誅伐可被申付之由ニ候事、
京吉田ニテ走リシ |一、同所にて、去年京吉田にて走り申候御小人、于今籠者申付置候、是ハ泰勝院御吊之時、籠ゟ可被
小人釈放 | (真下)(横田)
| 出ニ候へ共、七兵衛・権佐へ一通可相尋とて、于今籠ニ入置候、其後書状にて相尋候ヘハ、させ
| る罪にても無之候間、御免候へと申来候、左候ハヽ、籠ゟ被出候へとの儀ニ候事、
林弥五左困窮ニツ |一、同所、林弥五左衛門手前不罷成ニ付、知行上ケ可申之由候て、書物を上ケ申候、いかゝ可仕哉
キ知行返上願 | と被尋候ヘハ、御留守ニ知行を上ケ候とても、各として請取儀ニあらす候間、江戸へ可被請
| 御内証之由ニ相究、書物を被返候へとの儀ニ候事、
|同所にて、 (首) (首)
細川幽齋法事ノ布 |一、泰勝院御法事之時、圭主座弟子たくぞうす・全西堂弟子、其外四人ノ平僧布施之儀、此中圭主座
施ノ催促 | (雲崖靈圭)
| ゟ節々申来候、いかゝ可仕哉と被尋候、先例仕之由ニ候事、
筑前ヨリ唐人薬師 |一、筑前ゟたう人くすしおや子、上下五人はしり参候、女子御座候へ共、筑後へさり遣候を、おと子
父子走リ来ル | 之子壱人ハ此方へ召連参候、当町ニ有付申度由申ニ付、御町奉行衆へ被渡候事
町奉行へ渡ス |
| (下関、長門豊浦郡)
筑前ヨリ走来ル侍 |一、同所より侍壱人走り参候、爰元ニしる人も無之、壱人身ノ者ニて候間、下ノせきへおくり候へと
ヲ下関へ送ル | 之儀ニ候事
|(ママ)
|一、
|
| 十四日 両人詰 雨
| (久持か)
暇ヲ出サレシ陪臣 |一、宗持作丞と申歩之御小性、前かと道家次右衛門所ニ居申候へとも、暇を被出候ニ付、 殿様へ御
ノ召抱 | 抱可被成候事、
|一、河喜多五郎右衛門煩なをり、登城被仕候事
|
|
| 十五日 両人詰 曇
| (大里、規矩郡)
大里之茶屋作事所 |一、林弥五左衛門登城、たい里ノ御ちや屋作事御座候、 殿様上洛前ニ被仰出候ヘハ、所ノ者共ニや
ノ者ニ手伝ハシム | (御脱)
| くを免候間、手伝之様成物事ハ、所ノ者ニ可申付由、 諚被成候間、其分ニ御郡代へ可被仰渡
| 〃
| (上田)
| 候、弥五左衛門慥成承ニ而候間、則上忠左衛門へ被申渡候事、大工之入儀ハ弥五左衛門可申付之
| 由、被申候事、
|
吉田ニテ走リシ小 |一、御小人半介、去年吉田にて走り申候ヲ、籠者被申付候、当夏泰勝院御吊之時、籠ゟ被出筈ニ候へ
人赦免 | (真下) (横田)
| 共、七兵衛・権佐へ一通相尋候て、其上之儀ニ可仕と被延置候、右両人ゟも別条曲事無之候間、
| 被免候へと申来ニ付、今日籠ゟ被出、不相替、似相ニ可被召遣由ニ候事、
| (浜脇村、速見郡)
天領ノ入牢者診察 |一、はまわきノ久三郎、籠ニ而煩候ニ付、明寰ヲ見せニ被遣、薬与候へと被申渡候事、
ヲ明寰へ命ズ |
| (高月) (前原、志摩郡)現・糸島市
筑前ヨリ小者走来 |一、人留御番尾藤新介登城、筑前まへ原ゟ、喜七と申小者走参候、式ア殿へ召連可参由、被申渡候、
ル |
|追記
物書召抱 |「御物書本田加介、右之者召置候事、」
|