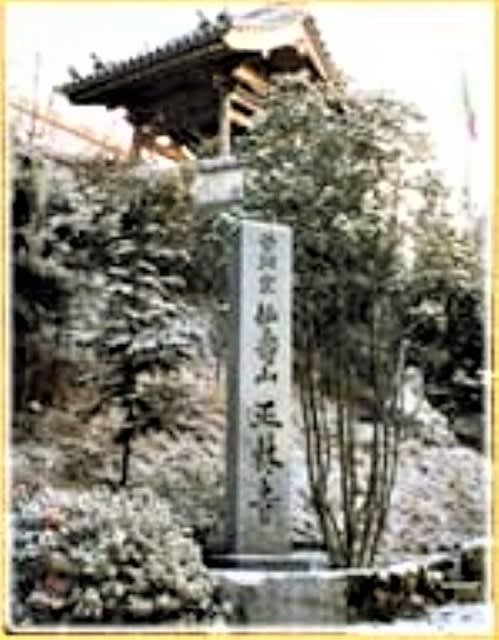今日の武蔵野公園の樹々の黄葉の風の写真をお送り致します。













現在、日本の仏教は八つの宗派があります。天台宗・真言宗・浄土宗・浄土宗真宗本願寺派・真宗大谷派・曹洞宗・臨済宗・日蓮宗です。宗派の違いによって焼香の方法や葬儀でのマナーなどが異なります。
そして東京には75の曹洞宗のお寺があるのです。その幾つかを以下にご紹介いたします。
恵比寿台雲寺 | |
|---|---|

1番目の写真は台雲寺の本堂です。
東長寺結の会納骨堂 龍樹堂 | |
|---|---|
杉並 下高井戸駅近永代供養付墓所 | |
|---|---|
曹洞宗雲居山 宗参寺 | |
|---|---|
心源院 のうこつぼ | |
|---|---|
泉岳寺 | |
|---|---|
普門山 慈眼寺 | |
|---|---|
明王山 威徳院 | |
|---|---|
慈眼寺 のうこつぼ | |
|---|---|
嶺雲寺 | |
|---|---|
誰でも子供の頃の思い出は懐かしいものです。それは人生のとっても大切なものです。今日はお寺の子供僧と山里のお寺の写真をお送りいたします。そして父の弟の孝元和尚のことも書きたいと思います。父の実家は兵庫県の田舎のお寺だったのです。
まず子供僧の写真をご覧ください。

1番目の写真は東京のあるお寺が企画した子供のお寺の生活体験の写真です。子供が袈裟を着て檀家回りに出発しようとしている場面です。写真の出典は、https://www.hongwanji.or.jp/project/report/000842.html です。
私も子供僧になった体験がありました。それは小学生の4,5年の頃、終戦直
そのお寺は曹洞宗で兵庫県の山里の小さな集落にありました。
小高い場所に建っていたので集落の農家や水田が箱庭のように見下せました。
集落の農家は全てお寺の檀家です。家々には金色に輝く立派な仏壇があります。そんな風景写真を示します。
2番目の写真は私が夏の間だけ子供僧になった田舎のお寺によく似た寺の写真です。
3番目の写真はお寺から見下ろした集落の風景に似た写真です。
この写真は「山里の風景写真」を検索して多くの写真から選びました。
集落の家は全て祖父のお寺の檀家でした。米や野菜を寄進してお寺の一家の暮らしを支えていたのです。日本の伝統文化です。
4番目の写真は寺の本堂での法要の様子です。
私も小坊主として後ろの方に座り知っているお経を一緒に唱えました。
毎年夏のお盆に行う施餓鬼供養の写真です。近隣のお寺から僧侶に来てもらい太鼓や銅鑼を打ち鳴らし賑やかな供養でした。
5番目の写真は京都のあるお寺で撮った子供の僧たちの写真です。当時私と弟はこんな袈裟姿をしました。子供用の袈裟は優しかった叔父の孝元和尚が仕立て屋に頼んで特に作ったものです。この写真の出典は、https://temple.nichiren.or.jp/5061018-rengeji/event/shamongo/ です。
最後に優しかった叔父の孝元和尚の思い出を書きます。第二次世界大戦の時に孝元和尚は徴兵されレマレー半島で激しい戦闘を体験したようです。しかし孝元和尚は一言も話しませんでした。敵味方双方の悲劇については完全に沈黙を守りました。
人間の悪については沈黙が賢明な場合があるのです。そのことを私は孝元和尚から学びました。いつも穏やかで優しい叔父でした。
今日は私がある山里で子供僧になった時の様子を書いてみました。そして伯父の孝元和尚の思い出も書きました。
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)