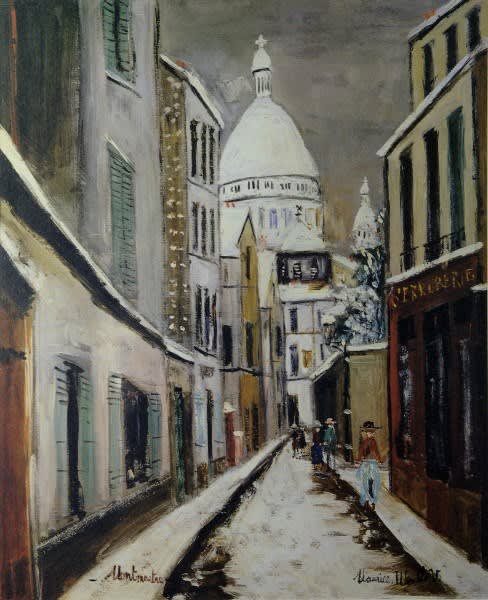日本人の花々に対する美意識が最近とても変わって来たと思います。
日本古来の楚々とした花々よりも華麗な西洋の花々の方が美しいと思う人が圧倒的に多くなってきました。何故か淋しい思いをする私は、時代に取り残された人間なのでしょうか?
そんな想いを込めて今日は日本サクラソウと西洋サクラソウの花の写真をご紹介致します。
数年前に可憐な日本サクラソウに魅了され埼玉県の自生地の「田島ヶ原」へ毎年、足を運んだ時代がありました。4月になるとまだ花が咲いていないかと何度も通ったものです。

1番目の写真は2008年の4月に田島ヶ原で撮った日本サクラソウの写真です。ここは江戸時代から有名な自生地なのです。

2番目の写真は田島ヶ原でサクラソウが密生している場所を探して撮った写真です。
広い草原に細い歩道がめぐらせたあります。その歩道を春風に吹かれながら歩いて行くと青草の間に小さなサクラソウが控えめに咲いています。
しみじみ美しいと思います。
そこで日本サクラソウの花を買おうと隣町の石塚園芸を訪問しました。
しかしニホンサクラソウの姿がありません。皆無です。
その代わり西洋サクラソウの花が広い温室いっぱいに咲いていたのです。
石塚園芸へ家内と何度も行っているうちにご主人の石塚健壽さんとは親しくなりました。
彼はいろいろな意味で感動的な花の栽培家だったのです。精魂こめて交配し20種の西洋サクラソウの新種を作ったのです。
そして新種の西洋サクラソウをオランダの新種の花の祭典、フロリアード2012へ出展し、金賞一席と特別賞を受賞したのです。

3番目の写真は2012年に特別賞受賞の湖畔の夢です。帰りがけに石塚さんが私に一鉢下さいました。

4番目の写真は石塚園芸の温室内に咲いている西洋サクラソウです。交配して作った白い花も見えます。

5番目の写真も石塚園芸の温室内に咲いている西洋サクラソウです。「湖畔の夢」が溢れています。このような温室が3棟あります。そして春に種を植え、大切に育てて12月の末から1月いっぱい花が咲くのです。
3棟ある温室はシクラメンの栽培とサクラソウの栽培の季節が違うので使いわけるそうです。
石塚健壽さんにニホンサクラソウは何故売っていないのですかと聞きました。
日本サクラソウも美しいと思いますよ。しかし圧倒的に多くの人が西洋サクラソウの方が綺麗だと思っているようですよ。とにかく売れるのです。こんなに一杯ある西洋サクラソウが1月になるとアッと言う間に売れてしまうのです。その花を囲んだ家族の笑顔を想像するとこの商売が止められないのです。こんなことを言っていました。
昨日も石塚健壽さんに会ってきましたが現在はシクラメンの季節でサクラソウはまだ咲いていませんでした。
サクラソウといい、シクラメンとといい、日本の家々に飾ってあるのは多くは西洋の花々になっています。
何故か淋しい思いをする私は、時代に取り残された人間なのでしょうか?
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)
===参考資料=======================
(1)ニホンサクラソウの栽培の歴史、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%82%A6
江戸時代の中ごろから、荒川の原野に野生するサクラソウから本格的な栽培が始まり、種子まきを繰り返すうちに、白、桃、紅、紫、絞りなどの色変わりや、大小さまざまな花形の変わり品が生まれ、名称が付けられた。やがて江戸時代後半になると品種数も非常に増え、文化元年(1804年)から新花を持ち寄り品評することが始まった。栽培者は旗本や御家人など武士階級が多く、「連(れん)」と呼ばれる2~3のグループが成立し、新品種の作出を競い合った。文化から天保(1804年~1844年)にかけてがもっとも盛んな時代であった。熱心な女性の愛好家もいて、寒天を流し固めた重箱に一品種ずつ挿し並べて鑑賞したという文献もある。幕末には各地に広まり、文久2年(1866年)にはサクラソウとしては現存最古の番付が発行されている。現在栽培される約300品種のうち、その半数が江戸時代から株分けで伝えられたもので、その花は多様な花型と繊細な花色が特徴で、他の多くの日本の伝統的な園芸植物と共通している。品種ごとに鉢植えで育て、花時には「花壇」と呼ばれる屋根付きの五段構造の展示台に配色よく飾る。鉢は「孫半土(まごはんど)」という、本来食品容器として作られた瀬戸焼の陶器が使われた。これはサクラソウのデリケートな花色をよく引き立てる。
愛好者層が武士中心であったので、明治維新前後には衰退の危機にも見舞われたが、やがて愛好者も増え、新花の作出も再び盛んになった。この頃に生まれた名花にも今に伝えられているものがある。やがて太平洋戦争により、サクラソウの栽培も下火になったが、戦後次第に復興し、昭和31年(1956年)に愛好者のグループである「さくらそう会」が発足、関西にも「浪華さくらそう会」が生まれた。この他全国各地に愛好会ができ、今に続いている。

6番目の写真は田島ヶ原サクラソウ自生地の写真です。
埼玉県さいたま市桜区の「田島ヶ原サクラソウ自生地」は国の特別天然記念物に指定されている貴重な群落である(桜区の区名も桜ではなくサクラソウに因んで命名されている)。荒川流域のこの一帯は、下流の戸田ヶ原、浮間ヶ原などとともに、江戸時代からサクラソウの名勝地として人々に親しまれてきた。しかし、度重なる治水工事や工場の開発などによって、原野の植生が変わり、サクラソウの群落も範囲を狭められていった。この群落を守るため、大正9年(1920年)に天然記念物に、昭和25年(1950年)に特別天然記念物に指定された。
(2)プリムラ・マラコイデス(西洋サクラソウ)
http://www.yasashi.info/hu_00008.htm
中国雲南省、四川省に分布するサクラソウの仲間です。本来毎年咲く多年草ですが、高温多湿に弱く花後に枯れてしまうことが多いため、園芸では一年草として扱うことが多いです。秋にタネをまいて翌春の花を楽しむのが一般的です。日本へはヨーロッパ経由で明治末に渡来しました。葉や茎に白い粉が付くので、ケジョウザクラ(化粧桜)の和名があります。
野生種は草丈20cm~50cm、主な開花期は早春~春です。花茎を長く伸ばして段状にたくさんの花を付けます。花茎は3cm~5cm、色はピンク、淡紫、白などがあります。多くの園芸品種があり、草丈、花の色や大きさなどは様々です。サクラソウの名前で苗が流通することも多いですが、従来のサクラソウ(日本サクラソウ)とは別種の植物です。
20世紀前半にイギリスを中心に品種改良が行われた。

7番目の写真はフロリアード2012でオランダのベアトリクス女王陛下とその足元にある石塚園芸のサクラソウ3種の写真です。2012年4月に撮った写真です。
日本古来の楚々とした花々よりも華麗な西洋の花々の方が美しいと思う人が圧倒的に多くなってきました。何故か淋しい思いをする私は、時代に取り残された人間なのでしょうか?
そんな想いを込めて今日は日本サクラソウと西洋サクラソウの花の写真をご紹介致します。
数年前に可憐な日本サクラソウに魅了され埼玉県の自生地の「田島ヶ原」へ毎年、足を運んだ時代がありました。4月になるとまだ花が咲いていないかと何度も通ったものです。

1番目の写真は2008年の4月に田島ヶ原で撮った日本サクラソウの写真です。ここは江戸時代から有名な自生地なのです。

2番目の写真は田島ヶ原でサクラソウが密生している場所を探して撮った写真です。
広い草原に細い歩道がめぐらせたあります。その歩道を春風に吹かれながら歩いて行くと青草の間に小さなサクラソウが控えめに咲いています。
しみじみ美しいと思います。
そこで日本サクラソウの花を買おうと隣町の石塚園芸を訪問しました。
しかしニホンサクラソウの姿がありません。皆無です。
その代わり西洋サクラソウの花が広い温室いっぱいに咲いていたのです。
石塚園芸へ家内と何度も行っているうちにご主人の石塚健壽さんとは親しくなりました。
彼はいろいろな意味で感動的な花の栽培家だったのです。精魂こめて交配し20種の西洋サクラソウの新種を作ったのです。
そして新種の西洋サクラソウをオランダの新種の花の祭典、フロリアード2012へ出展し、金賞一席と特別賞を受賞したのです。

3番目の写真は2012年に特別賞受賞の湖畔の夢です。帰りがけに石塚さんが私に一鉢下さいました。

4番目の写真は石塚園芸の温室内に咲いている西洋サクラソウです。交配して作った白い花も見えます。

5番目の写真も石塚園芸の温室内に咲いている西洋サクラソウです。「湖畔の夢」が溢れています。このような温室が3棟あります。そして春に種を植え、大切に育てて12月の末から1月いっぱい花が咲くのです。
3棟ある温室はシクラメンの栽培とサクラソウの栽培の季節が違うので使いわけるそうです。
石塚健壽さんにニホンサクラソウは何故売っていないのですかと聞きました。
日本サクラソウも美しいと思いますよ。しかし圧倒的に多くの人が西洋サクラソウの方が綺麗だと思っているようですよ。とにかく売れるのです。こんなに一杯ある西洋サクラソウが1月になるとアッと言う間に売れてしまうのです。その花を囲んだ家族の笑顔を想像するとこの商売が止められないのです。こんなことを言っていました。
昨日も石塚健壽さんに会ってきましたが現在はシクラメンの季節でサクラソウはまだ咲いていませんでした。
サクラソウといい、シクラメンとといい、日本の家々に飾ってあるのは多くは西洋の花々になっています。
何故か淋しい思いをする私は、時代に取り残された人間なのでしょうか?
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)
===参考資料=======================
(1)ニホンサクラソウの栽培の歴史、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%82%A6
江戸時代の中ごろから、荒川の原野に野生するサクラソウから本格的な栽培が始まり、種子まきを繰り返すうちに、白、桃、紅、紫、絞りなどの色変わりや、大小さまざまな花形の変わり品が生まれ、名称が付けられた。やがて江戸時代後半になると品種数も非常に増え、文化元年(1804年)から新花を持ち寄り品評することが始まった。栽培者は旗本や御家人など武士階級が多く、「連(れん)」と呼ばれる2~3のグループが成立し、新品種の作出を競い合った。文化から天保(1804年~1844年)にかけてがもっとも盛んな時代であった。熱心な女性の愛好家もいて、寒天を流し固めた重箱に一品種ずつ挿し並べて鑑賞したという文献もある。幕末には各地に広まり、文久2年(1866年)にはサクラソウとしては現存最古の番付が発行されている。現在栽培される約300品種のうち、その半数が江戸時代から株分けで伝えられたもので、その花は多様な花型と繊細な花色が特徴で、他の多くの日本の伝統的な園芸植物と共通している。品種ごとに鉢植えで育て、花時には「花壇」と呼ばれる屋根付きの五段構造の展示台に配色よく飾る。鉢は「孫半土(まごはんど)」という、本来食品容器として作られた瀬戸焼の陶器が使われた。これはサクラソウのデリケートな花色をよく引き立てる。
愛好者層が武士中心であったので、明治維新前後には衰退の危機にも見舞われたが、やがて愛好者も増え、新花の作出も再び盛んになった。この頃に生まれた名花にも今に伝えられているものがある。やがて太平洋戦争により、サクラソウの栽培も下火になったが、戦後次第に復興し、昭和31年(1956年)に愛好者のグループである「さくらそう会」が発足、関西にも「浪華さくらそう会」が生まれた。この他全国各地に愛好会ができ、今に続いている。

6番目の写真は田島ヶ原サクラソウ自生地の写真です。
埼玉県さいたま市桜区の「田島ヶ原サクラソウ自生地」は国の特別天然記念物に指定されている貴重な群落である(桜区の区名も桜ではなくサクラソウに因んで命名されている)。荒川流域のこの一帯は、下流の戸田ヶ原、浮間ヶ原などとともに、江戸時代からサクラソウの名勝地として人々に親しまれてきた。しかし、度重なる治水工事や工場の開発などによって、原野の植生が変わり、サクラソウの群落も範囲を狭められていった。この群落を守るため、大正9年(1920年)に天然記念物に、昭和25年(1950年)に特別天然記念物に指定された。
(2)プリムラ・マラコイデス(西洋サクラソウ)
http://www.yasashi.info/hu_00008.htm
中国雲南省、四川省に分布するサクラソウの仲間です。本来毎年咲く多年草ですが、高温多湿に弱く花後に枯れてしまうことが多いため、園芸では一年草として扱うことが多いです。秋にタネをまいて翌春の花を楽しむのが一般的です。日本へはヨーロッパ経由で明治末に渡来しました。葉や茎に白い粉が付くので、ケジョウザクラ(化粧桜)の和名があります。
野生種は草丈20cm~50cm、主な開花期は早春~春です。花茎を長く伸ばして段状にたくさんの花を付けます。花茎は3cm~5cm、色はピンク、淡紫、白などがあります。多くの園芸品種があり、草丈、花の色や大きさなどは様々です。サクラソウの名前で苗が流通することも多いですが、従来のサクラソウ(日本サクラソウ)とは別種の植物です。
20世紀前半にイギリスを中心に品種改良が行われた。

7番目の写真はフロリアード2012でオランダのベアトリクス女王陛下とその足元にある石塚園芸のサクラソウ3種の写真です。2012年4月に撮った写真です。