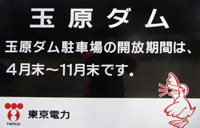5年ほど前から我が家にきたサルビアミクロフィラホットリップスが
今年も満開になった。
メキシコ原産のチェリーセージの仲間で宿根サルビア。
ホットリップスはサルビアミクロフィラの園芸種。
この花は気温によって花の色が変わる。
一年の内でも、いろいろ花色の変化が楽しめる。
シロ科サルビア属
2013年5月11日




↓ 2013年4月30日のホットミックス
10日ほど前になるが、赤味が強い唇形の花だった。


ネット検索すると、サルビアミクロフィラホットリップスは
気温が高くなると赤味が増すと言うが、
我が家では気温が増すと白味が増えた。
どうなるか今後観察していこうと思う。
閲覧有難うございました。
コメント欄閉じています。
昨年のアル 12歳の誕生日に
サルビアミクロフィラホットリップスの前で
二ヶ月前に大手術を受けたが、元気に回復した頃の一枚。