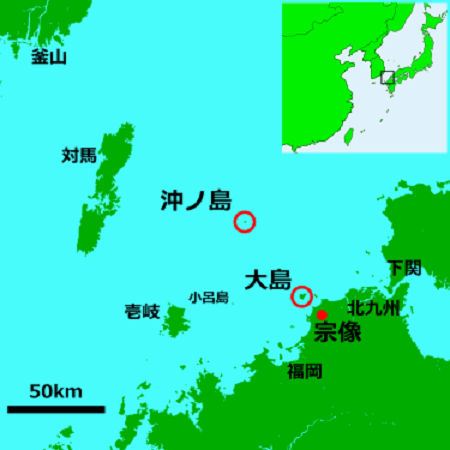昨年に続いて2度目のビアパーティだった。参加者は昨年より少なかったが、和やかに楽しいひと時を過ごした。会の中では、マンションコミュニティを築くための貴重な意見もいただいた有意義なパーティーだった。
近代美術館前の歩道の清掃ボランティアに取り組んでいる「近美を愛するブリリアの会」では、昨年初めて懇親のためのビアパーティを開催した。ところが時期を逸し、8月31日に開催したこともあり、「往く夏を惜しむ会」と称しての開催だった。
今年は夏の盛りの開催ということで「納涼ビアパーティ」と称して昨日10日(金)に開催した。
会場は昨年に引き続き、ニューオータニイン札幌のダイニングラウンジで行った。
ニューオータニインには「カジュアルナイトフェア」と銘打って90分食べ飲み放題で2,900円というリーズナブルなコースがあり、私たちシニアにはちょうど良いコースがあるのだ。
参加者は日程の合わなかった方も多く7名の参加だった。

会はいつも陽気なMさんがリードする形で楽しく歓談が進んだ。
シニアの会らしく、身体のこと、孫のこと、マンションライフのこと、等々…。
そうした歓談の中で、Mさんから一つの提案があった。
「マンション入居以来、10年が経ちそれぞれ年齢を重ねて、かなりの方がシニア世代の仲間になってきた。その方々との交流の場があってもいいのでは?」
という提案だった。
私に異存はない。もともと私たちの「近美を愛するブリリアの会」もそうした思いを抱きながら呼びかけ、これまで活動を続けてきたのだ。ただ、残念なことにその輪が願っていたほど広がらなかった。(まあ、ボランティアに対するいろいろな思いがあるからだろうが…)
私は以前からマンション内にそれぞれのプライバシーを尊重しつつ、緩やかなマンションコミュニティが作れないものか、と考えていた。
Mさんの提案は大きな勇気をいただいたように思えた。
Mさんと相談しつつ、何らかの形でシニア世代の方々の交流の場ができないものか、少し考えてみたいと思った「納涼ビアパーティ」の夜だった。