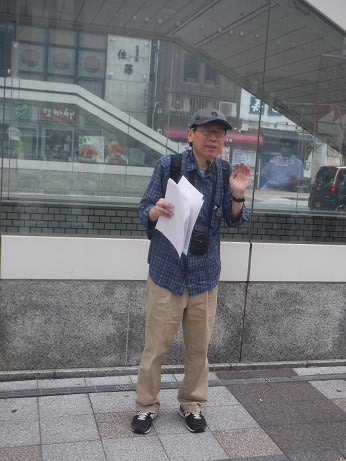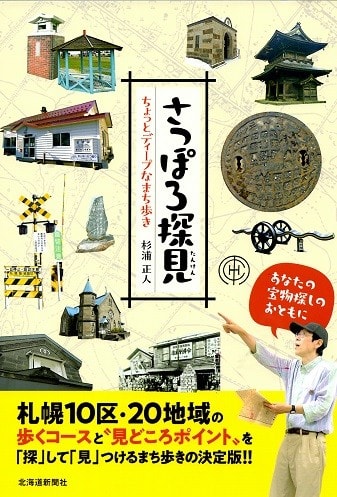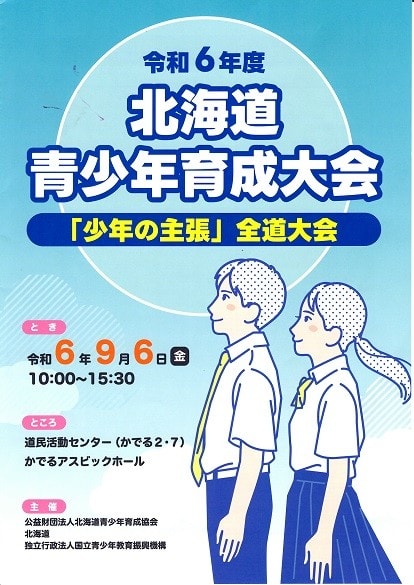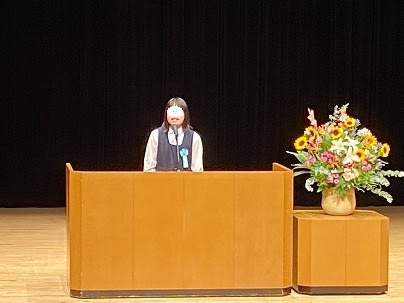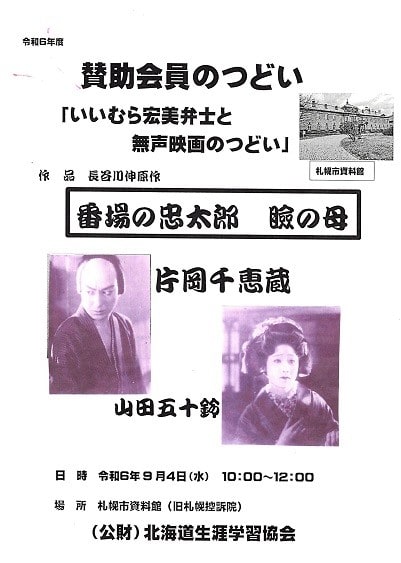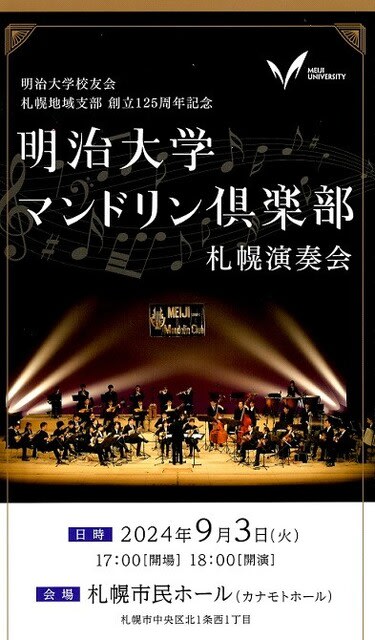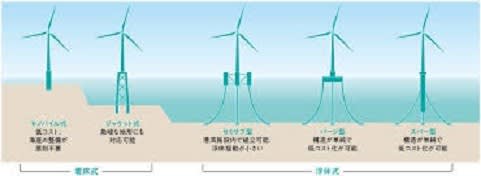興味あるとは…、札幌市民芸術祭「ギター音楽祭」はコンペティション形式をとっていることだ。ステージに上がったギター奏者の演奏は市民芸術祭大賞や市民芸術祭奨励賞の対象となっているのである。
9月8日(日)午後、札幌コンサートホールKitaraの小ホールにおいて札幌市民芸術祭の「ギター音楽祭」が開催され、昨年に引き続いて鑑賞した。ギター音楽祭は「独奏部門」には〈小学生の部〉に3名、〈一般の部〉に7名の参加があり、「合奏部門」に4つの団体が参加した。このうち、〈一般の部〉が大賞や奨励賞の対象となるという告知だった。
昨年は私が最も優れた演奏だと思われた方が奨励賞に輝いたのをみて、「これは面白い企画だな」と思ったのだが、今年も7名の中から「果たして大賞や奨励賞を受賞する奏者が現れるだろうか?」という興味を持ちながら演奏に聴き入った。
〈一般の部〉の出場者は、予めオーデションが行われて通過した人だけが出場できるという仕組みだけあって、出場者のレベルは高かった。昨年度奨励賞を獲得した那須朱音さんも大賞に挑戦するため7名の一人として登場した。
私は私なりに個人的な感想をメモしながら各人の演奏に聴き入った。そのメモには次のような記述が残っている。「う~ん」、「テクニックは相当。やや硬かった?」、「情感のこもった演奏。2曲目が…」、「歳に似合わず若々しく」、「ただ弾いていただけ?」、「聴かせた演奏。あるいは?」、「さすが!」などにメモが残った。
那須さんの演奏は、やはり他の出場者と比べると一段上のレベルの演奏と感じられ、私の感想は最後の「さすが!」だったが、残念ながら大賞とはならなかった。
残り6名であるが、3番目の演奏は1曲目が情感のこもった演奏で良かったのだが、2曲目に明らかなミスが2~3度あったのが残念だった。その点、6番目の演奏者は演奏技術も表現もまとまった演奏に聴こえた。
演奏会の最後に審査員から結果が公表されたが、残念ながら今年は大賞も、奨励賞の対象者は無しという残念な結果となった。しかし、惜しくも受賞を逃した方もいたという講評があったが、それがどなただったのかは知る由もないが、あるいは私が「惜しい!」と感じた方だったのでは?などと夢想している。
大賞、奨励賞の対象外だった〈小学生の部〉や「合奏部門」も楽しませてもらった。小学生の段階からクラシックギターに親しむことは将来楽しみである。
「合奏部門」は、ギター教室等の指導者がいる教室の合奏が主であったが、「札幌室内ギター合奏団」はサークル的集まりのグループだったが、会員の高齢化が顕著だった。若者のクラシック離れが背景にあるような気がした。
札幌市民芸術祭の「ギター音楽祭」…、ただ聴くだけではなくて結果を予想しながら聴くという企画は、なかなか興味深いものである。